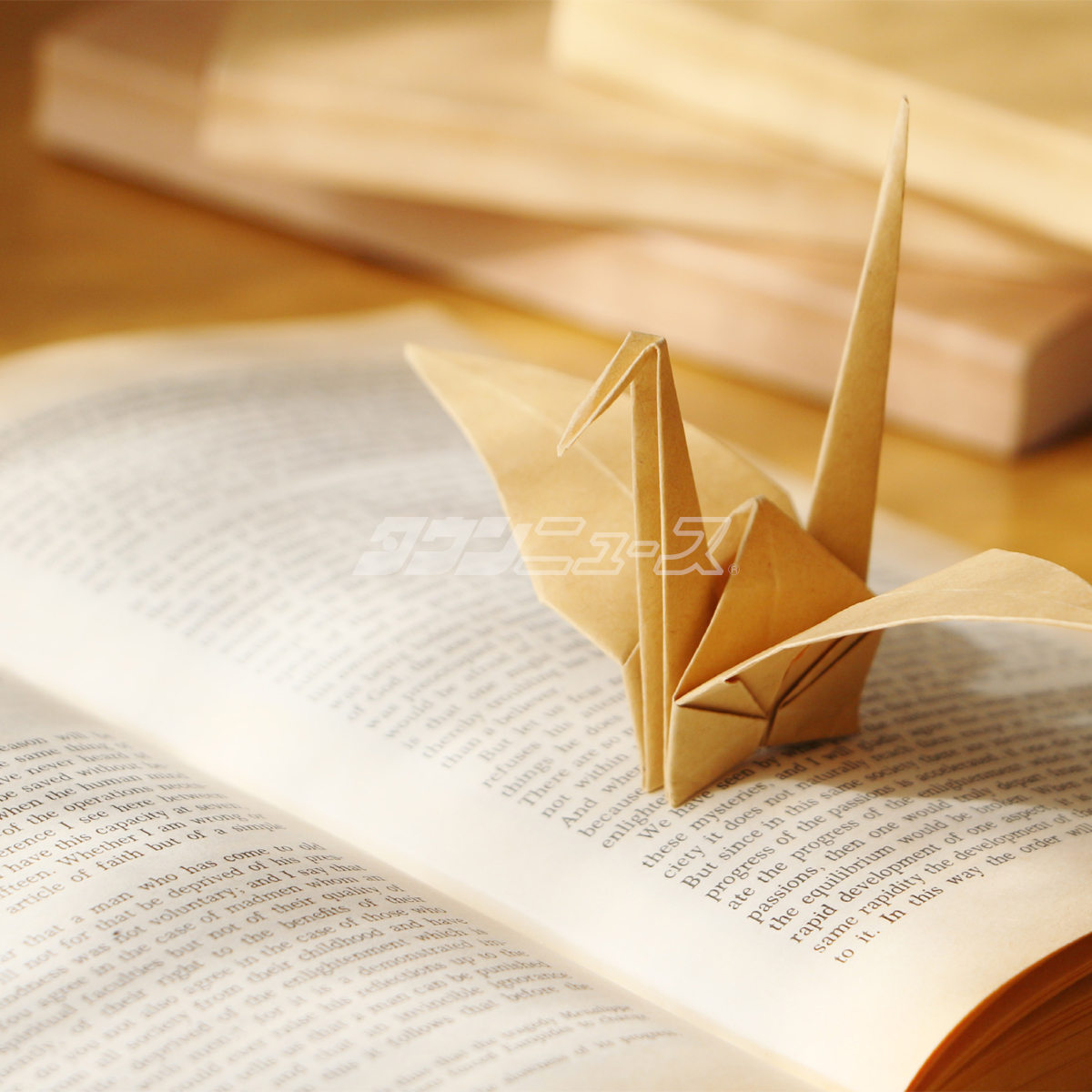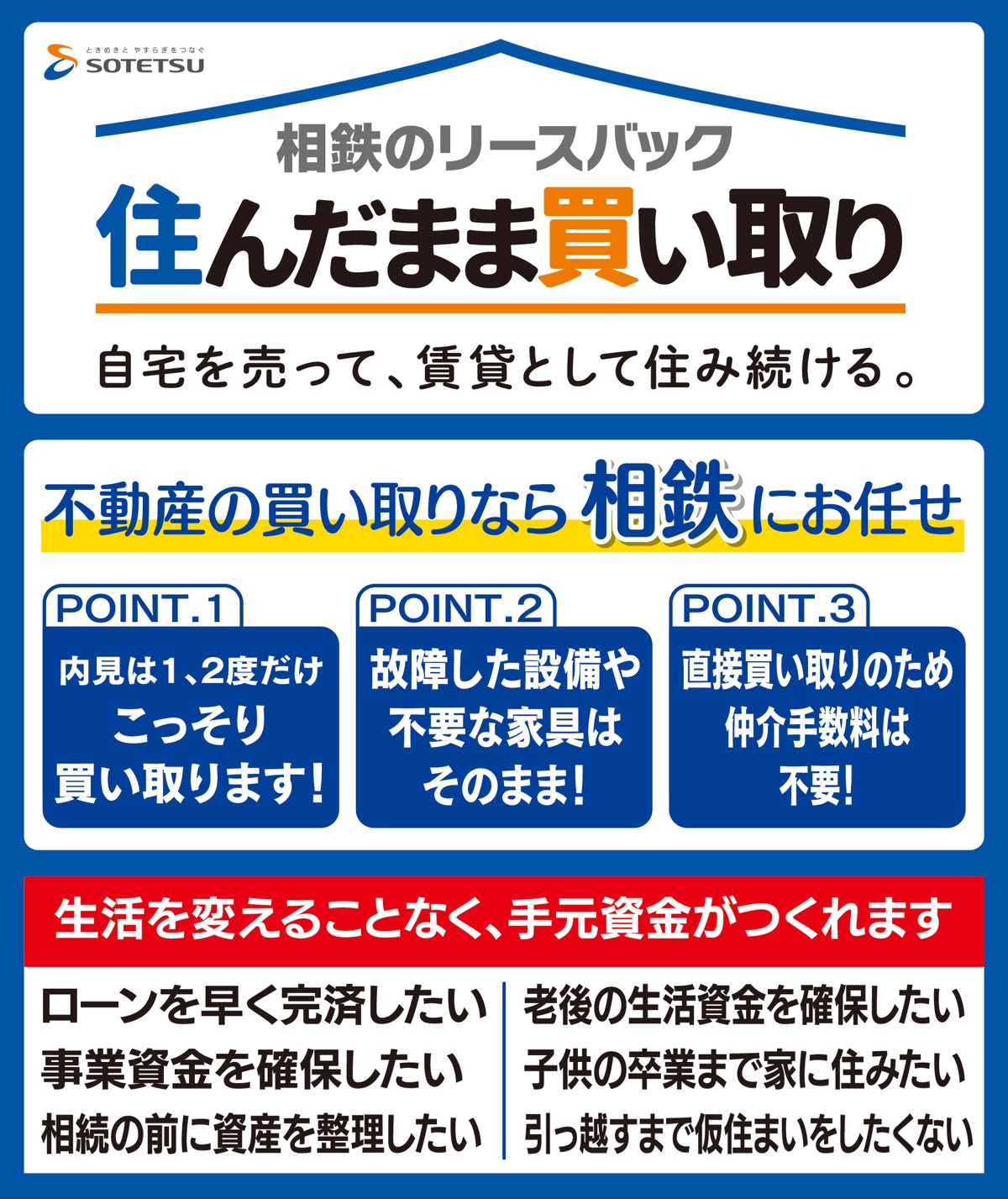港北区 社会
公開日:2025.06.19
95歳 大工が見た戦禍
大豆戸町在住 武田信治さん
「舟もお宮も作ってね。この家も自分で建てた」。大豆戸町在住の武田信治さん(95)は、大工の棟梁としてさまざまな建築業に従事。鶴見川に和舟を浮かべる「舟運復活プロジェクト」にも携わり、舟の制作も手がけた。大工仕事は天職。しかし、戦時中は職業も自由に選べなかった。
1944年3月、大綱国民学校高等科卒業間近のとき、「将来は何になる」と先生に問われ、父の跡を継ごうと「大工」と答えた。小売業や中小企業は整理され、非軍事部門への就職は制限されていた時代。「この非常時にとんでもない」と一喝され、軍需工場として魚雷の部品などを作っていた天野製作所(現アマノ株式会社=大豆戸町)に歯切工として配置された。鍋や雨樋、寺の釣り鐘が供出され、手作業で歯車を作る日々。「カッターで一つずつ削って、何時間もかかって1つ作って。こんなことで戦争に間に合うのかなと、子ども心に思ったねえ」
軍需関係の企業は技能養成が義務付けられ、外部の学校と提携する企業もあった。天野製作所には社内に青年学校があり「社長が教育熱心だったのか、そんな時分でも教科書もあり、仕事前に授業があった」。卒業後は藤原工業大学付属の機械科(慶應義塾大学工学部の前身)夜間部に入学。「交通費、授業料は会社が持ってくれた。『公用外出』の印をもらって大手を振って通ったよ」
焼け跡、目の前に
「物心ついた頃から戦争一色。平和とか幸福とか、考える余地がなかった」。空襲が激しさを増す4月15日未明、遠くの空が赤く染まっていた。「あれは菅田じゃないか」。菅田町(神奈川区)にある母の実家は、250kg爆弾と焼夷弾多数の直撃を受けた。防空壕に逃げ込んだ祖父と叔父は大やけどを負い、祖母と叔母が犠牲になった。家は跡形もなくなり、遺体は翌日土葬にした。
5月29日は早朝から警戒警報が出た。防空壕から様子を見ると「横浜の中心部の方は日食のように真っ暗。燃えているところは雲に反射して赤く見えた」。戦闘機が、搭乗員の顔が見えるほどの低空で何機も飛来した。「恐ろしかった。こちらからは迎撃もない。菊名にあった高射砲も移動してしまったらしく、ただ焼かれていくだけだった」。社命で菊名にある社員寮を見に行くことになり向かうと、辺り一面焼け野原。家も寺もまっ平らになり、何も残っていなかった。東神奈川の駅まで行くと電車や自動車が焼け、道路には黒い塊が転がっていた。よく見ると人だとわかった。「その時は怖いとも思わなかった」。燃え盛るなか逃げ場がなかったのか、水場には折り重なった焼死体が山のようになっていた。
「日本のどこかに新型爆弾が落ちたらしい」。広島に原爆が投下されてからは、綿入れをかぶり防空壕で過ごした。ほどなく終戦を迎え、戦後は大工として焼け跡の家を建て直してきた。「時代が違うからどんなに悲劇かわからないかもしれないが、戦争は決してしてはいけない。残酷で悲惨なものと伝えたい」
※ ※ ※
今年で戦後80年。当事者の記憶を後世に残すとともに平和の意義について考える。不定期で連載。
ピックアップ
意見広告・議会報告
港北区 ローカルニュースの新着記事
コラム
求人特集
- LINE・メール版 タウンニュース読者限定
毎月計30名様に
Amazonギフトカード
プレゼント! -

あなたの街の話題のニュースや
お得な情報などを、LINEやメールで
無料でお届けします。
通知で見逃しも防げて便利です!