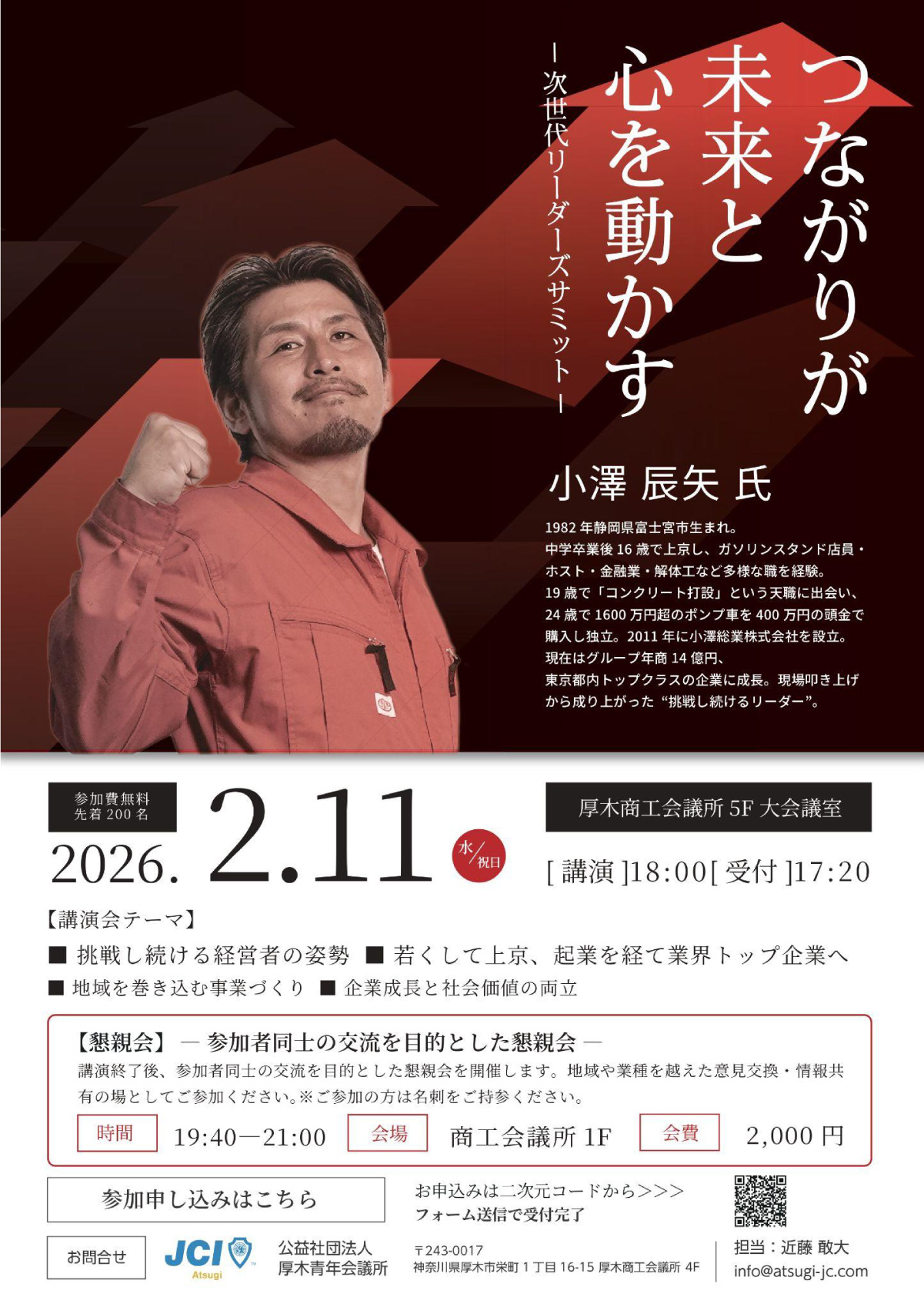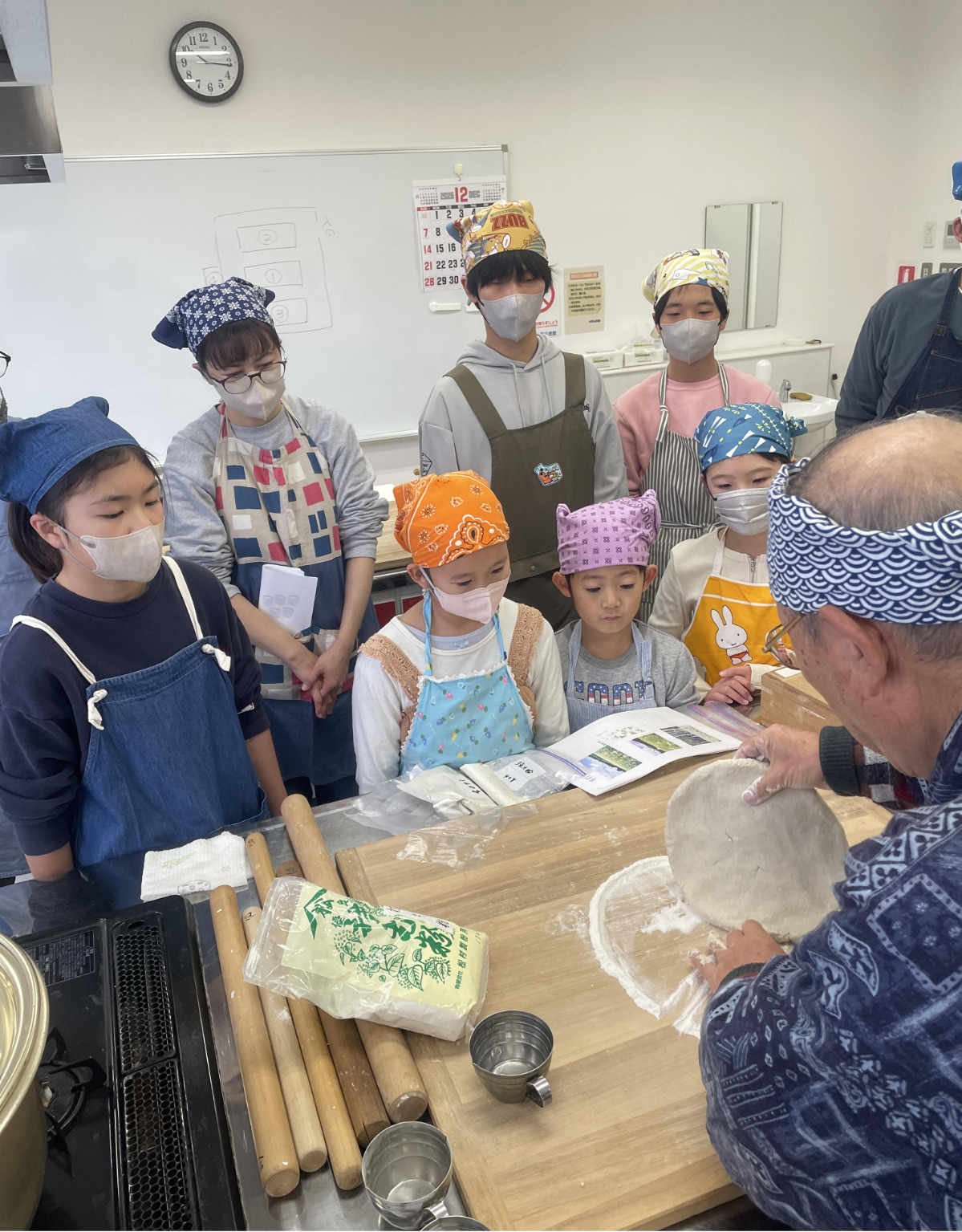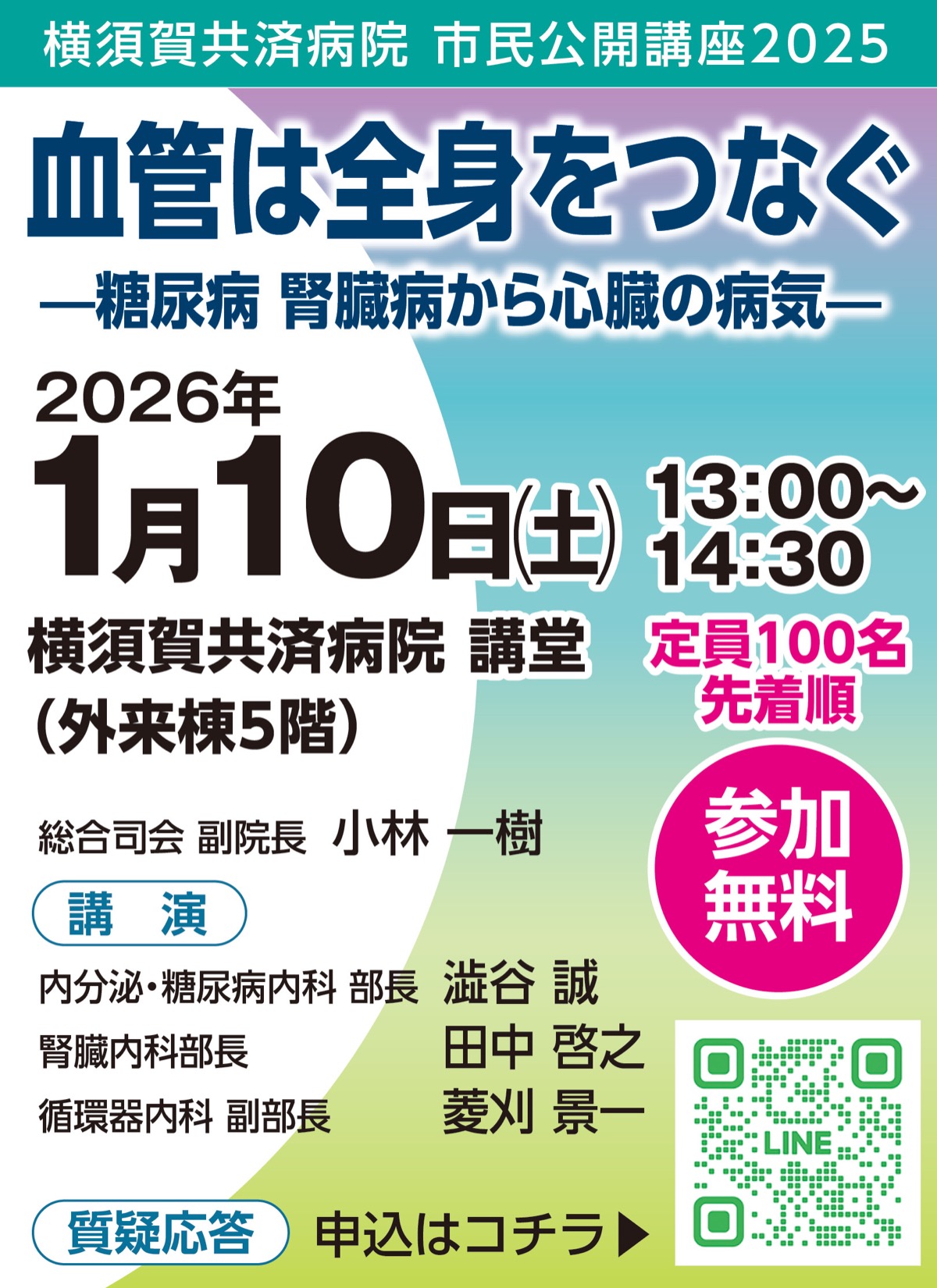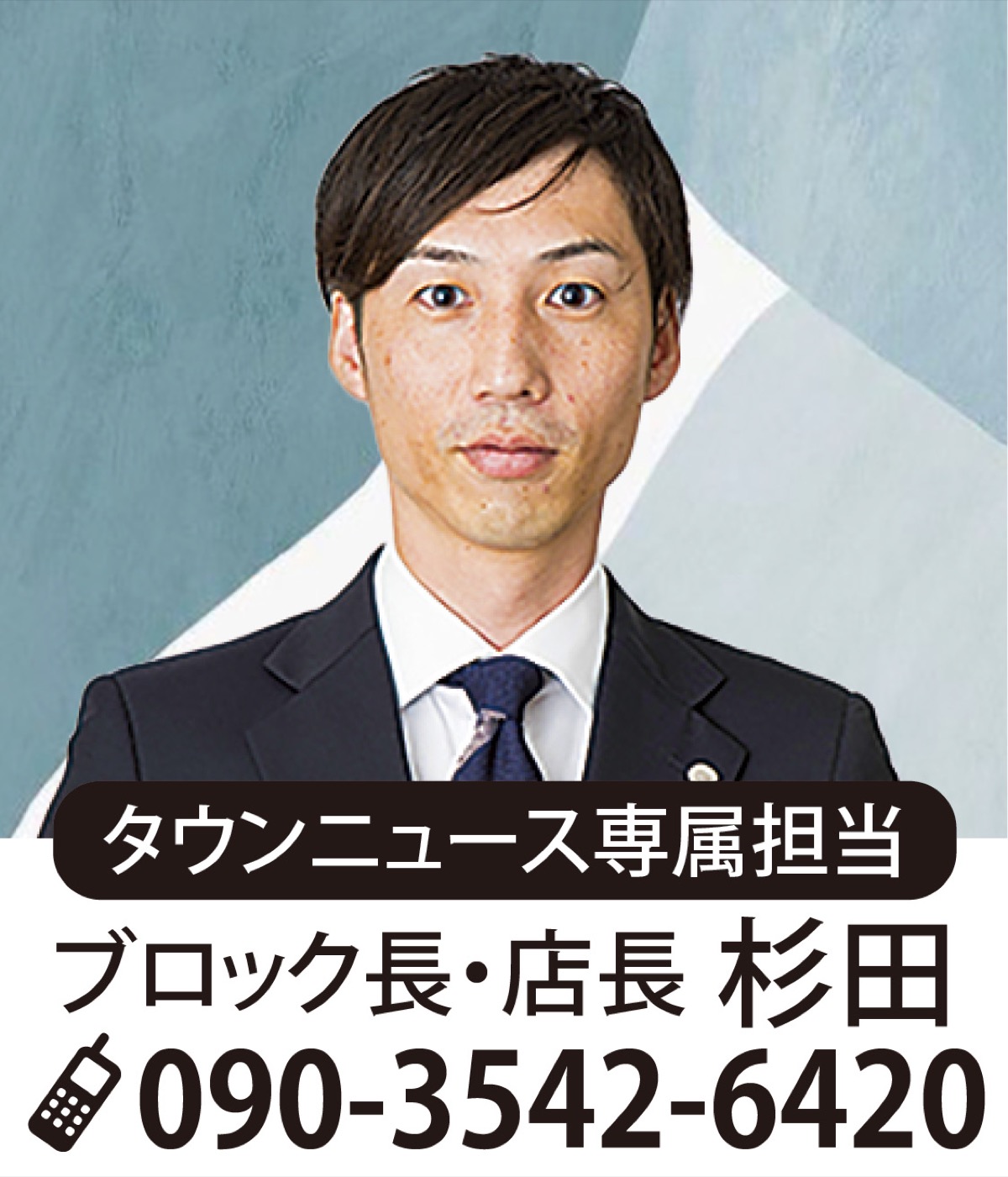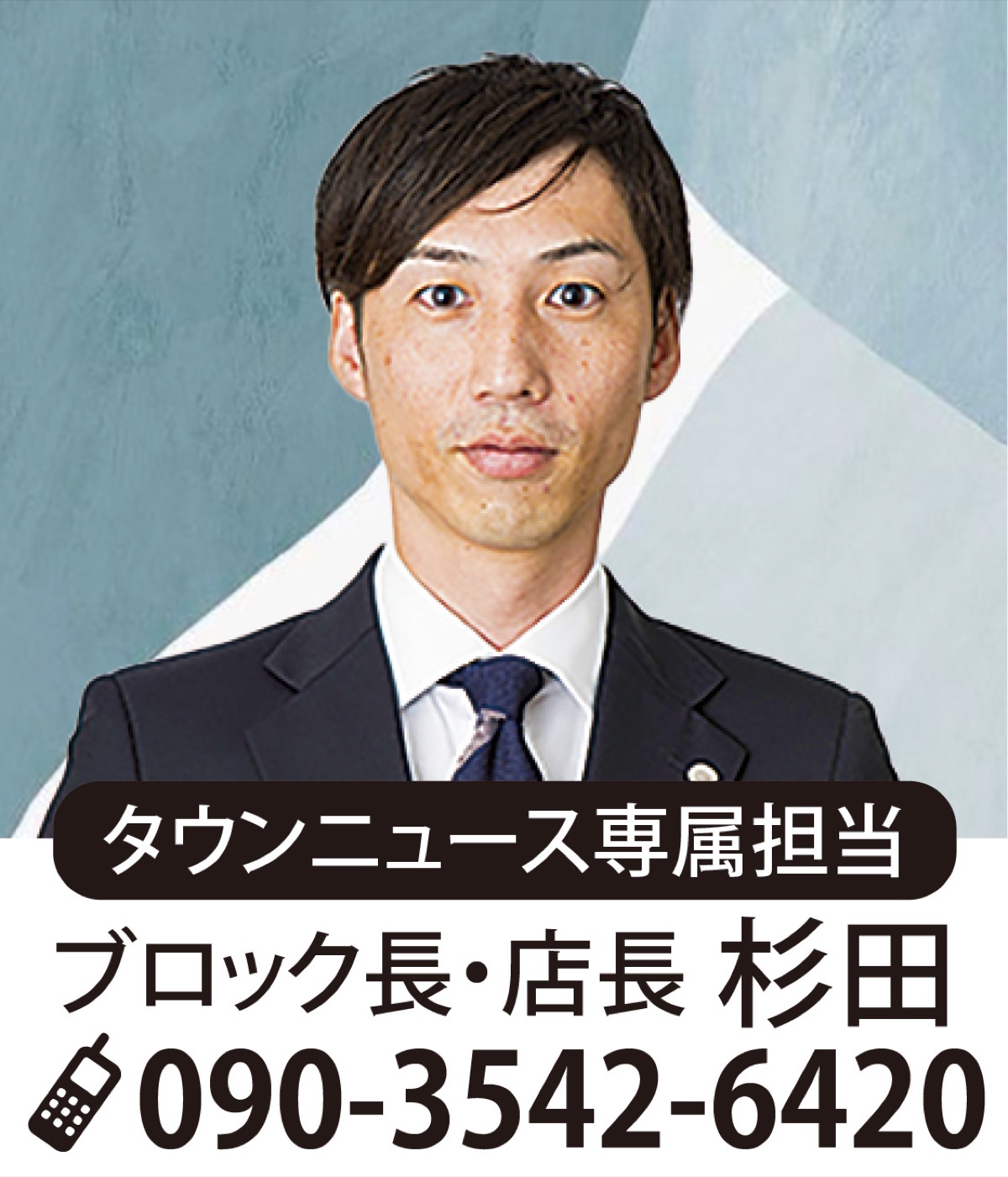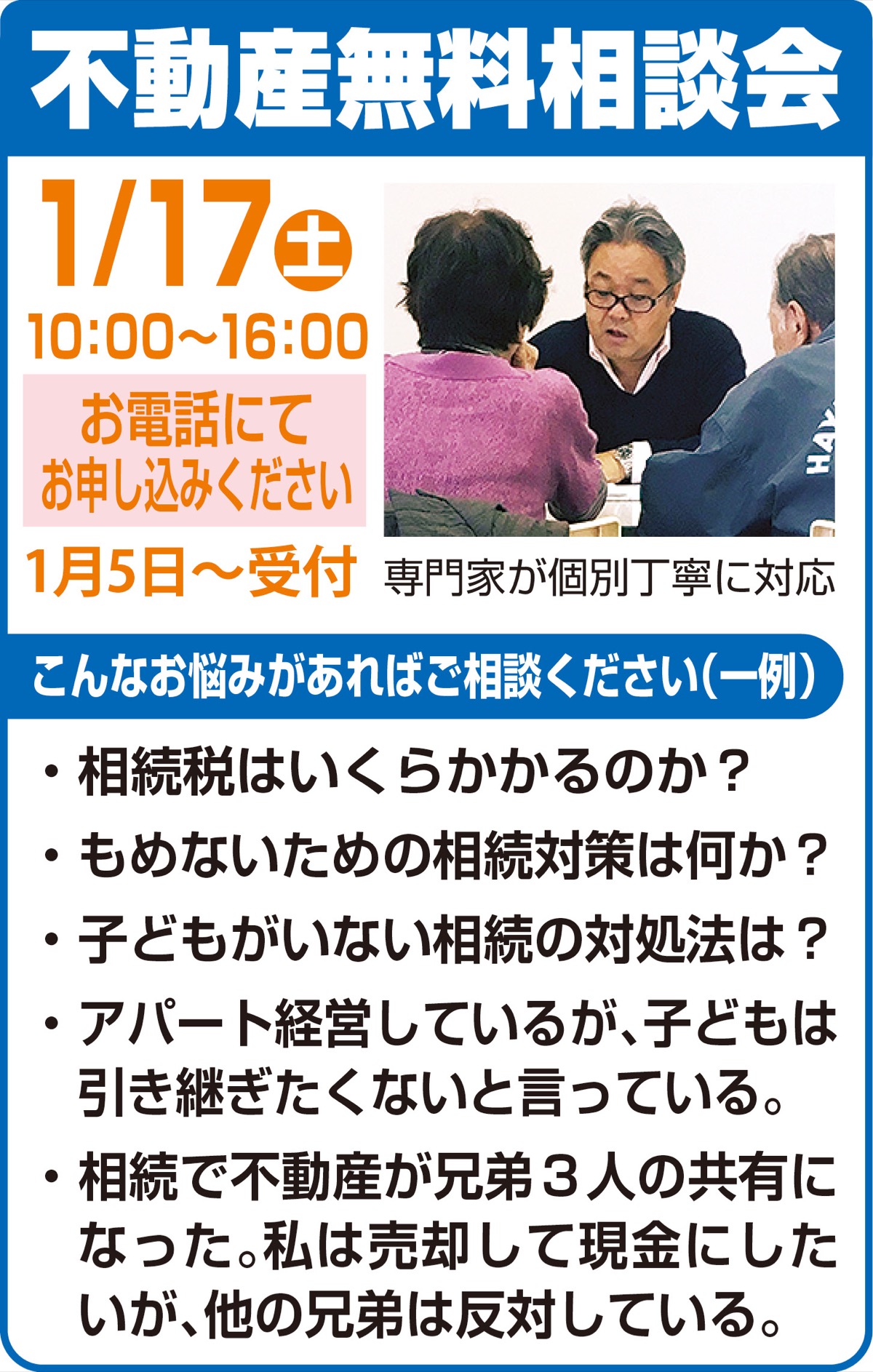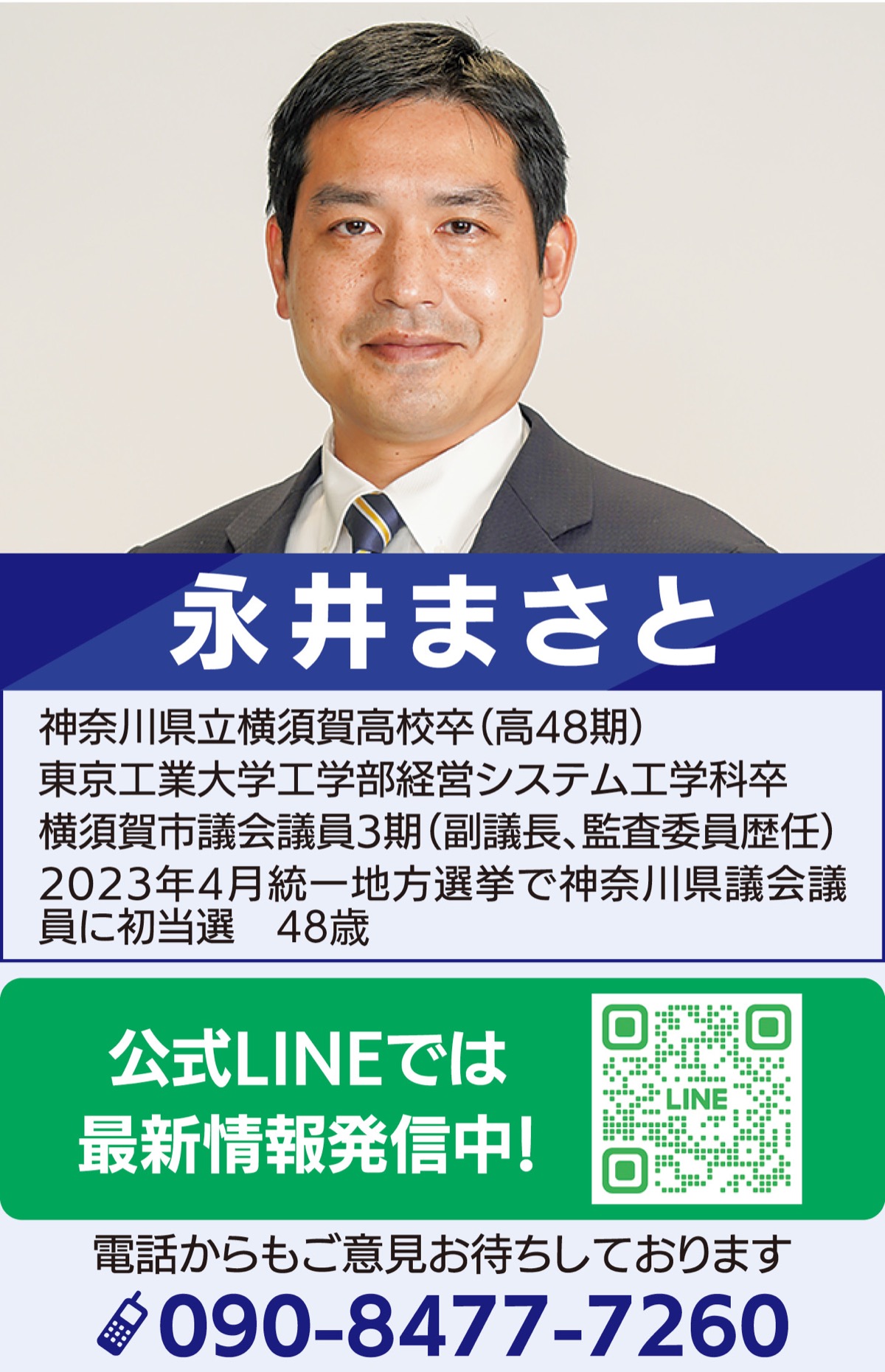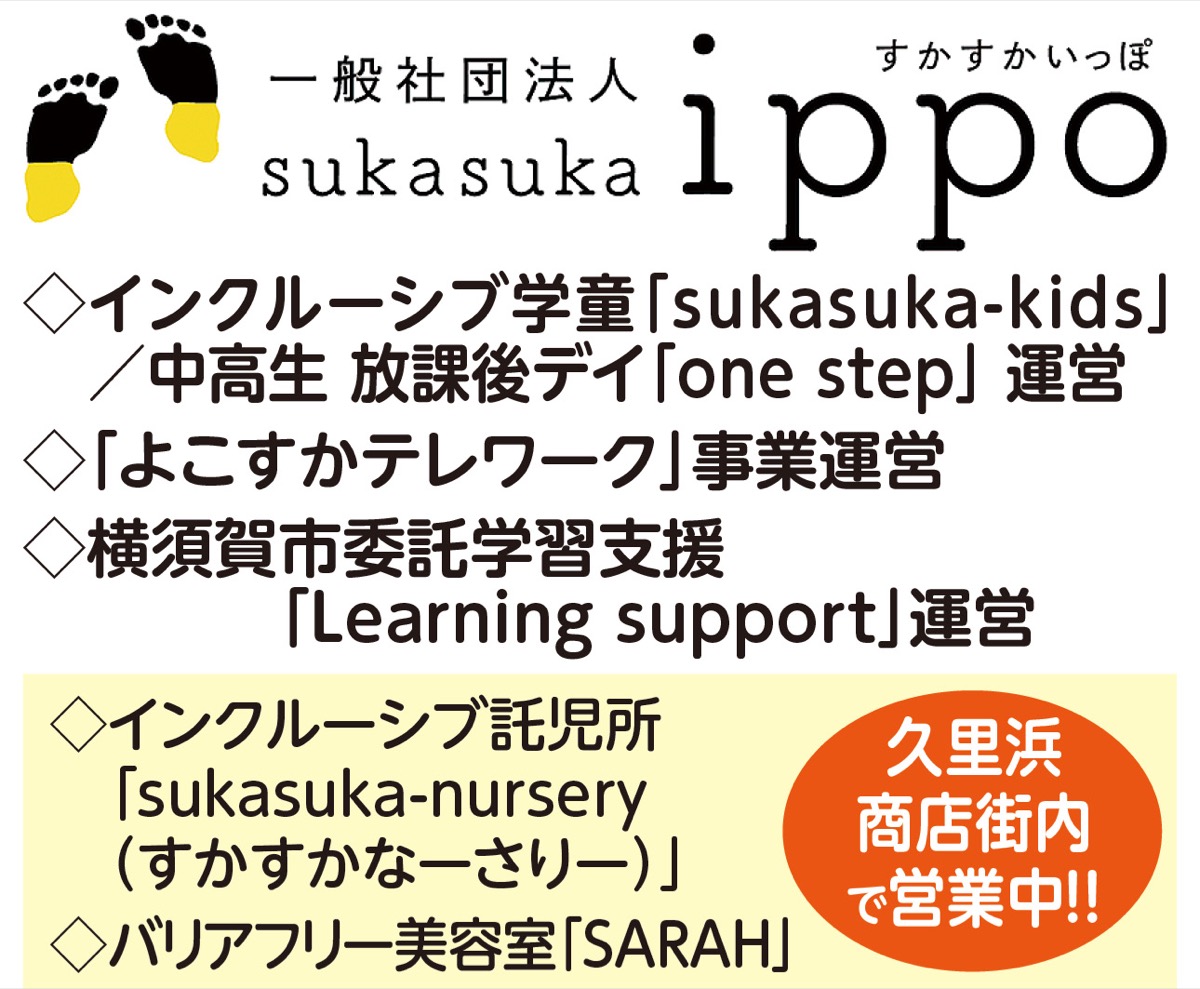横須賀・三浦 ピックアップ(PR)
公開日:2022.06.24
神歯大附属病院
「認知症=もの忘れ」は誤解
正しく理解が治療の第一歩
国内の認知症患者数は増加の一途をたどっており、今や600万人を超えている。65歳以上の高齢者では、6人に一人が発症しており、身近な症状といえる。一方で、流言や誤解に基づく情報も多く、誤った予防法や接し方により状態を悪化させてしまうことが少なくない。神奈川歯科大学附属病院 認知症・高齢者総合内科の眞鍋雄太教授=写真=に話を聞いた。
* * * *
「先ず大前提として『認知症』は病気の名前ではない」と眞鍋教授。「症」の言葉が示すように、何らかの病気を原因に認知機能障害が生じ、その結果、社会生活に支障を来している状態をそう呼ぶのだという。
もう一つ、多くの人が誤解しているのが「認知症=もの忘れ」という理解。とっさに人の名前が思い出せなくなるなど、老化現象による物忘れもあり、「問題なく社会生活を送れているのであれば、心配することはない」と眞鍋教授は説明している。原因となる病気ごとに認知症の症状は異なり、もの忘れがなくても理解力や判断力の低下によって、反社会的な行動を取ってしまう「物忘れのない認知症」も存在するという。
認知症を正しく理解することが治療の第一歩であり、同院では、日本認知症学会専門医が見極めの難しい認知症の診断と治療を行っている。
神奈川歯科大学附属病院
-
横須賀市小川町1-23
TEL:046-822-8877
ピックアップ
意見広告・議会報告
横須賀・三浦 ピックアップ(PR)の新着記事
コラム
求人特集
- LINE・メール版 タウンニュース読者限定
毎月計30名様に
Amazonギフトカード
プレゼント! -

あなたの街の話題のニュースや
お得な情報などを、LINEやメールで
無料でお届けします。
通知で見逃しも防げて便利です!