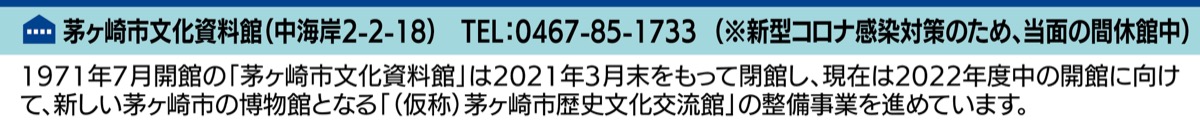茅ヶ崎・寒川 コラム
公開日:2021.01.15
茅ヶ崎市文化資料館
おうちでミュージアム
連載Vol.8
冬の風物詩 こたつの今昔
今回は冬の風物詩ともいえるこたつの今昔を紹介します。電気やガスが普及する前のこたつは炭火にやぐらを被せ、その上から布団をかけて使いました。床に作り付けた炉を熱源にしてやぐらを乗せて使う「切りごたつ」や「腰掛けごたつ(掘りごたつ)」以外に、やぐらの中に熱源を入れて持ち運ぶことができる「置きごたつ」などがありました。
文化資料館では置きごたつのやぐらを所蔵しています。炭は石炭の粉や海藻などを混ぜて練り固めた燃料である「豆炭(まめたん)」がよく使われました。安価な上、火力の調節がしやすく温かさも長続きしたため人気があったようです。しかし、炭火を使うこたつは火事や火傷の危険を伴うため、徐々に使われなくなりました。(」がよく使われました。豆炭は、石炭の粉や海藻を混ぜて練り固めた燃料で、安価な上、火力の調節がしやすく、温かさも長続きしたため人気があったようです。しかし、火事や火傷の危険を伴うため、主要燃料が石油やガスに移りゆく中で徐々に使われなくなりました。)
1960年代以降、椅子とテーブルを使う洋風の生活様式が広がり、近年は背の高いテーブル型のこたつも登場しました。姿を変えつつ冬の暮らしに寄り添ってきたこたつで、今年の冬はゆっくり過ごしてみては。
ピックアップ
意見広告・議会報告
茅ヶ崎・寒川 コラムの新着記事
コラム
求人特集
- LINE・メール版 タウンニュース読者限定
毎月計30名様に
Amazonギフトカード
プレゼント! -

あなたの街の話題のニュースや
お得な情報などを、LINEやメールで
無料でお届けします。
通知で見逃しも防げて便利です!