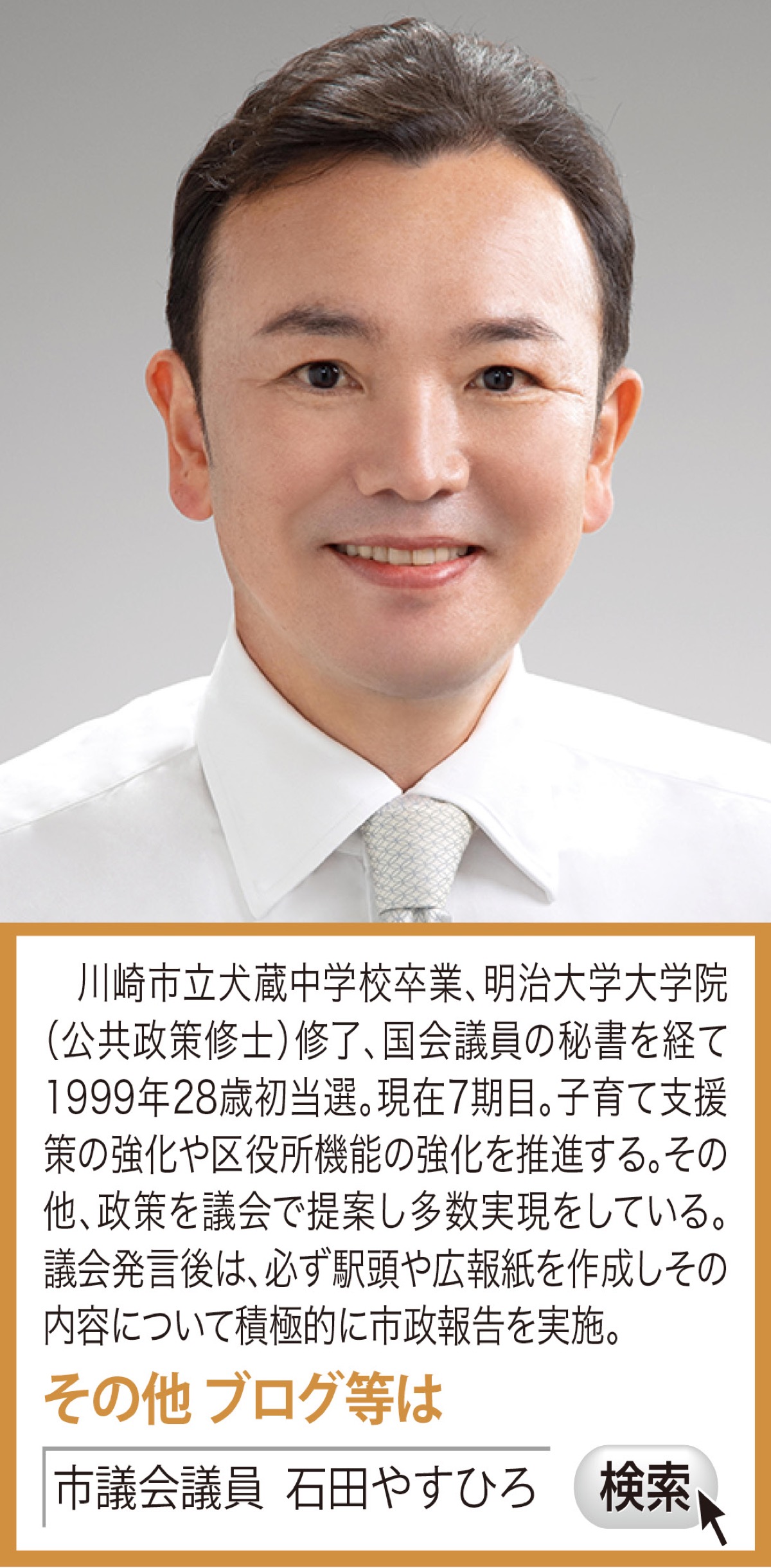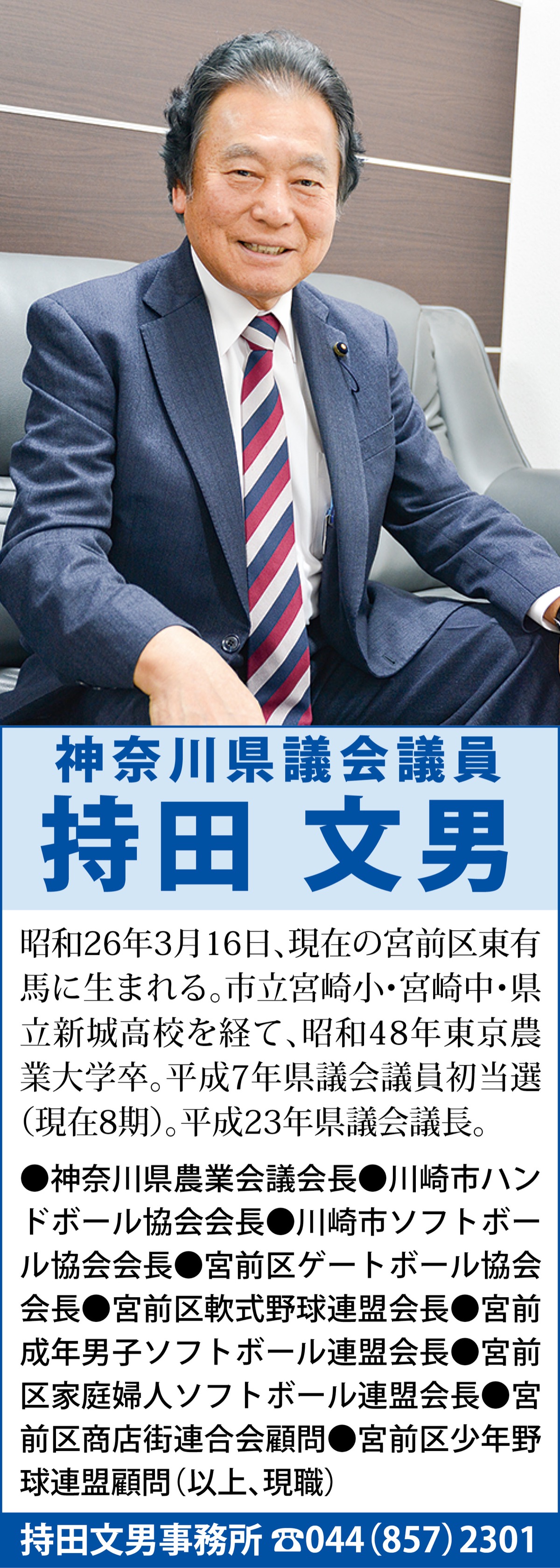宮前区 意見広告
公開日:2025.02.21
宮前ガバナンス2月号 連載寄稿
救急搬送はICTを活用して迅速に!
〜第4回川崎市議会定例会の一般質問立つ〜川崎市議会議員 石田 やすひろ
「ICT等のデジタル技術を活用した救急業務の効率化に関する実証実験」について消防局長に質しました。令和6年11月18日から、救急隊と医療機関との情報連携により、傷病者の救急搬送を的確に早くするための実証実験が行われています。本市において、救急隊が現場到着してから搬送先の医療機関が決まるまでの平均現場滞在時間は、約25分(令和5年)です。現場滞在時間の短縮に期待されているのがICTの導入です。
この実証実験は、北部3区の3署13隊、中部2区の2署7隊の救急隊で実施しています。民間事業者の情報共有システムを活用して、救急隊と医療機関との間で、年齢、性別、症状、病歴、体温、血圧等の傷病者情報を共有します。システムの機能の一つとして、OCR機能があります。これは、救急隊員がタブレット端末で傷病者の運転免許証等を撮影して、文字情報を取り込むものです。傷病者を医療機関に引き渡す際に、医師の署名や傷病名等の入力を、端末上で行うことができます。情報共有システムを活用することで、救急隊員の活動や医師への引継ぎを効率よく行うことが可能となります。
令和6年9月6日から11月6日までの2カ月間、市内全救急隊(30隊)で「マイナンバーカードを活用した救急業務に関する実証事業」を実施しました。11月6日以降は、南部2区の3署10隊の救急隊で継続して実施しています。この事業では、救急隊が搬送先医療機関の選定を行う際に、傷病者のマイナンバーカードを活用することで、病歴、受診歴、処方薬等の必要な情報を得ることができ、現場滞在時間の短縮に貢献するものとして期待されます。
本市の第3期実施計画における目標では、現場到着時間を8分、医療機関までの平均搬送時間を40分と定めています。ICTの活用は、搬送時間の短縮化や救急隊員による傷病者情報の収集と医療機関への情報伝達の効率化に資するものです。現場滞在時間の短縮化に向けて、令和7年度以降も積極的に取り組むことを求めました。
川崎市議会議員 石田やすひろ
-
川崎市宮前区馬絹6-24-26
TEL:044-861-6870
ピックアップ
意見広告・議会報告
宮前区 意見広告の新着記事
コラム
求人特集
- LINE・メール版 タウンニュース読者限定
毎月計30名様に
Amazonギフトカード
プレゼント! -

あなたの街の話題のニュースや
お得な情報などを、LINEやメールで
無料でお届けします。
通知で見逃しも防げて便利です!