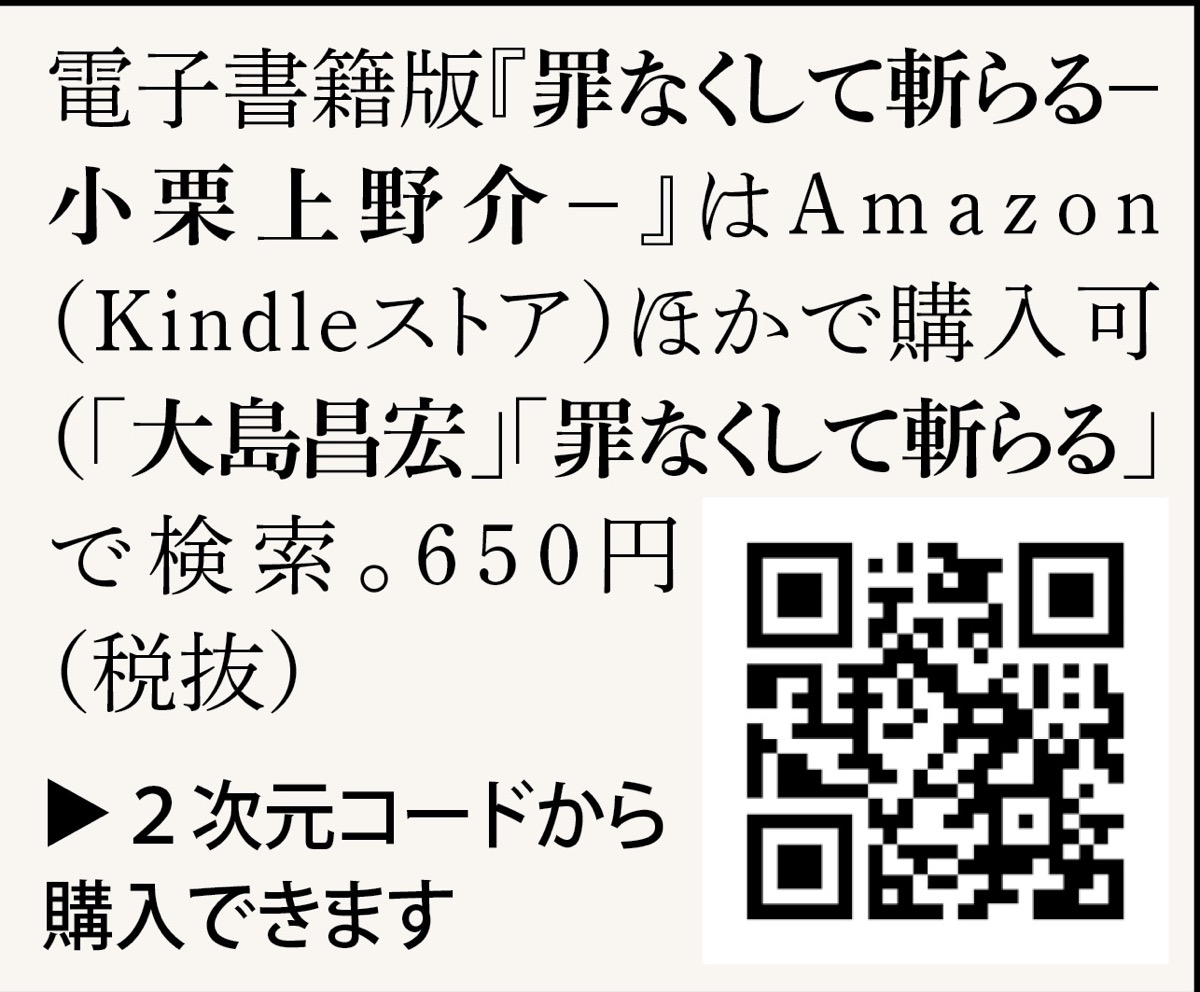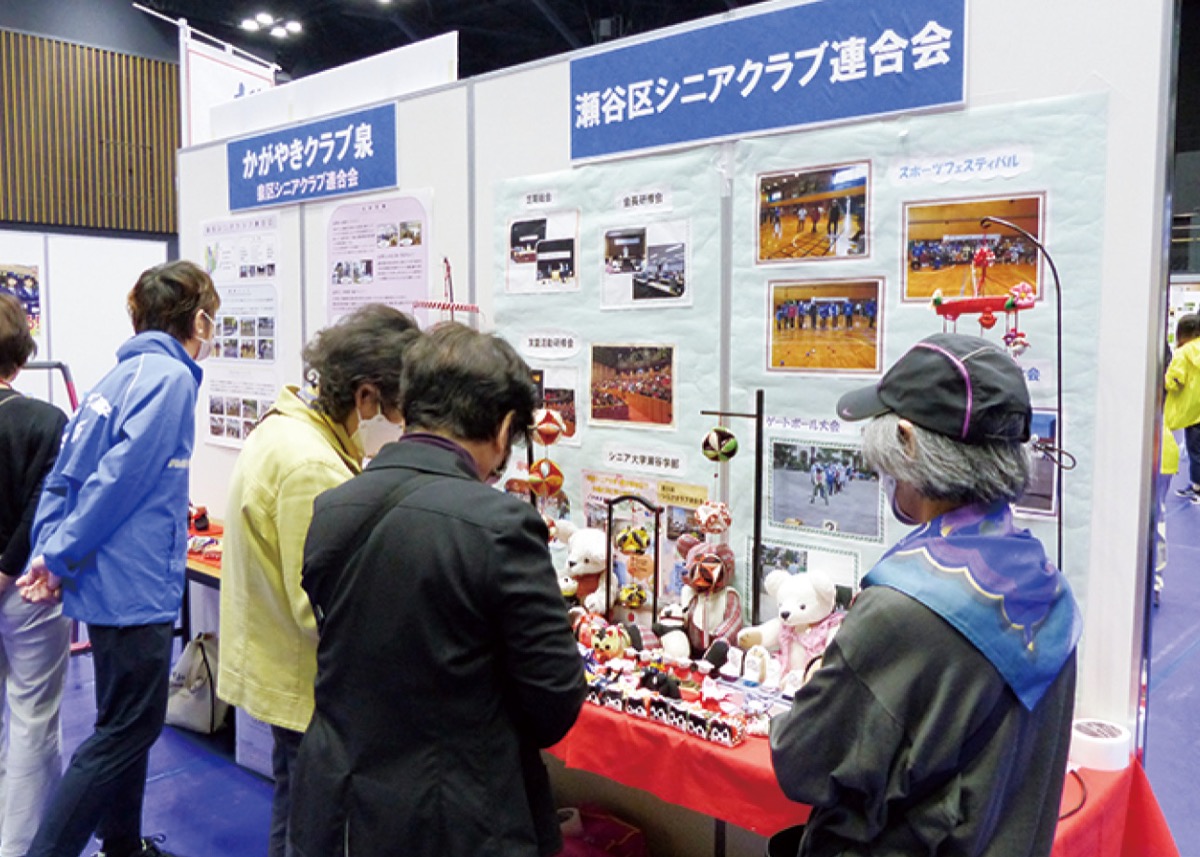横須賀・三浦 コラム
公開日:2025.03.07
OGURIをあるく
〜小栗上野介をめぐる旅〜第37回 横浜編【4】文・写真 藤野浩章
「領土的な野心ではないと言われるか」(第五章)
◇
仏との交渉は大詰めを迎え、ついに江戸城で仏公使ロッシュと幕閣の会見が設定された。
ここに至るまでの経緯は本書に詳しいが、小栗は実に慎重だった。彼は強引に物事を進めたのではなく、フランスに対する心理的、技術的な懸念を一つひとつ検証していった。冒頭のセリフはその最大のもの。「こんな状態の幕府に肩入れするのは日本を植民地にしたいからなのか?」という疑問は、今から160年前には極めて現実的な話だったのだ。
ロッシュは、今てこ入れすれば幕府はまだまだ延命する。その第一歩が造船所である。さらに言えば、日本は金銀が尽きて銅しか残っていないが、豊富な工芸品が魅力であり、最終的には生糸の独占輸入が目的だ、と断言する。しかも「ようやくインドシナ経営の緒(しょ)についたばかりで、とても日本に野心を抱く余裕はない」とまで言い切っている。こうした赤裸々な実情を幕閣の前で言わせた小栗。タフ・ネゴシエーターの本領発揮であったが、結果的に日本が欧米列強の属国になるのを防いだ、とも言えるのではないだろうか。
本書では、最終段階で小栗が幕閣に「まずは、イギリスやロシアに較(くら)べればやや増(ま)し、ぐらいに考えておけばよいのではありませぬかな」と、背中を押すような発言をしているのが面白い。
こうして1864(元治(げんじ)元)年11月10日、幕府はついにフランスの斡旋(あっせん)によって造船所を建設することを正式に決定した。未来の日本を開く歯車が、ようやく動き出した日だった。
ピックアップ
意見広告・議会報告
横須賀・三浦 コラムの新着記事
コラム
求人特集
- LINE・メール版 タウンニュース読者限定
毎月計30名様に
Amazonギフトカード
プレゼント! -

あなたの街の話題のニュースや
お得な情報などを、LINEやメールで
無料でお届けします。
通知で見逃しも防げて便利です!