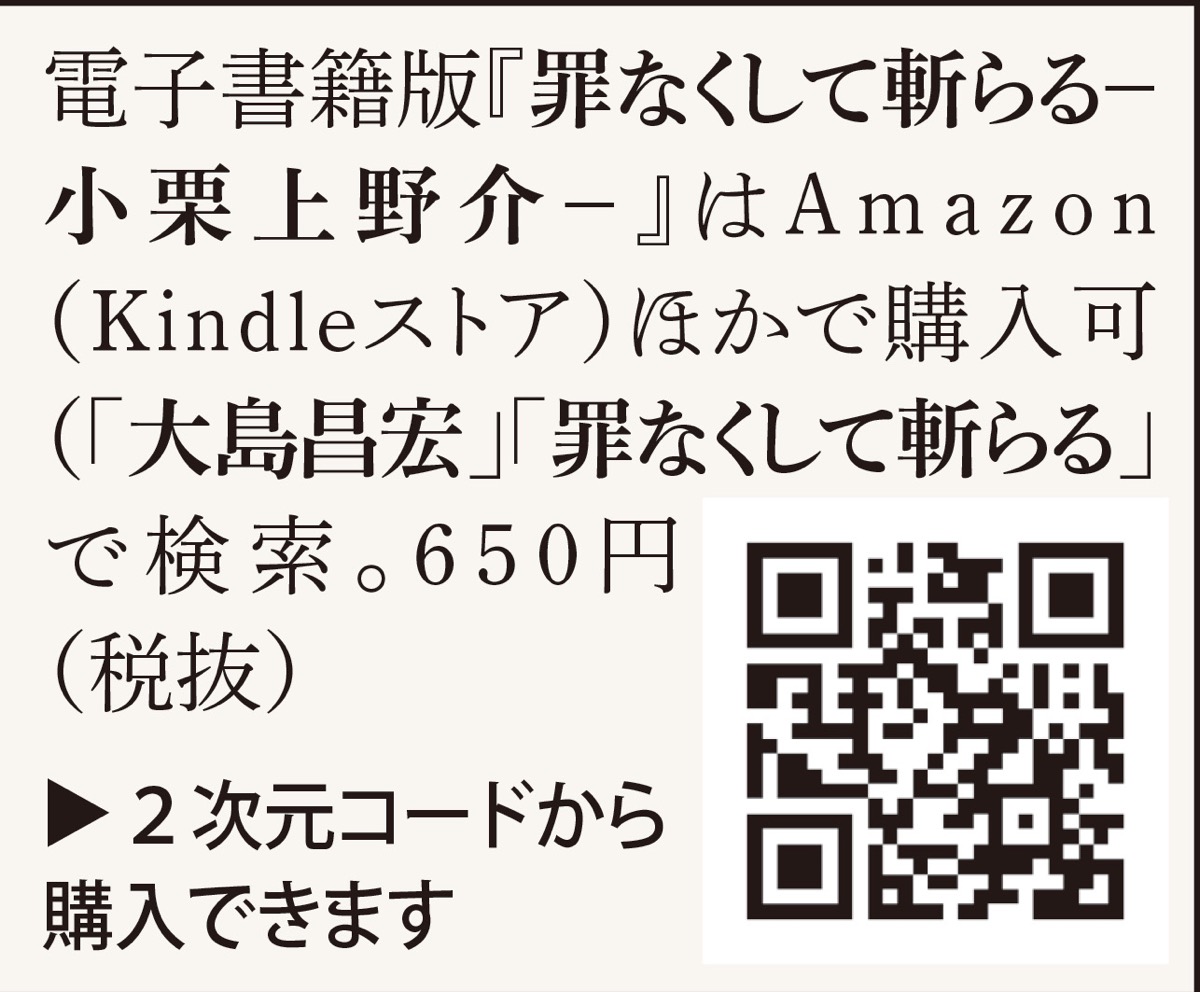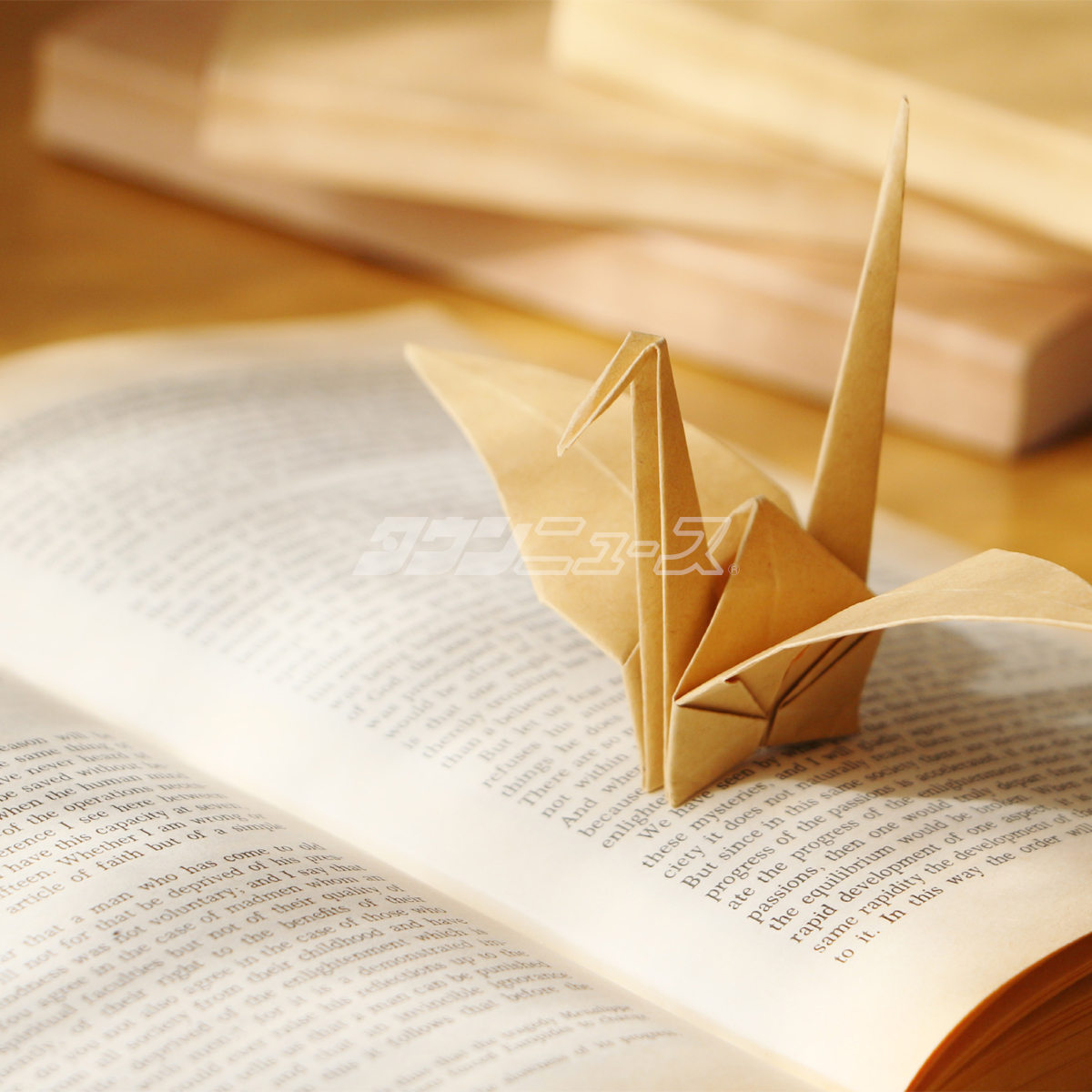横須賀・三浦 コラム
公開日:2025.05.30
OGURIをあるく
〜小栗上野介をめぐる旅〜第48回 キーマン編文・写真 藤野浩章
"最後の幕臣"として活躍した小栗忠順(ただまさ)。彼を語るうえで、特に注目したい人物が2人いる。
1人は、徳川慶喜(よしのぶ)。江戸幕府を最後に舵取りした彼は、良くも悪くも忠順の上司。忠順は最後まで徳川の家臣であり続け、その恩顧はもはやDNAに刻み込まれているとも言えるものだった。
一方、同じ家臣でありながら、組織を超えて日本全体のデザインを考えていたのが勝海舟だ。
幕府がどうにも立ち行かない事は、3人に共通の事だった。しかしその先をどうするか、は大きく異なる。小栗は知識と経験をフル活用して、時に忖度(そんたく)なしに突っ走っても徳川を守ろうとする。一方で勝は、ひょいと組織を乗り越えて日本の形を変えようと走る。
何とか力を合わせて国づくりができなかったのか?とモヤモヤしてしまうが、小栗は勝を「鼻先に人を小馬鹿にしたような敵意をぶら下げている」と評し、勝は勝で「育ちが悪ければ、考えもひねくれてこようというものでの」と意に介さない。実際に幕府内で有名だったという2人のすれ違いは、不幸にも最後まで続いてしまうのだ。
加えて慶喜も、巨大な組織を率いてもがき続けた。時代を動かす主役になった彼らの物語を考える時、この3人それぞれの想いを追っていくと、新たな視点が見えてくるかもしれない。横須賀製鉄所が着工した1865年の時点で小栗38歳、勝42歳、そして慶喜27歳。江戸幕府の後始末は、彼らに託されていた。
◇
さて、本連載の第1部も終盤。次回は開国史研究の第一人者、山本詔?一(しょういち)さんに、小栗の業績と横須賀製鉄所について聞いてみる。
ピックアップ
意見広告・議会報告
横須賀・三浦 コラムの新着記事
コラム
求人特集
- LINE・メール版 タウンニュース読者限定
毎月計30名様に
Amazonギフトカード
プレゼント! -

あなたの街の話題のニュースや
お得な情報などを、LINEやメールで
無料でお届けします。
通知で見逃しも防げて便利です!