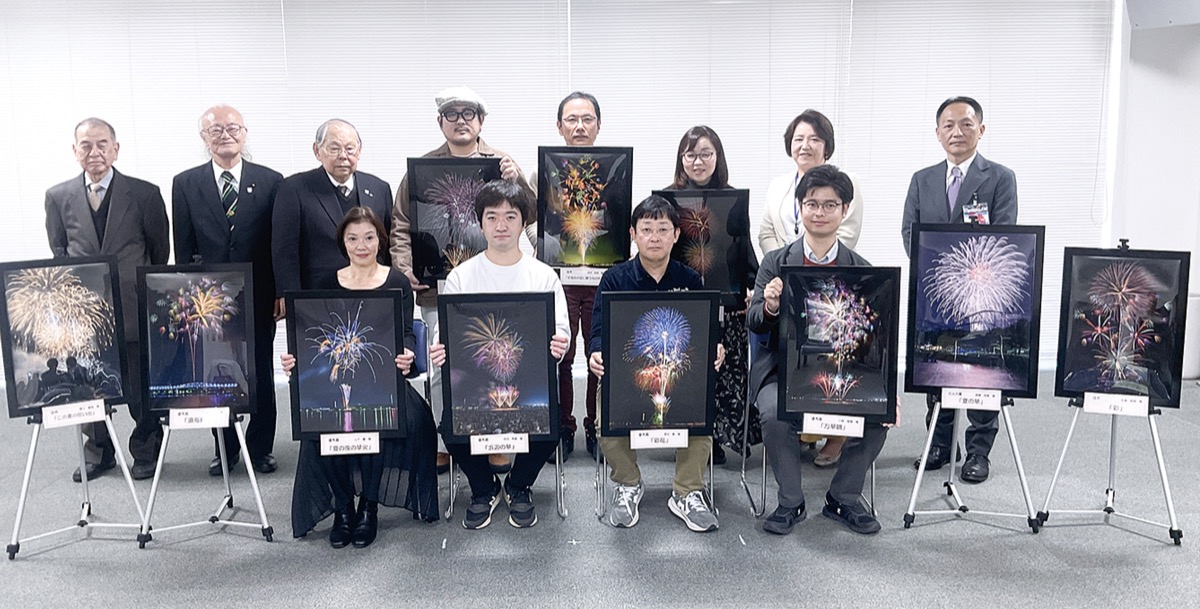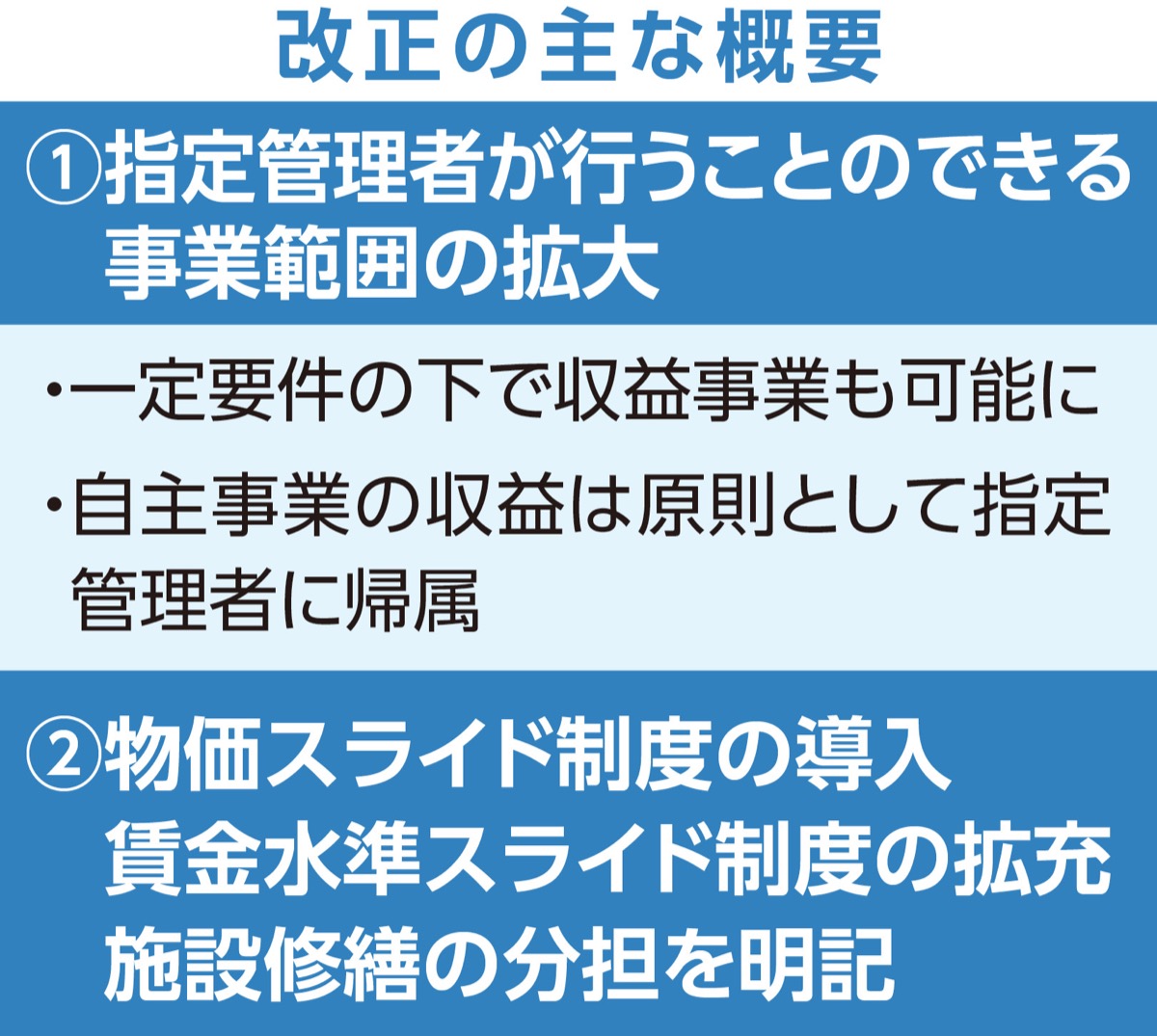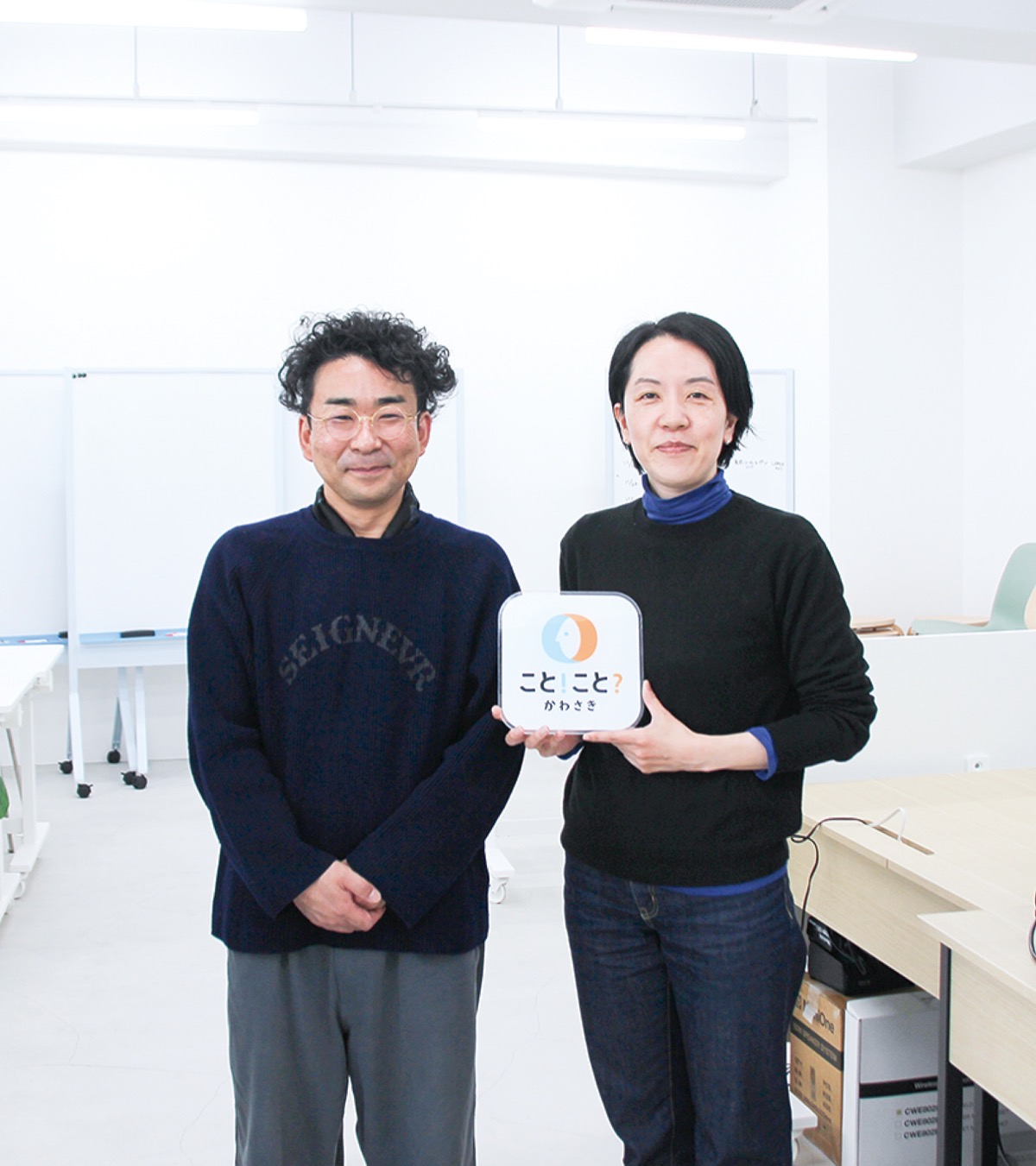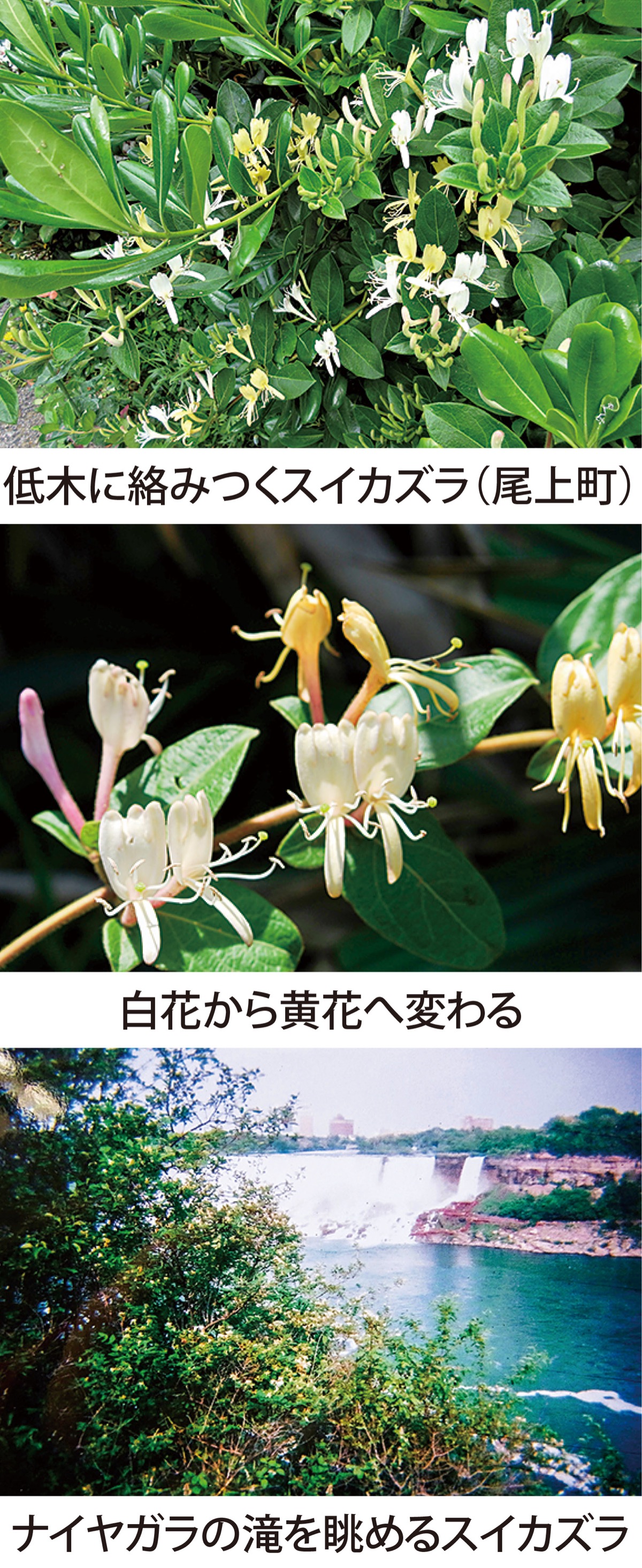三浦 コラム
公開日:2020.11.20
連載 第71回「新編相模風土記稿」
三浦の咄(はなし)いろいろ
みうら観光ボランティアガイド 田中健介
江戸時代の天保十二(1811)年に完成したと言われる『新編相模国風土記稿』のうち、「三崎町」を「美佐木末智(みさきまち)」と記述しています。さらに、「近隣城村及び向ヶ崎・二町谷・東岡・中之町・岡原・宮川の七村は昔此(この)地の属里(ぞくり)なりしが後年各村となりしと云ふ。」とあって、ここに記されている七村を加えれば、現在の「三崎町」と同じ地域となりましょう。
三崎町は江戸時代から漁港として栄え、町の様子を「人家櫛比(じんかじっぴ)」と述べています。人家がくしの歯のようにぎっしりならんでいるさまを、このように述べているのです。他の書物にも「三崎津」や「三崎浦」などと記されていたようです。
さらに、海岸の眺望について東は「房陽(房総)の諸山、西方は小網代や諸磯の海浜から鎌倉、江ノ島が見え、遠くは富峰(富士山)や雨降(大山)箱根の諸岳や真名鶴崎や伊豆の伊東浦が望見できる景色に勝れた地であるとも記されています。
また、「鎌府」(鎌倉幕府)が盛んな頃は「遊覧」の地として、山荘(御所と呼ばれた)を設けられたのでした。
『玉葉集』(八代集の一つ。京極為兼撰、正和元年/1312年撰進)に、源実朝が此の地に遊覧されたときの詠歌が記載されています。
「みさきと云ふ所へまかり侍(はべ)りける道に磯辺の松年(とし)ふりたる(年を経(へ)た)を見て詠(よ)みはべりけるとして、「磯の松幾ひさしにか成(なり)ぬらんいたく木高き風の音かな」(海の水ぎわにある松の木は、どれほどの長い年月を経たのであろうか、高い木の枝先きに風の音が聞こえることだなァ)という意であろうか?
本文では「按ずるに(調べてみると)、右府(三代将軍実朝公)が当所に遊覧されたのは承元四(1210)年・建暦二(1212)年の二回のことで、この時に詩吟されたのであろう。と記されています。
また、源親行(ちかゆき)(鎌倉初期の歌学者)が『関東紀行』に、三崎のことを掲載しています。
「三浦の三崎など云ふ浦々を行って見ば、海上の眺望哀(あわれ)を催(もよお)して、来(こ)しかた(通り過ぎてきた)浦々も沖の釣り舟を眺めながら「玉よする三浦が崎の波まより出たる月の影のさやけさ」と詠(よ)んでいます。
また、『回国雑記』(聖護院門跡准后道興編・室町期の長享元年/1487年)成立。北陸、関東、奥州諸国の遊歴見記で、当時の交通路などが記されていると言う。
それに、「船にのりて三崎といへる所にあがりて、「哀(あわれ)とも誰か三崎の浦伝ひ汐なれ衣(ころも)旅にやつれて」と詠じています。
さらには、応永十(1403)年八月に唐(から)船が三崎港に着岸し、「永楽銭」数百貫が持ち込まれた。との話も載っています。 【完】
ピックアップ
意見広告・議会報告
三浦 コラムの新着記事
コラム
求人特集
外部リンク
- LINE・メール版 タウンニュース読者限定
毎月計30名様に
Amazonギフトカード
プレゼント! -

あなたの街の話題のニュースや
お得な情報などを、LINEやメールで
無料でお届けします。
通知で見逃しも防げて便利です!