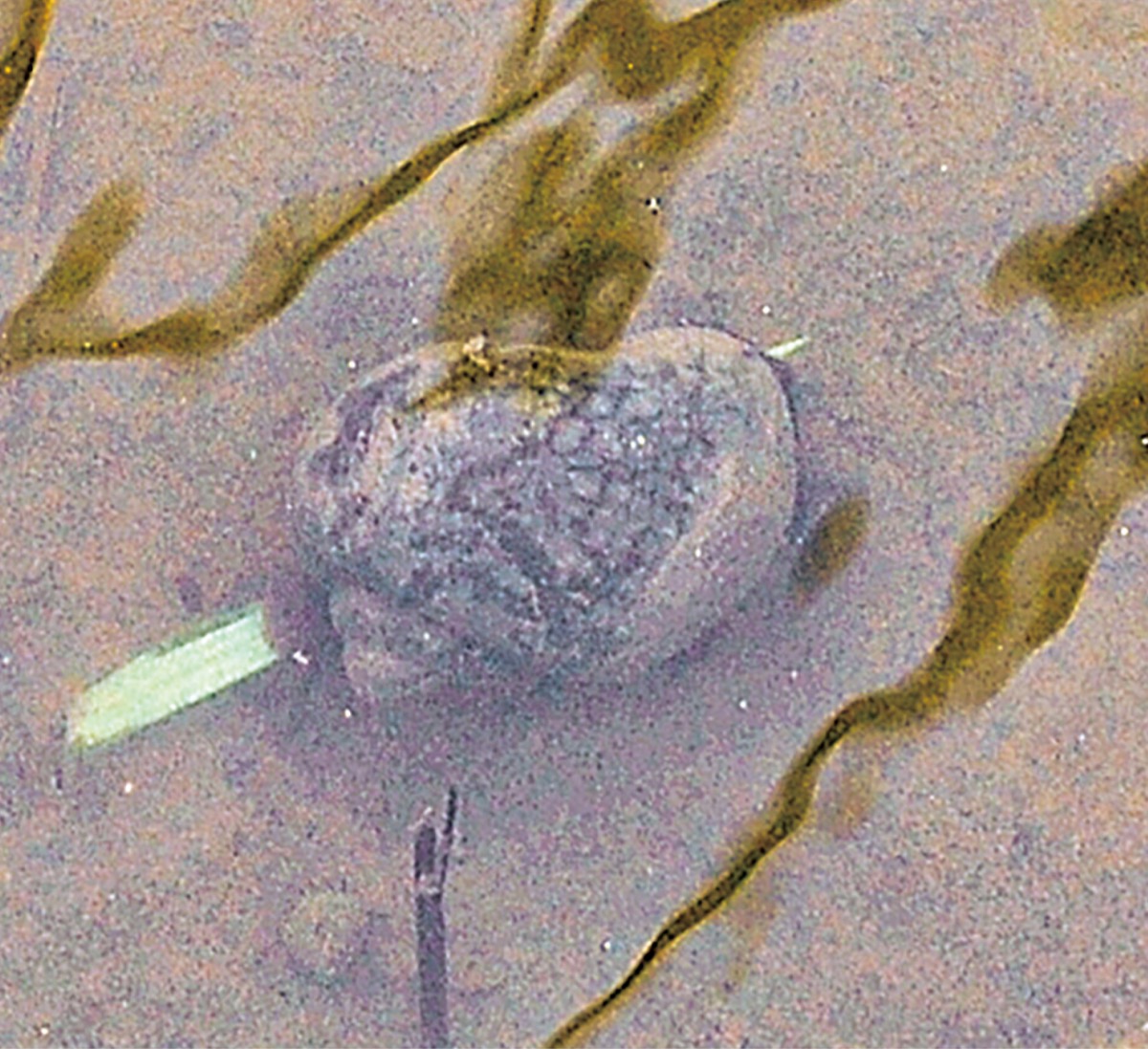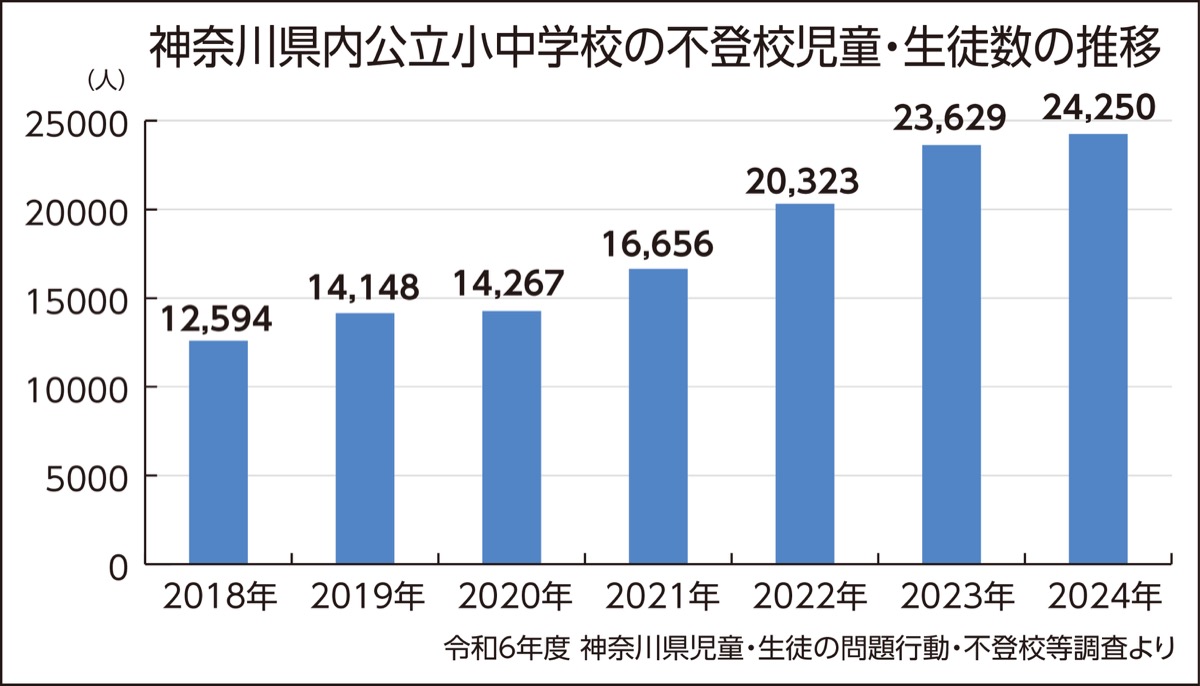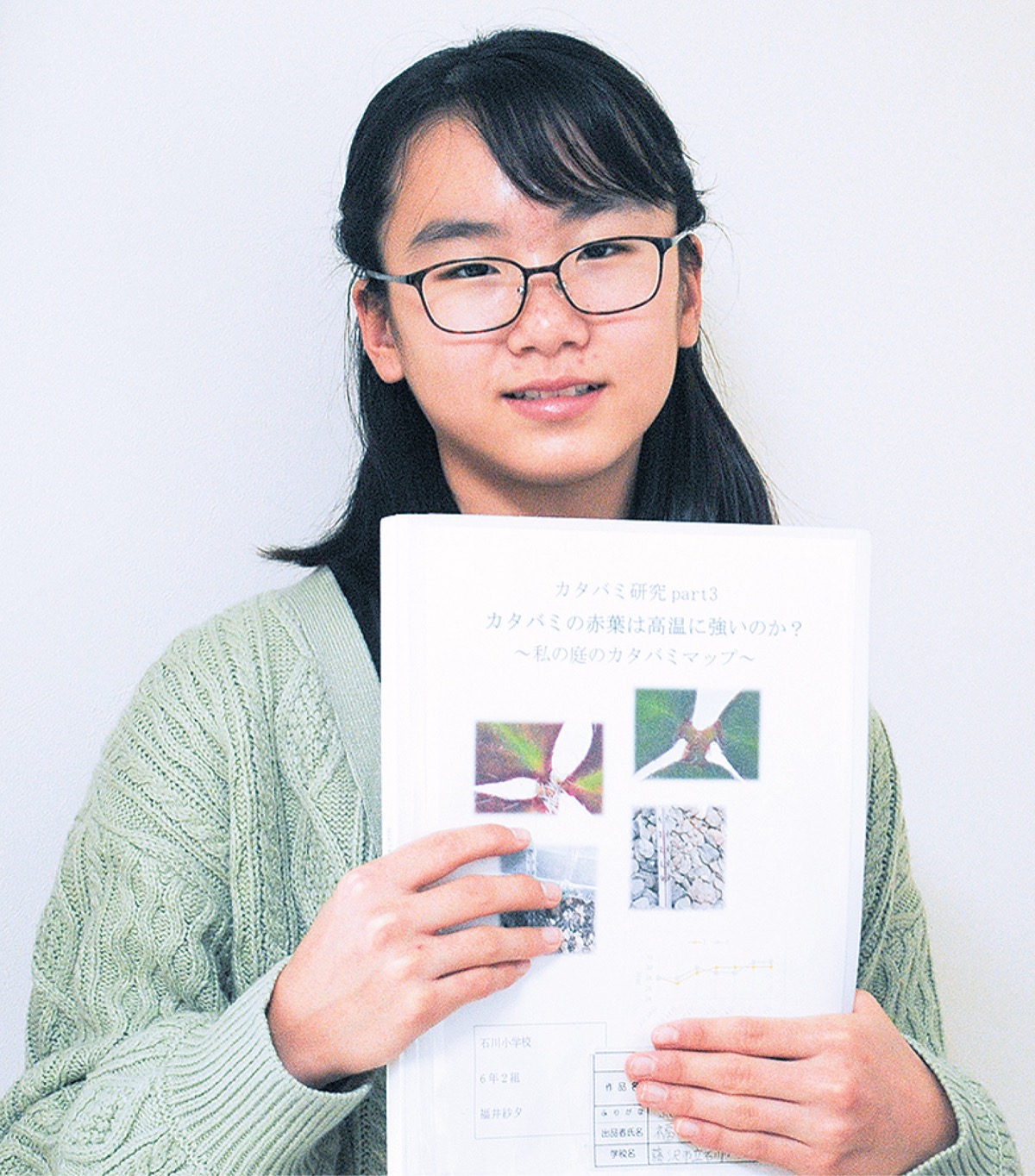藤沢 社会
公開日:2025.06.20
「ジャンボタニシは無用」
稲食う外来種、一斉駆除へ
コメの高値が続く中、水田の稲を食い荒らす淡水巻貝の外来種、スクミリンゴガイ(通称・ジャンボタニシ)による食害が藤沢市内でも確認されている。農家らで組織する城稲荷水利組合も対策に追われており、22日(日)には農家関係者の他、近隣の住民や児童生徒などと協力しながら大庭耕地で一斉駆除を実施する計画だ。
ジャンボタニシは南米原産で、成貝の殻高は5〜8cmにおよぶ。日本へは1981年に食用目的で台湾から購入されたが、その後食用の養殖業は廃れ、野生化したジャンボタニシによる水稲の食害が西日本を中心に広がっていった。
県内では2009年に平塚市で発見され、小田原市、秦野市、伊勢原市など多数の水田地域に繁殖域が拡大。うるち米や酒造好適米などを栽培する大庭耕地では、15年ごろから土中で越冬したとされる個体が現れ、被害が見られるように。19年から近くの小学校などと連携し、共同駆除を開始するに至った。
水田を守れ
水田の一部がぽっかりと穴が開いたように稲がなくなったり、ぽつりぽつりと稲がなったりと、被害の状況はさまざま。水温が上がる田植時期に活性化し、雌貝は3〜4日ごとに200〜300個の卵を産む。卵は10日ほどで孵化し、約2カ月で成熟する。毒を持ち、用水路の壁面などにピンク色の卵がびっしりと付着する光景も見られるため、安全性や景観を守る観点からも迅速な対応が求められる。
故郷の水田と景観を守ろうと、大庭耕地では6年前から地域総出で駆除作業を行ってきた。昨年は50リットルの肥料袋いっぱいに、5袋分のジャンボタニシとその卵を捕獲。おととしの駆除時と比べ、3袋分減ったという。
JAさがみの担当者は「他の自治体では地域ぐるみでの駆除活動により、根絶した例もある」とした上で、「今後も皆一丸となって続けていきたい」と話した。
ピックアップ
意見広告・議会報告
藤沢 ローカルニュースの新着記事
コラム
求人特集
外部リンク
- LINE・メール版 タウンニュース読者限定
毎月計30名様に
Amazonギフトカード
プレゼント! -

あなたの街の話題のニュースや
お得な情報などを、LINEやメールで
無料でお届けします。
通知で見逃しも防げて便利です!