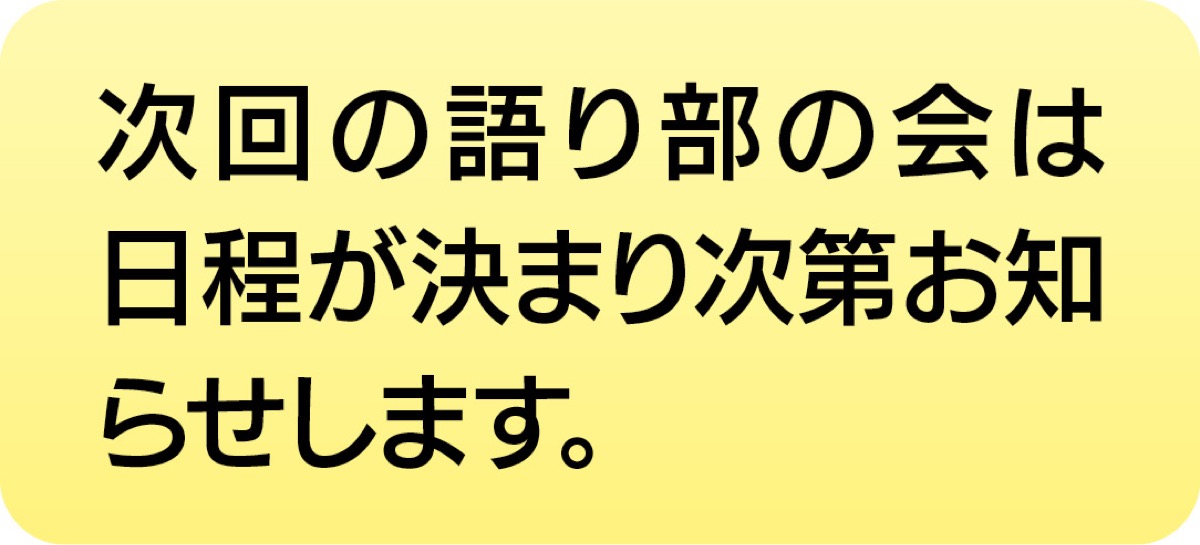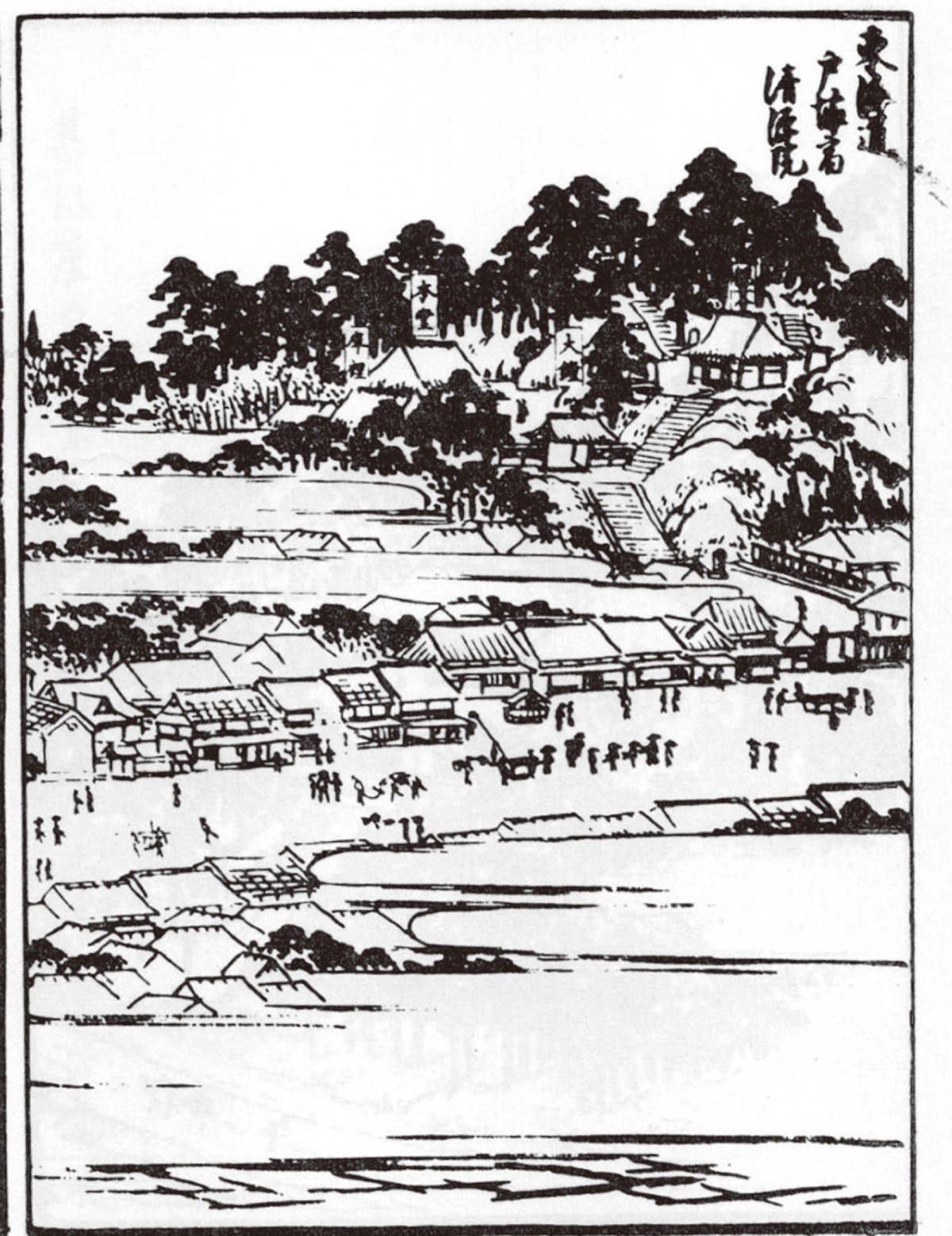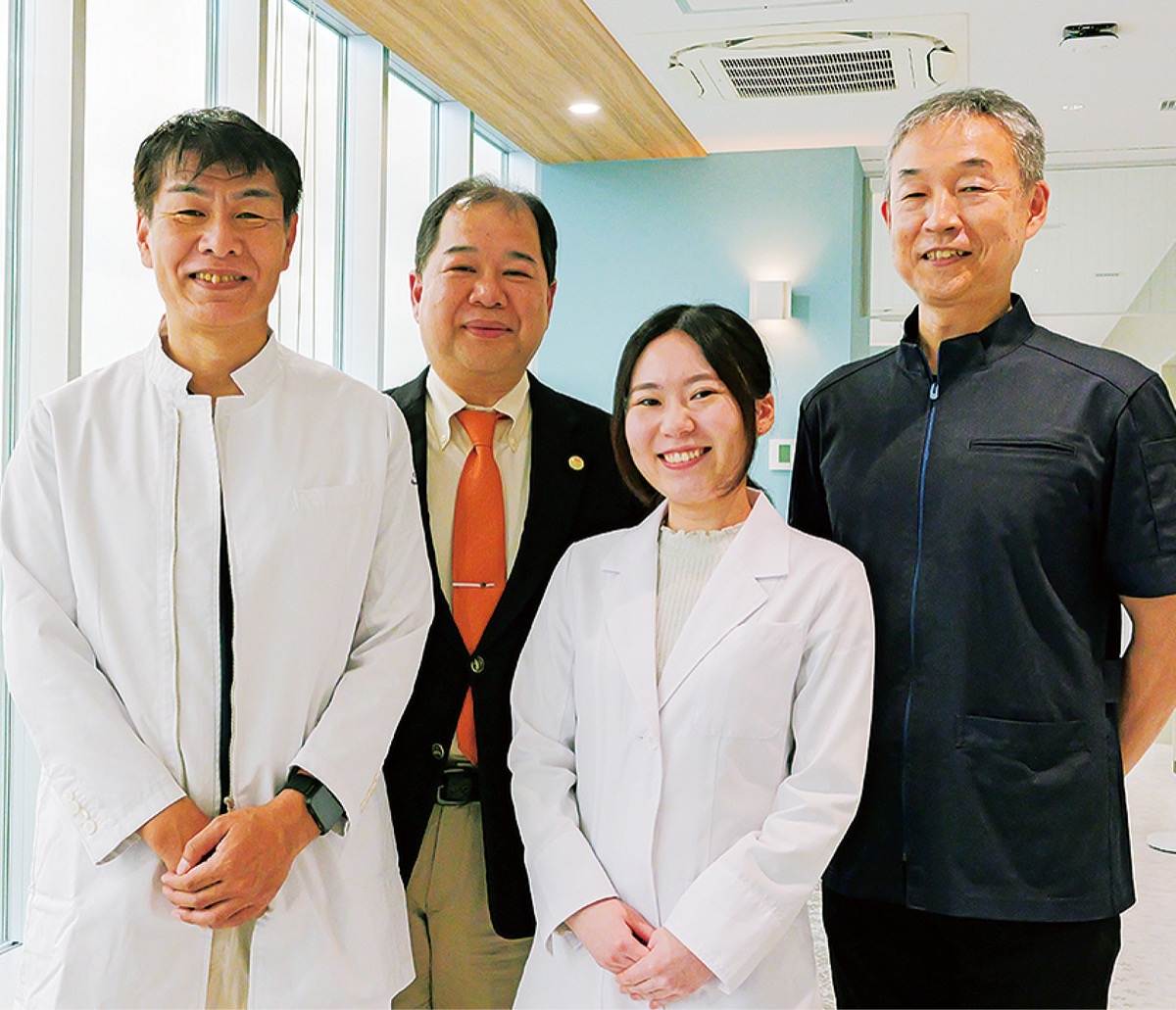大磯・二宮・中井 コラム
公開日:2023.12.22
大磯歴史語り〈財閥編〉
第72回「浅野総一郎㉒」〈敬称略〉 文・武井久江
いよいよ最終号です。良い事・悪い事、勉強をさせてもらいました。総括として、少し前の朝ドラで鶴見の沖縄タウンが描かれてましたがご存知でしたか、あの町になったのも浅野が関係しています。
京浜工業地帯には、JR鶴見線が走っていて、「浅野」「安善」「武蔵白石」「大川」と言った駅名があるが、浅野はもちろん総一郎の事、安善は安田善次郎、武蔵白石は白石源次郎(浅野の次女と結婚、秘書として働いた後、日本鋼管を設立し、現在のJFEホールディングスに繋がっている)で、大川は、大川平三郎(渋沢栄一の書生として働きながら、東京大学で勉学・ドイツ語・英語・歴史などを学び日本で初めて製紙技師になり後に日本の製紙王と呼ばれた人です。浅野を側面から助けるように渋沢から言われ、浅野セメント・現太平洋セメントなど80余りの企業経営に携わり「大川財閥」を作り上げた人です。)
JR鶴見線に乗り、浅野駅で降りて10分程歩くと、仲通り商店街が有ります。そこには、沖縄料理店などが何軒か並んでいます。ここは「リトル沖縄」と呼ばれる地区で、ここがどのように出来たかというと、明治時代後半に砂糖生産業が不振になり、県外に仕事を求める人が急増し、多くの人が横浜港から海外に移住を試みました。実際に移住できたのは、一部の人でした。横浜まで来たが海外に移住できなかった人達がそのまま住み続け、仕事を求めた先が、浅野が鶴見で始めた埋め立て事業でした。
日本でかつてない規模の工事でしたので、人手不足となり沖縄出身者は、労働者となり生活を始めました。知られざる浅野の足跡です。浅野総一郎のお墓は、鶴見の総持寺に有ります。石原裕次郎のお墓も有ります。15万坪の広さで、3千人が座れる大本堂があり、後醍醐天皇霊廟も有ります。その一番奥の一角に600坪の敷地に墓地が有ります。私も御参りさせて頂きましたが、普段は鍵がかかっています。その日はご親族の方がお参りにいらしていて、どうぞとお声を掛けて頂き、お話を聞くことが出来ました。何故この地にお墓があるのですかの問いに、総持寺は曹洞宗の大本山で、石川県の能登に有りましたが、明治31年に火事に見舞われ焼失しました。そこで浅野が土地を寄付し、鶴見に呼び寄せたというのです。浅野がいなければ総持寺は鶴見に引っ越すことは出来ませんでした。
そんな浅野も残念なことに、昭和5年11月9日午前零時52分83歳の生涯でした。「死んだ後まで社会を益すること」この精神を貫いた人でした。
ご冥福をお祈りします。
ピックアップ
意見広告・議会報告
大磯・二宮・中井 コラムの新着記事
コラム
求人特集
大磯・二宮・中井編集室
外部リンク
- LINE・メール版 タウンニュース読者限定
毎月計30名様に
Amazonギフトカード
プレゼント! -

あなたの街の話題のニュースや
お得な情報などを、LINEやメールで
無料でお届けします。
通知で見逃しも防げて便利です!