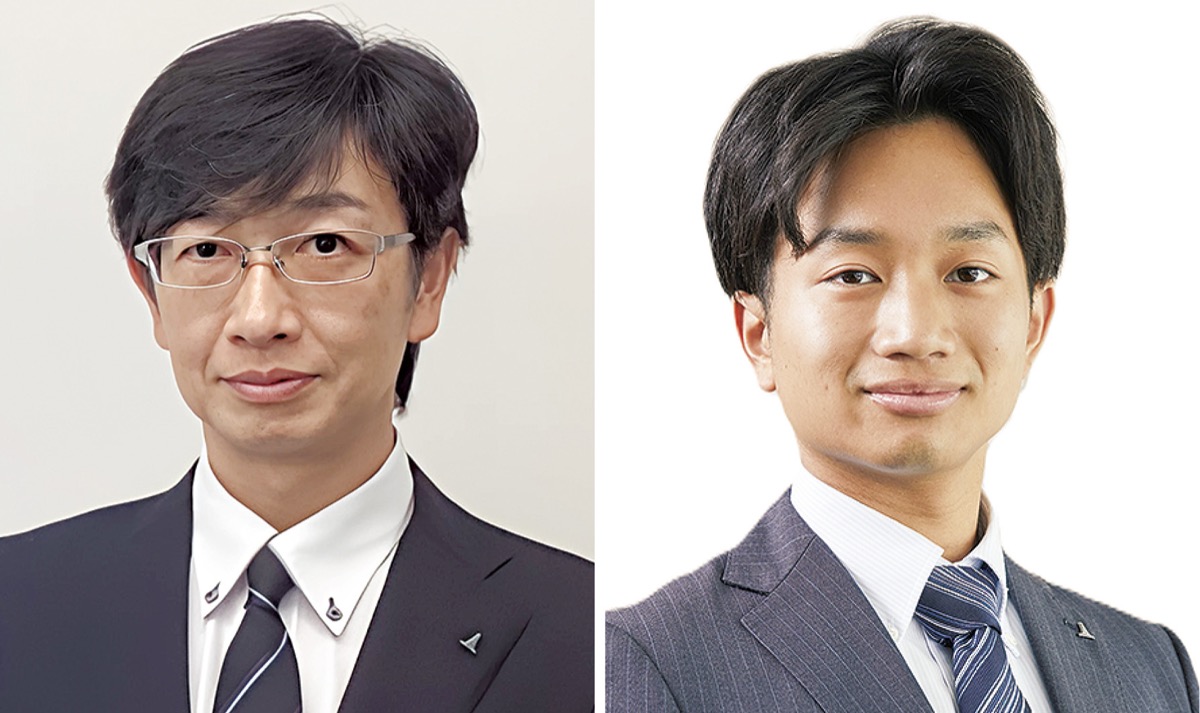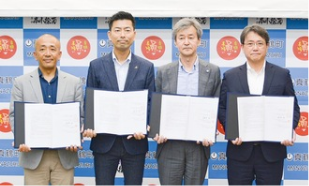鶴見区 コラム
公開日:2025.05.29
「土木事業者・吉田寅松」60 鶴見の歴史よもやま話
鶴見出身・東洋のレセップス!?
文 鶴見歴史の会 齋藤美枝 ※文中敬称略
国産自転車製造へ
明治十年ごろ、外国人が乗っているダルマ型の自転車に興味をそそられた横浜の燈台局で仕上職工として働いていた梶野仁之助が、自転車の研究をして、明治十二年に横浜市蓬莱町に自転車製造販売の店を創業。職人を雇い、木製の前輪駆動の二輪車と三輪車の製造をはじめた。事業を拡大し、タイヤを使用した安全型自動車を製造し、明治十五年ごろには一年に五、六十台の生産体制がととのっていた。
梶野の自転車は、明治二十八年の第四回内国勧業博覧会に出品して受賞し、宮内省や参謀本部に採用され、中国やロシアなどにも輸出するようになり、明治三十年に高島町で大日本自転車製造株式会社を創立した。明治三十五年には、同業者を代表して渡米し、アメリカ自転車発明銀婚式に参列した。
宮田自転車の宮田商店創業者の宮田栄助が自転車づくりを始めたのは、東京京橋で営んでいた鉄砲工場に一人の外国人が故障した自転車を持ち込んで来て、「テッポウヲツクルナラ、ジテンシャ、ナオセマスネ」と、身振り手振りで自転車の修理を依頼されたことがきっかけだった。
見たことも触ったともなかった自転車を何とか息子の政治郎と二人で修理することができた。喜んだ外国人の紹介で、築地居留地の外国人たちから自転車修理の依頼が多くなった。
鉄砲生産も順調だったが、その将来性に不安を感じ、鉄砲造りの金属技術を応用できる自転車製造を試みた。横浜の梶野仁之助の工場で一週間ほど自転車づくりを体験し、分からないことは聞きに行き、助言を受けて完成させた。
梶野と共に博覧会に出品した堅牢で高品質、安全な宮田の自転車は年間五百台以上売れるようになった。明治二十八年に狩猟法が改正され、猟銃の需要も激減したため、銃砲づくりから撤退し自転車製造を主流とするため「宮田製銃所」を「宮田製作所」と改め、今日のMIYATAへ発展の基礎を築いていった。
自転車(一名馬鹿車)
明治二十四年四月十一日日本新聞に「珍しや合乗自転車」「近来府下にも自転車しきりに流行し熟練せし少年はおさおさ外人に劣らぬほどのものあり、したがっておいおいこのもの車もできるならんが、一昨日夕方愛宕下の方角より新橋のほうへ向かいて転輪する自転車をみたり。乗り人は外人の夫婦と覚しく女を前に男は後ろの方に乗り、前はやや低く後ろは少し高く、車形は通常三輪車の大なる者にて、運転は前後一様に調子足を上下する体なり」とある。
明治二十五年七月二十八日の郵便報知には、「馬をやめて自転車 憲兵司令部では乗馬に変えて自転車。春以来練習し、大阪、名古屋、広島、仙台、熊本の各練兵タイへ練習用三台、上等自転車二台、計五台ずつ配布。各隊で練習中」とある。
明治十八年四月十日の日本立憲政党新聞は、京都府下で自転車が大流行し、通行人の妨げになるのみならず怪我をさせることもあり、学校生徒が自転車をもてあそんで学業を怠る者が少なくないので、京都府庁から生徒たちの自転車使用禁止の通達が出されたことを報じている。二十八日の日出新聞に「馬鹿車大津でも流行」「京都で流行していた自転車(一名馬鹿車)がこの頃大津市街に移り、二、三か所も自転車の貸与所ができて、しきりに流行するよしなり」の記事がある。
明治二十年頃まで、自転車の前輪にクランクハンドルとペダルを取り付け、足でクランクをこいで走らせる高価なミショー自転車は、特に用途もなく、新しもの好きの単なる遊び道具のようなもので、「馬鹿車」「阿呆車」と呼ばれ、「自転車に乗る人は悪童、惰少年」とみなされていた。「自転車で大けがをして、釣台に乗せられて帰る人」と、戯作の馬鹿者番付で自転車はは東前頭十五枚目に格付けされている。
ピックアップ
意見広告・議会報告
鶴見区 コラムの新着記事
コラム
求人特集
外部リンク
- LINE・メール版 タウンニュース読者限定
毎月計30名様に
Amazonギフトカード
プレゼント! -

あなたの街の話題のニュースや
お得な情報などを、LINEやメールで
無料でお届けします。
通知で見逃しも防げて便利です!