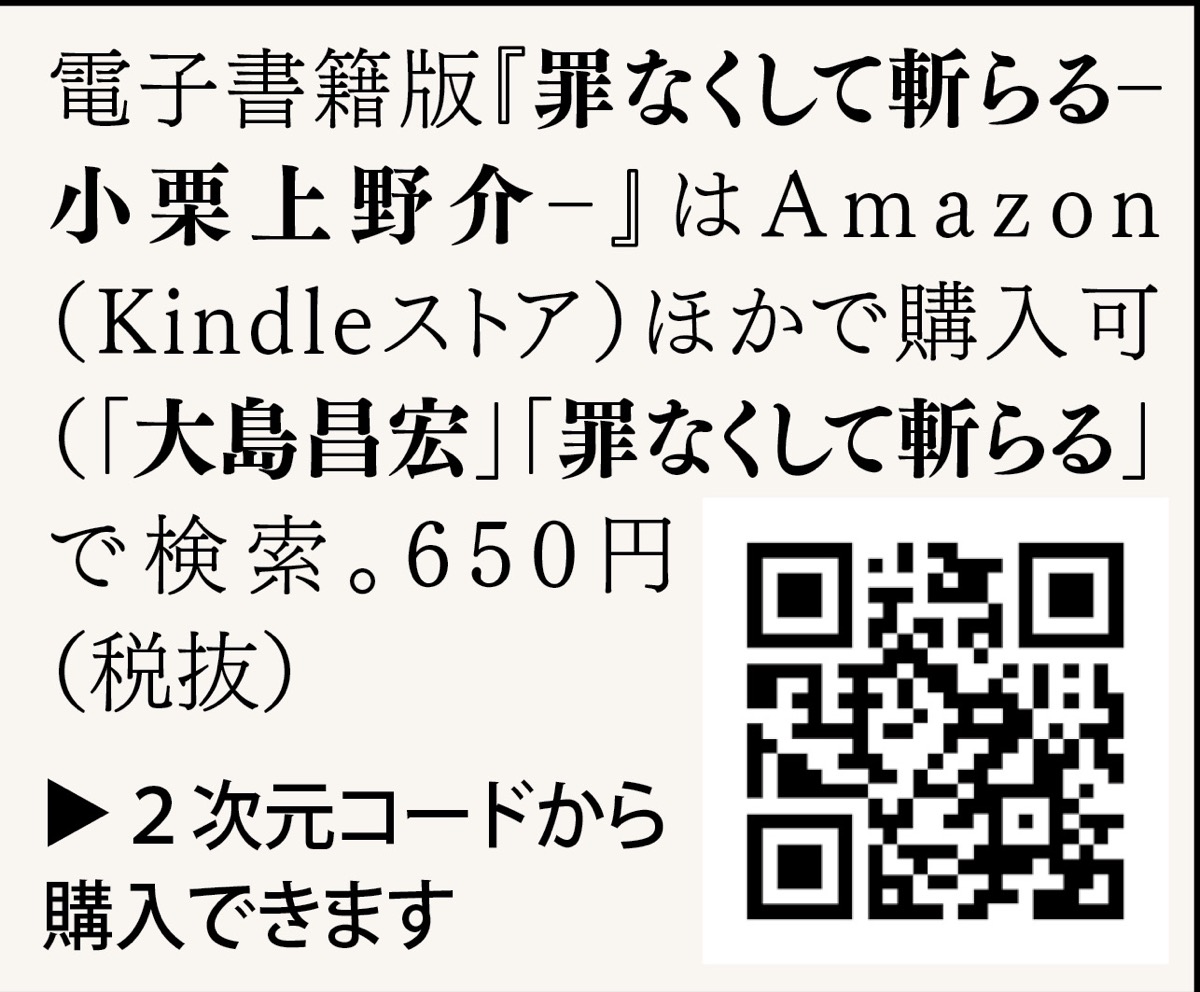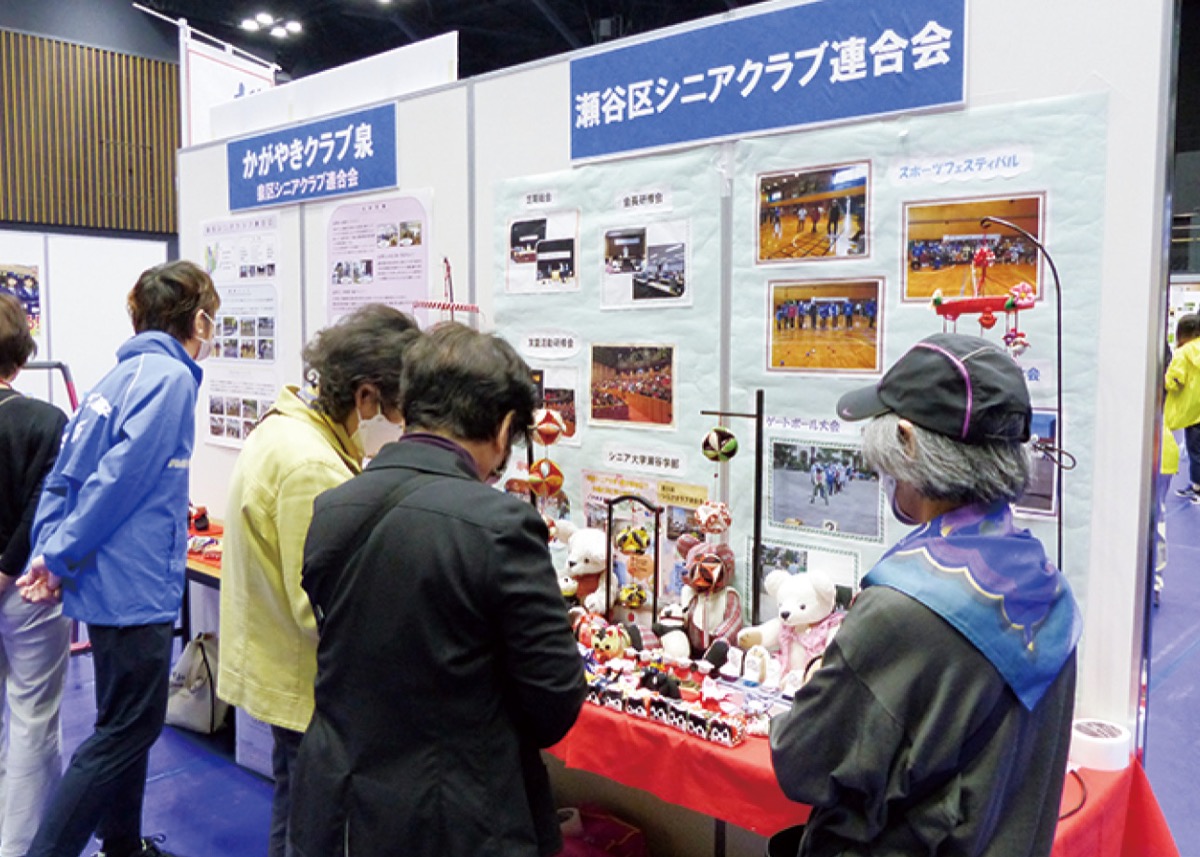横須賀・三浦 コラム
公開日:2025.02.14
OGURIをあるく
〜小栗上野介をめぐる旅〜第34回 横浜編【1】文・写真 藤野浩章
「ではその補強策、次なる手を考えまする」(第四章)
◇
栗本瀬兵衛(せへえ)(鋤雲(じょうん))は小栗の5歳年上で、将軍や大名に仕える医師の家に生まれた。全然違う畑だが、幼い頃2人は昌平黌(しょうへいこう)で出会っている。さらに、以前紹介した儒学者、安積艮斎(あさかごんさい)の私塾・見山(けんざん)楼でも共に学んでいたというから、当時先進的な考え方も備わっていたのだろう。しかも「幕府医官の身で外国の文物に興味を持ったのが上司の忌諱(きい)に触れ、箱館(はこだて)奉行所勤務を命ぜられて六年」という記述が物語っているように、何やら小栗とは似たもの同士という雰囲気。それゆえ「忠順(ただまさ)にとっては心を許せる数少ない友」だった。
さて、箱館に瀬兵衛がいたことは造船所にとって非常に大きかった。当時、メルメ・デ・カションというフランス人に日本語を教え、その代わりに彼から仏語を習っていたのだが、その男は後にフランス公使レオン・ロッシュの通訳官となり、日本へ舞い戻って来た。その縁で、栗本はロッシュとも親しく交際していたのだ。
この奇跡とも言える繋がりに小栗が加わった時は、まさに重大な決断の直前だった。造船所の技術顧問をオランダに打診したところ、幕府の不安定さを懸念し「今後も我が国へ発注する方が早く合理的な策ではないか」という。オランダは、すでに政権の崩壊を確信しているのだ。たとえ現実的な案であっても、小栗には到底受け入れられるものではなかった。
冒頭のセリフは、苦境の際の"切り札"とも言える男の顔を思い浮かべてのものだったはずだ。横浜へ向かった彼を、盟友、栗本が待っていた。
ピックアップ
意見広告・議会報告
横須賀・三浦 コラムの新着記事
コラム
求人特集
- LINE・メール版 タウンニュース読者限定
毎月計30名様に
Amazonギフトカード
プレゼント! -

あなたの街の話題のニュースや
お得な情報などを、LINEやメールで
無料でお届けします。
通知で見逃しも防げて便利です!