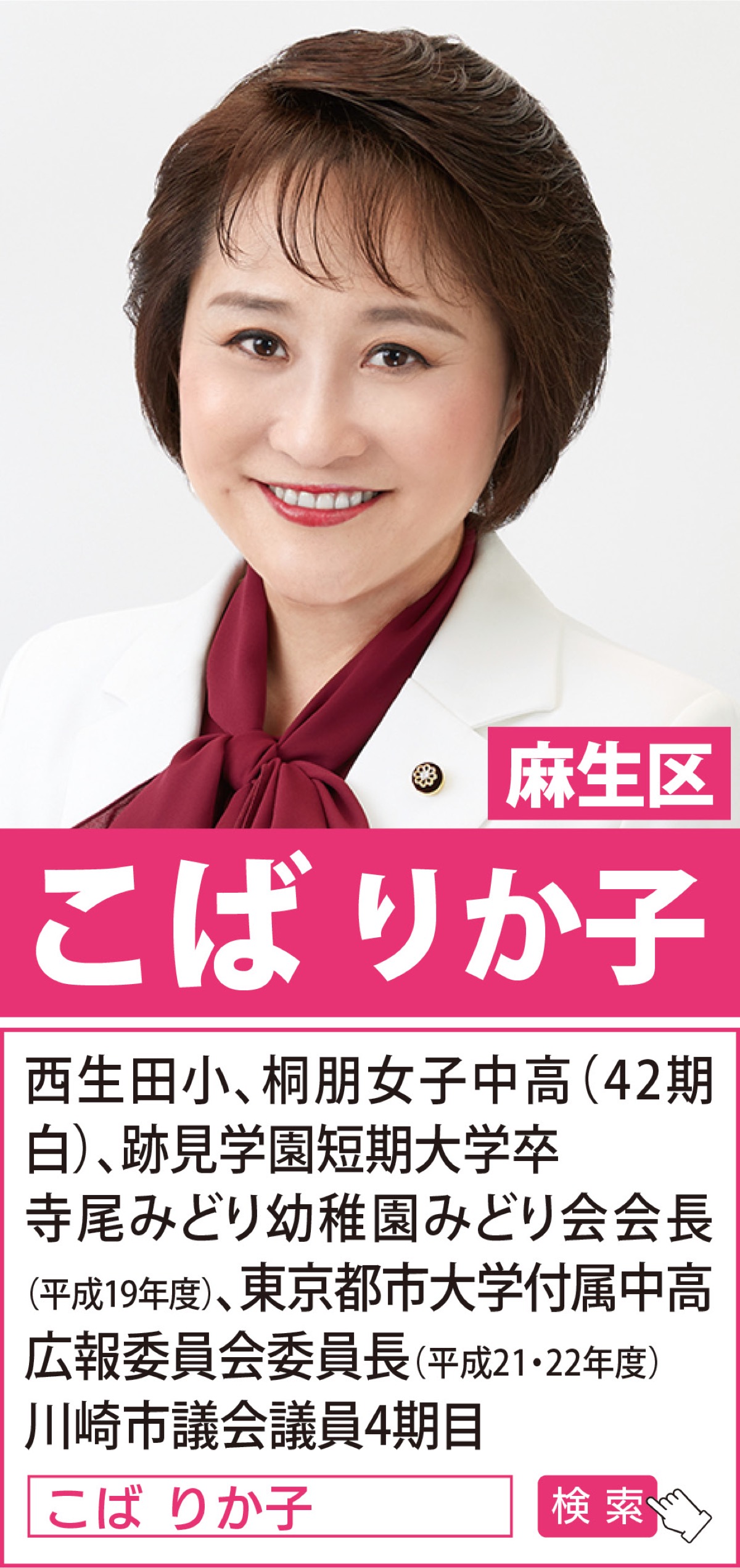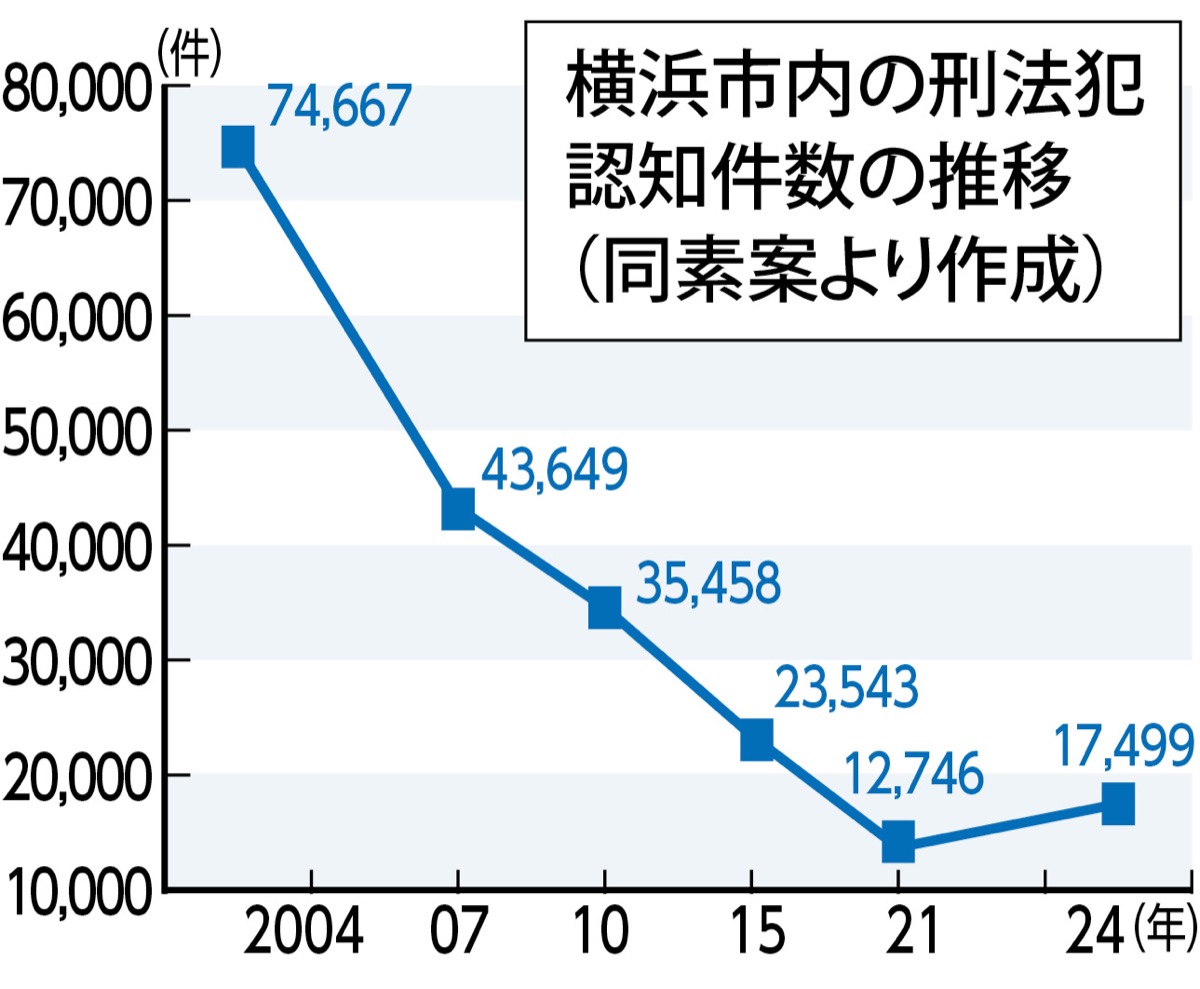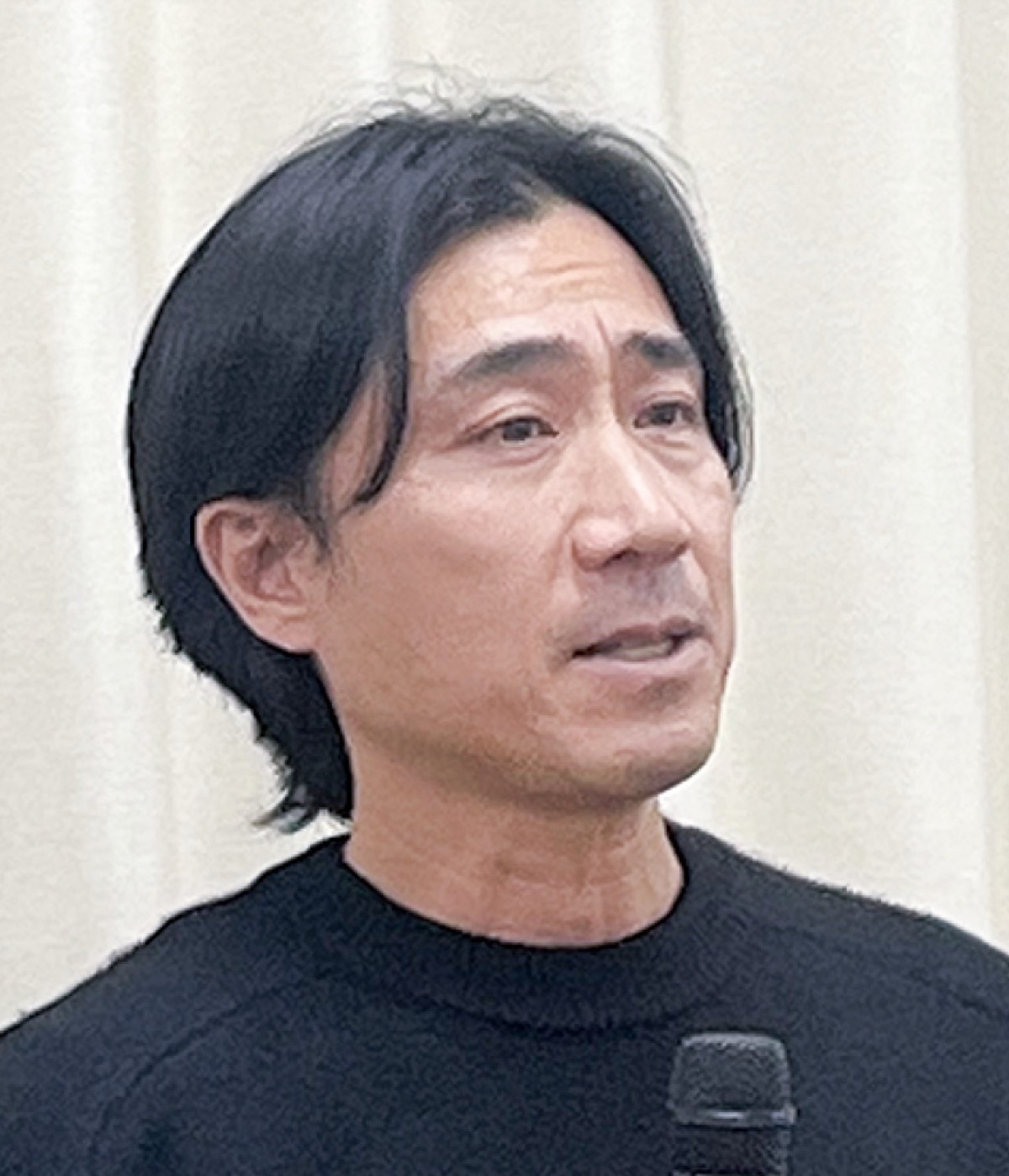多摩区・麻生区 意見広告
公開日:2025.01.10
連載116
地域のやる気を支える保健所指導を!
みらい川崎市議会議員団 こば りか子
コロナ禍を経て、お祭りや地域イベントが未だ復活していない、もしくは廃止されてしまった町会自治会は多く存在します。そのような中、頑張ってお餅つきやお祭りなどを継続、もしくは復活された複数の団体から寄せられるのは「保健所の指導が厳しく、このままでは飲食物を提供するイベントを存続させるのは難しくなる」という声です。そこで、こうしたイベントを実施する際の指導内容について確認したところ「『行事における食品提供の手引き』等を活用し、食品提供場所や取扱い方法、食品を取扱う人の健康管理等について周知を図っている」とのことでした。
多くの餅つき会場で指摘された「屋根付きテントの下で餅をつく方が不衛生ではないか」ということについて質したところ、「あくまでもお願い」であり義務ではないことがわかりました。では、なぜ多くの団体が、様々な「お願い」を「義務」と感じたのでしょうか。
それは保健所の対応に課題があると考え、保健所対応や手引き等の見直しを求めたところ、「営業者向けとは異なった説明をしているものの、情報量が多く目的等が伝わりにくいことが一因と考えるため、既存の手引きを町会自治会向けにシンプルでわかりやすいものに見直し、伝わる広報広聴スキル向上のための研修を実施し改善する」とのことでした。
お餅つき大会やお祭りなど、薪式のかまどで火を起こし、米を炊き、みんなで協力して大型寸胴鍋で具沢山の汁物を提供する様子を拝見するたびに、災害時の炊き出しや、役割分担の訓練に繋がっていると感じています。また、こうした役割を、イベントの際は、普段町会自治会活動に役員として参加していない方も手伝いに参加されており、イベントを通じた顔の見える関係性の構築に貢献していると考えます。さらに、こどもたちにとっても「地域の大人の顔」や自治会館等の場所の周知になることも期待できます。保健所の「地域の方が楽しんでいるイベントで食品による事故が発生しないように」という懸念は当然ですが、厳しくし過ぎて地域の方が、イベント継続を断念しては本末転倒です。イベントを企画する地域の方に伝わりやすいシンプルな手引きの制作と、何より対応する職員の方の接遇スキルの向上に期待したいと思います。
「町内会・自治会活動支援補助金の活用を」
ところで、町内会自治会活動支援の一環として、市では「応援補助金」を交付し、活用事例集を作成するなど、活用を促しているものの、未だ3割の団体に交付実績がないことがわかりました。規模の小さな町会ほど申請がないようです。市では、全ての町内会自治会に事例集を配布するとともに、区役所で随時相談を受付け、また、未活用の団体に対しては電話で申請案内も行っているとのことです。町会自治会活動活性化のため、ぜひ、ご活用ください。
みらい川崎市議会議員団 木庭理香子
-
TEL:044-299-7360
ピックアップ
意見広告・議会報告
多摩区・麻生区 意見広告の新着記事
コラム
求人特集
外部リンク
- LINE・メール版 タウンニュース読者限定
毎月計30名様に
Amazonギフトカード
プレゼント! -

あなたの街の話題のニュースや
お得な情報などを、LINEやメールで
無料でお届けします。
通知で見逃しも防げて便利です!