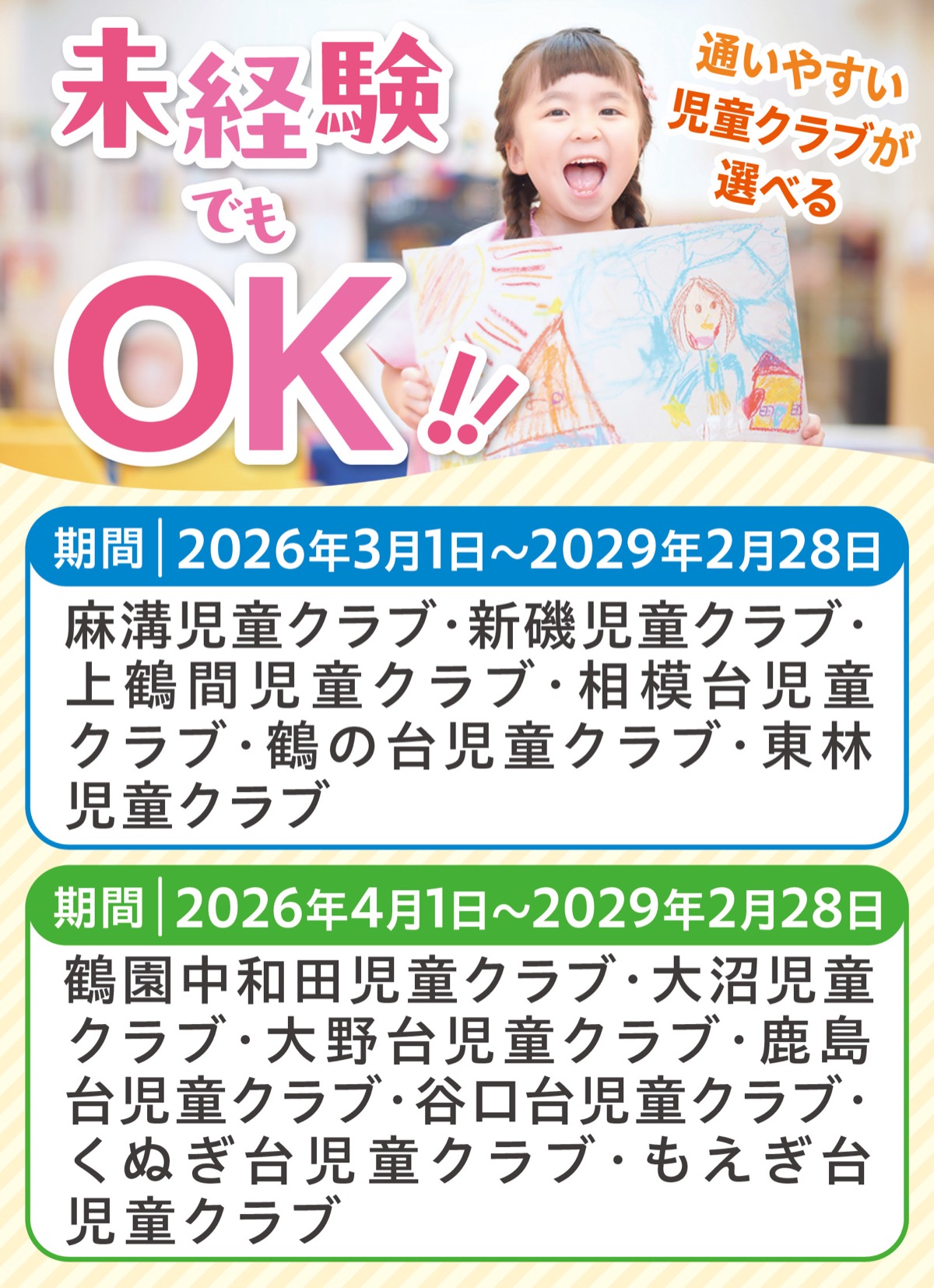町田 コラム
公開日:2025.05.22
町田天満宮 宮司 池田泉
宮司の徒然 其の152
うらしまそう
春うららかな四月、恒例の参拝研修旅行は愛知県の岩津天満宮に正式参拝し、帰りには静岡の井伊谷宮(いいのやぐう)と小国神社(おぐにじんじゃ)に参拝してきた。井伊谷宮の本殿近くにウラシマソウが群生していた。町田近辺の藪でも稀に見ることがあるが、同じテンナンショウ属のムサシアブミやイシヅチテンナンショウ、マムシグサなどに比べると数が少ない。テンナンショウ属は独特な袋状の仏炎苞を持っているが、その形はそれぞれ個性的で、特にウラシマソウは先端から細い蔓状のものを伸ばす。これが浦島太郎の釣り糸のようだからか、全体的に釣竿を持つ浦島太郎の姿に似ているからか、ウラシマソウと名付けられたのだと思う。
亀の背に乗って竜宮城へ招かれた浦島太郎が3年間楽しく過ごし、現実世界へ戻ってみたら長い年月が経過していたというこのお伽話は、時間の流れが違う異次元の世界へ行くというファンタジーの原点ではないだろうか。玉手箱を渡した理由については様々な説があるが、やはり日本の昔話だから、仕事もせずに楽しいことばかりしていると、それなりのしっぺ返しがあるという戒めなのかもしれない。
テンナンショウ属は宿根性で、地下の根が年々太り、春に芽吹くたびに少しずつ大柄になる。若い何年かはずっと雄株で、大きくなると雌株に性転換して、仏炎苞の底に雌しべができるが、外観ではわからない。つまり体力のある大きな株になったら雌株になって、強い種を作るという繁殖の戦略なのだろう。不思議かつ地道だ。シルエットは浦島太郎に似ているのかもしれないが、変わりゆく地球環境の下、決して気を緩めて遊ぶことなく、じっくり確実にウラシマソウは生きている。
ピックアップ
意見広告・議会報告
町田 コラムの新着記事
コラム
求人特集
- LINE・メール版 タウンニュース読者限定
毎月計30名様に
Amazonギフトカード
プレゼント! -

あなたの街の話題のニュースや
お得な情報などを、LINEやメールで
無料でお届けします。
通知で見逃しも防げて便利です!