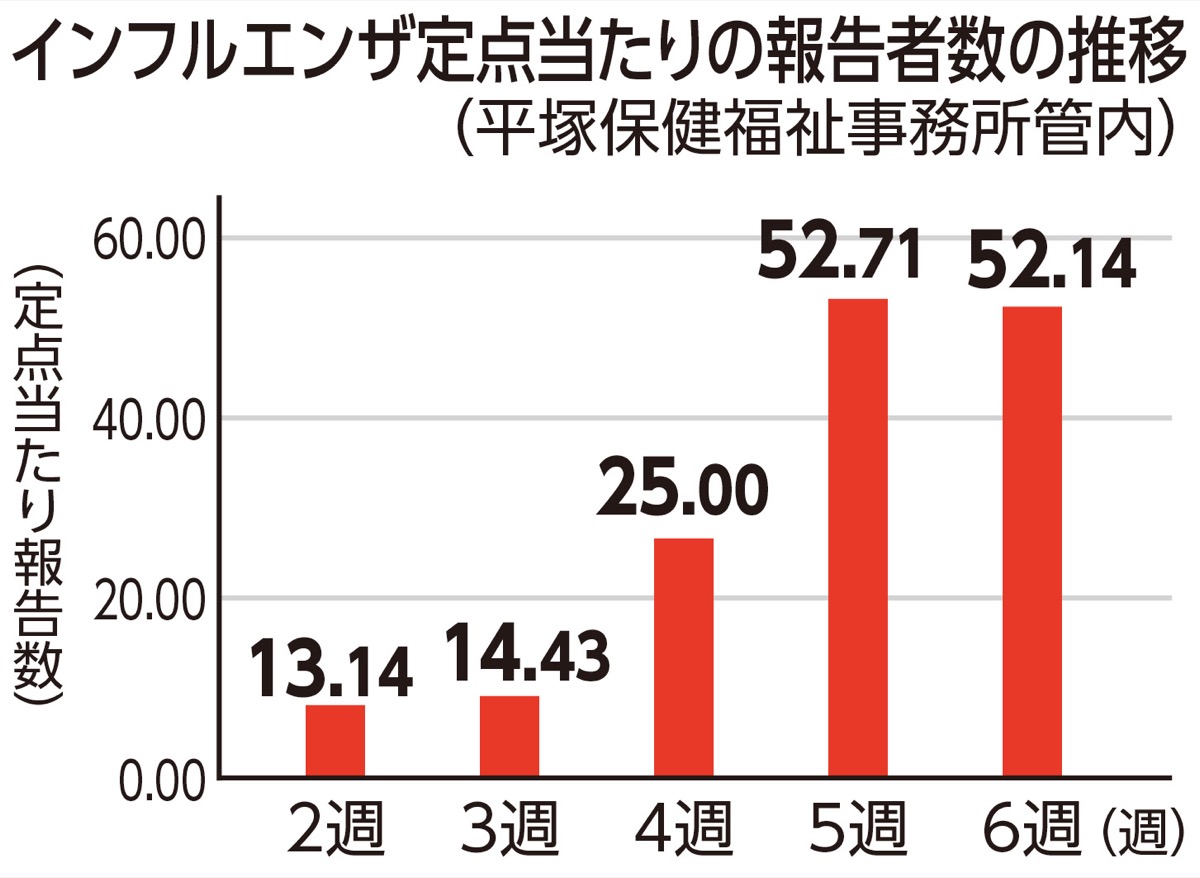横須賀・三浦 コラム
公開日:2024.04.26
"海の隼"をあるく
〜按針が見たニッポン〜最終回 逸見編作・藤野浩章
「三浦按針」とは何だったのか──。その核心を追う本書の旅の最後は、幕末だった。彼の死後230年余りが経過し、浦賀にペリーが来航した後のことだ。
開国するかどうか腐心する老中(ろうじゅう)・阿部正弘を登場させ、三浦浄心(じょうしん)の『慶長見聞(けんもん)録』を読んで按針にたどり着く。その功績を読んだ彼は「按針のように、すぐれた水先案内人を持っていたことが羨(うらや)ましくてならぬ」と本音を漏らす。そして「ここはやはり、権現(ごんげん)さまの昔に立ち戻るしかあるまい」と決意するのだ。作者の大島は、あとがきで「開国に踏み切ったのも本卦(ほんけ)帰りしたにすぎないのでは」と感想を記している。
按針亡き後、鎖国令の厳密化で平戸の妻・たき(・・)と娘のハルは国外追放になったという。一方、逸見のゆき(・・)は夫の死から14年後に亡くなっている。そして息子のジョセフ(千松)は"二代目三浦按針"を名乗り朱印船貿易に携わっていたというが、娘のはる(・・)と同じく、その後は不明だ。
按針は、紛れもなく日本史上特異な英雄だった。家康と按針が見た夢は、幕末に思わぬ形で実現し、現代の基礎になったと言っても過言ではないだろう。
でもその裏には、一人の人間としての喜びや達成感、そこに至る苦しみや悩みが確実に存在したはずだ。それを思うとき、歴史を追い、挑戦していく「物語」のチカラを改めて思うのだ。
さて、幕末の開国で按針から"歴史の先駆者"という思わぬバトンを受け取ったのは小栗(おぐり)上野介(こうずけのすけ)かもしれない。次は『罪無くして斬(き)らる』を元に、小栗の旅に出かけることにしよう。
ピックアップ
意見広告・議会報告
横須賀・三浦 コラムの新着記事
コラム
求人特集
- LINE・メール版 タウンニュース読者限定
毎月計30名様に
Amazonギフトカード
プレゼント! -

あなたの街の話題のニュースや
お得な情報などを、LINEやメールで
無料でお届けします。
通知で見逃しも防げて便利です!