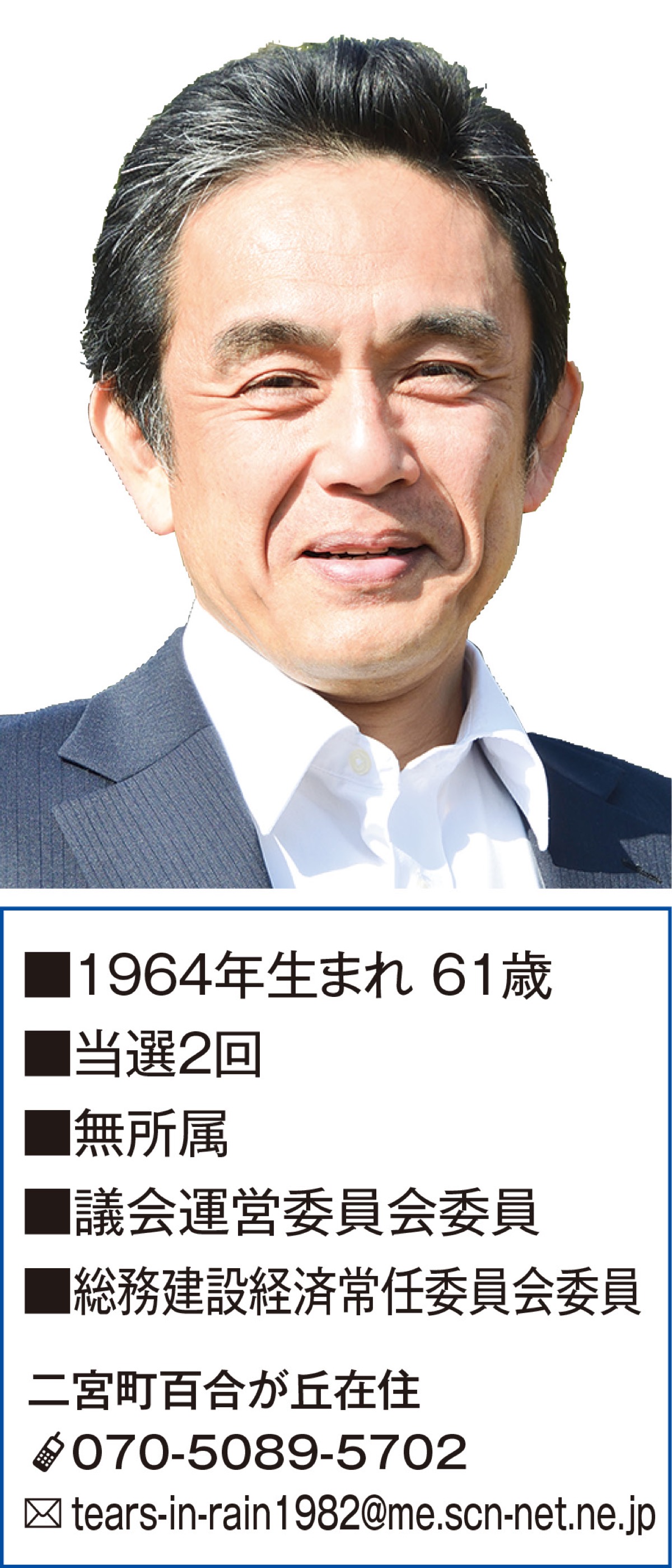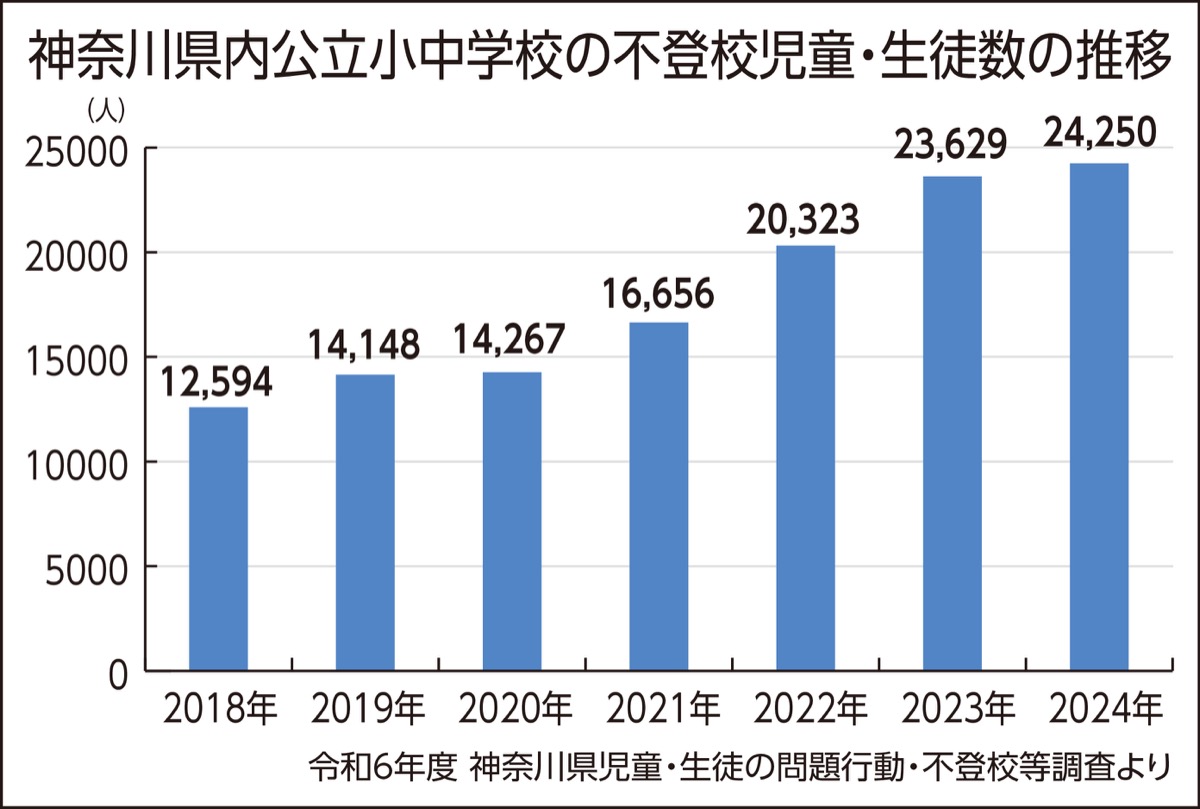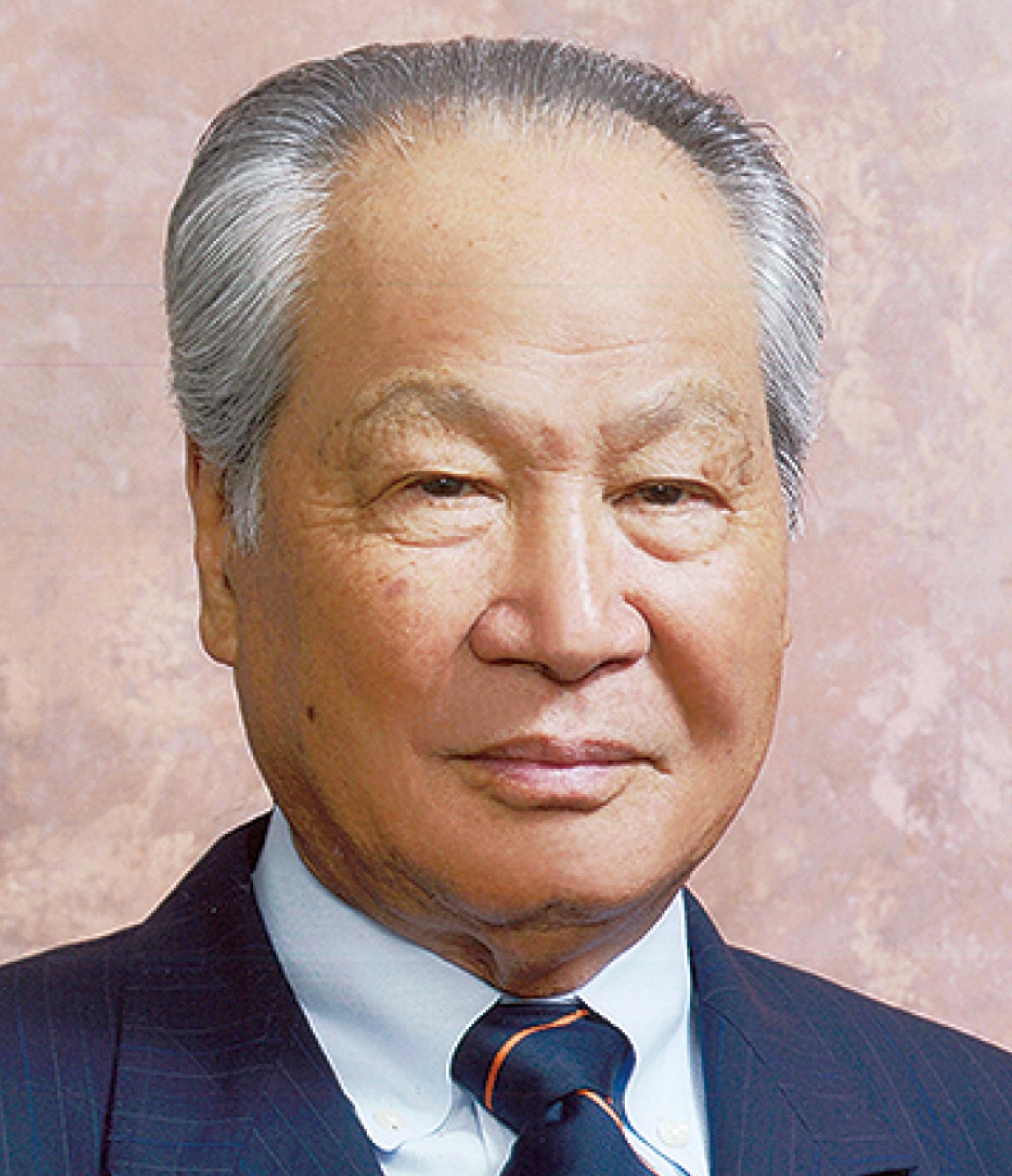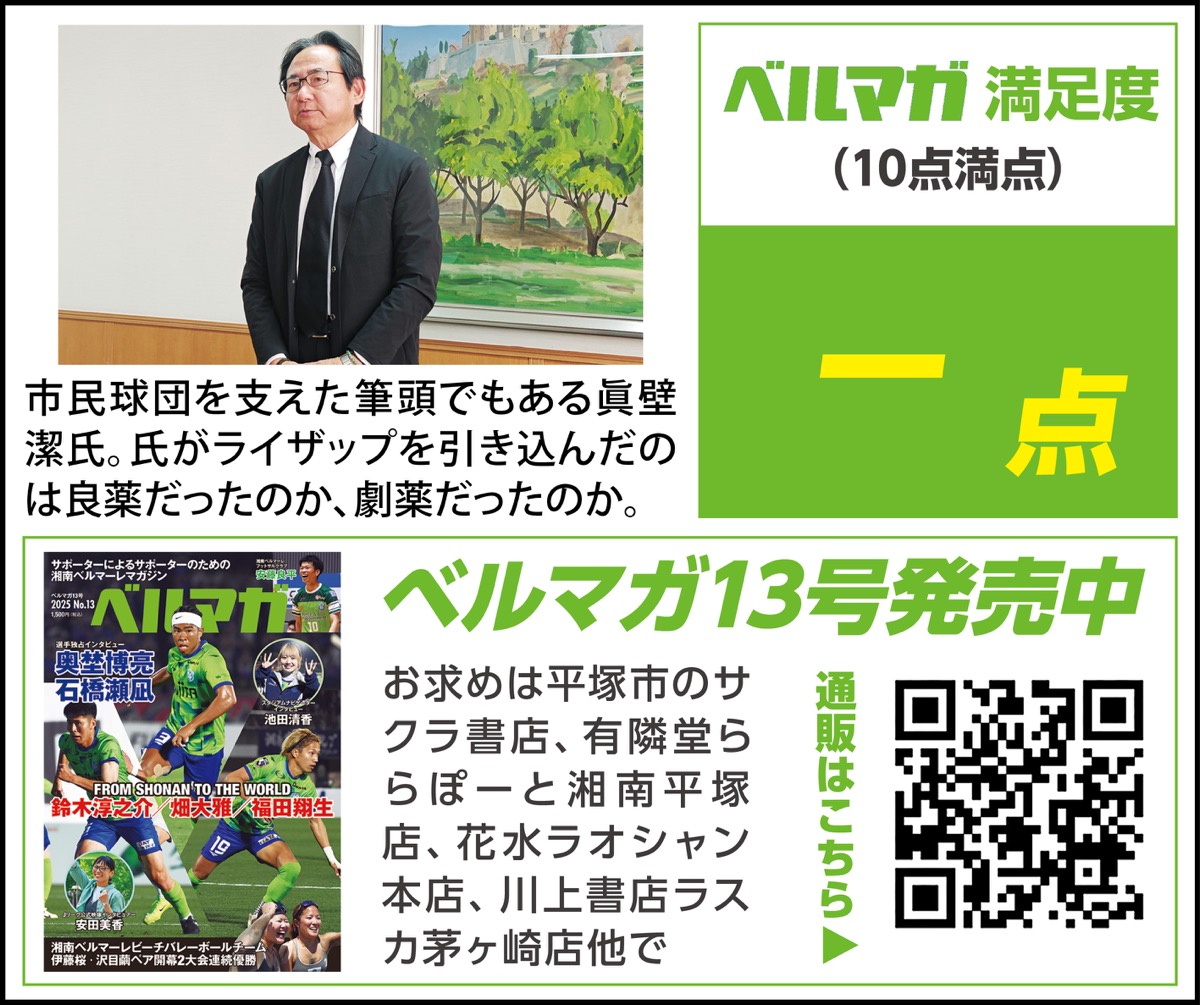平塚・大磯・二宮・中井 トップニュース文化
公開日:2025.03.21
日本三大俳諧道場鴫立庵
西行祭で遺徳偲ぶ
大磯に文化根付かせ
大磯の鴫立沢の地名の由来にもなった平安末期の歌人・西行法師の遺徳を偲び、俳諧振興を目的とした第68回大磯西行祭が3月30日(日)、鴫立庵(大磯1289)で開催される。投句された俳句の入選作披講などを行うもので、日本の俳諧文化を今に伝えている。
「心なき身にも哀(あわれ)はしられけり鴫立沢の秋の夕暮」という句は、西行が平安時代に大磯あたりの海岸を吟遊して詠んだと伝えられている。この句をゆかりとして、江戸時代には鴫立沢という地名が町民にも浸透していたということが文献にも残っているという。
「鴫立庵」の始まりは1660年頃の江戸時代。小田原の外郎一族とされる崇雪が、鴫立沢の近くに閑居の地として建設した。俳諧道場として利用され始めたのは庵が整備されてから30年ほど経った頃だ。俳人・大淀三千風が第一世庵主となって以来、日本三大俳諧道場として現代に続いている。江戸時代後期には俳諧が農民にも浸透する娯楽となっていたことから、人々が集い教えを乞う「道場」として活用されたという。
明治時代以降、俳諧文化は雑誌や新聞などの普及により従来の「集まって楽しむもの」から、投句するものへと変化していた。そうした社会の変化も踏まえ、今一度、同庵を地域の文化施設として盛り上げようと発起したのが初の女性庵主・鈴木芳如氏(第十八世)だ。1961年には西行祭もスタートさせ、戦後の鴫立庵の礎を作った。
大磯町郷土資料館の学芸員の富田三紗子さんは、大磯小学校のPTA広報誌『いそかぜ』に俳句の投句コーナーがあることや、鴫立庵庵主による選句が行われることなどから、「鴫立庵という場所としてだけでなく、俳句を楽しむ文化が大磯町民に根付いていると感じる」と話していた。
西行祭は午前10時半〜。投句はすでに締め切られている。同日、町保健センターでは俳句大会(席題発表10時)、短歌大会も開催。(問)同庵【電話】0463・61・6926
ピックアップ
意見広告・議会報告
平塚・大磯・二宮・中井 トップニュースの新着記事
コラム
求人特集
- LINE・メール版 タウンニュース読者限定
毎月計30名様に
Amazonギフトカード
プレゼント! -

あなたの街の話題のニュースや
お得な情報などを、LINEやメールで
無料でお届けします。
通知で見逃しも防げて便利です!