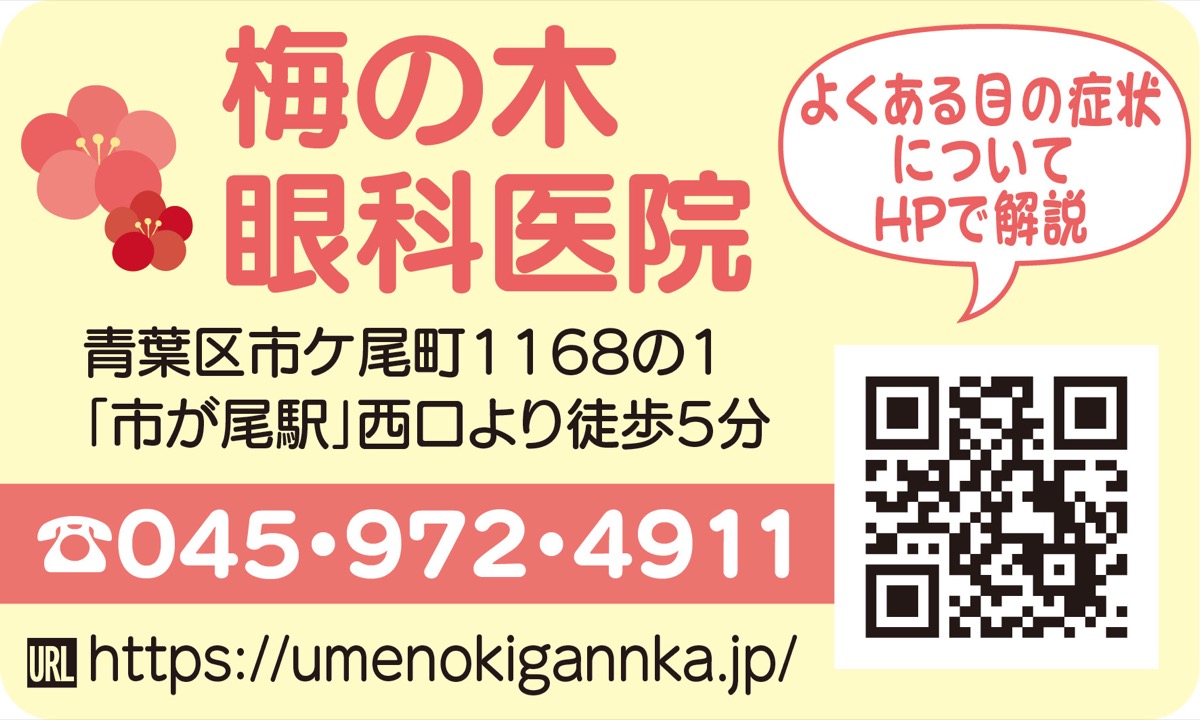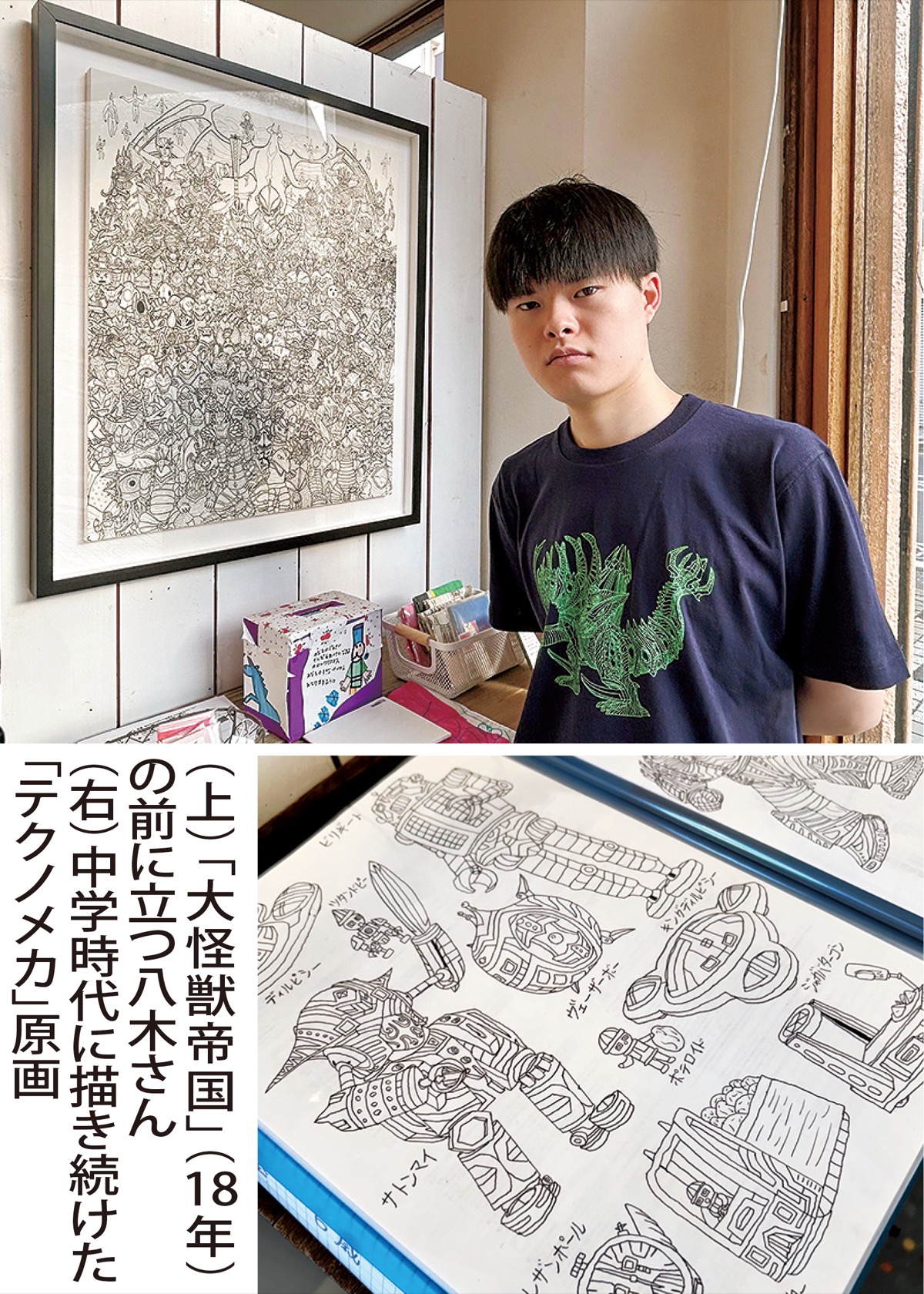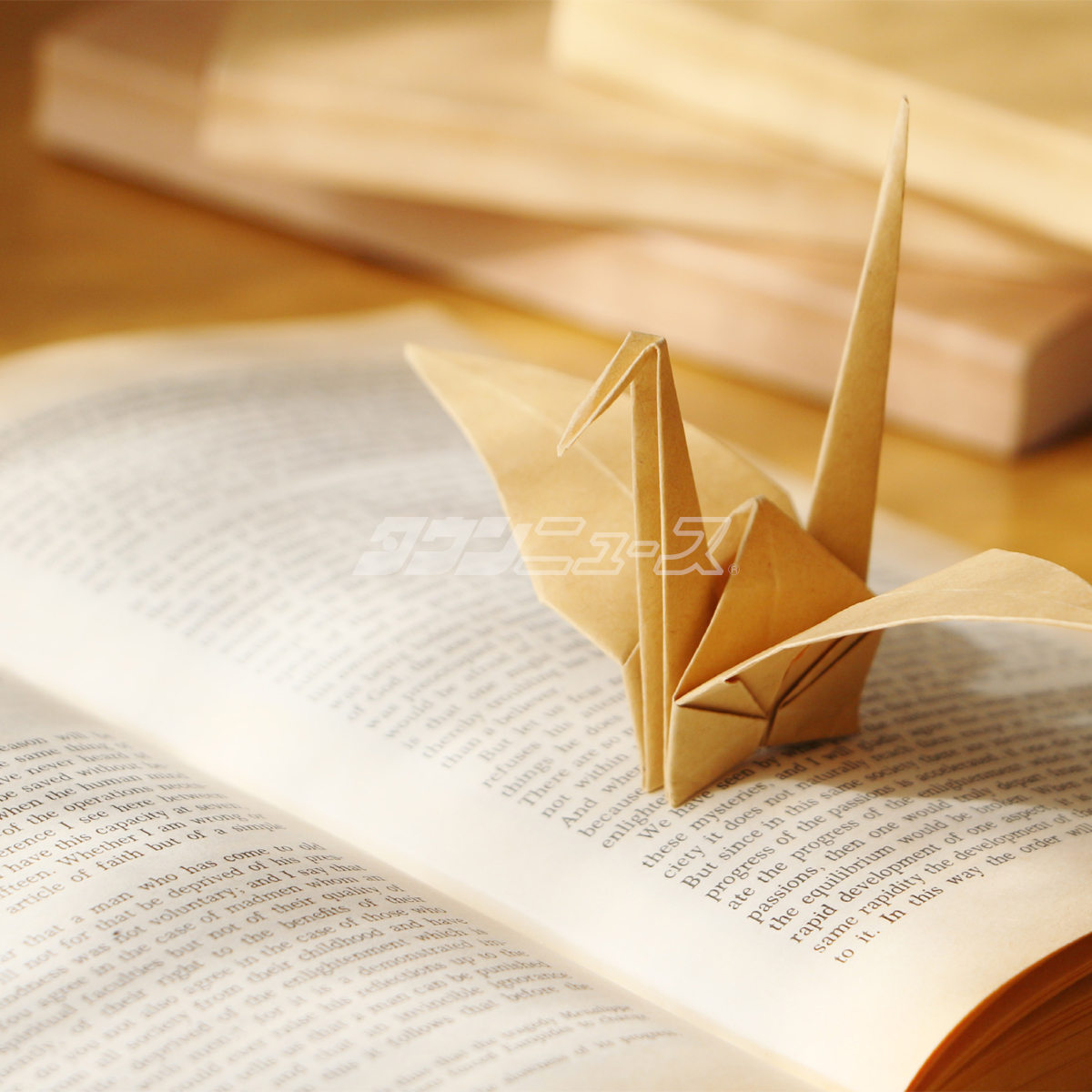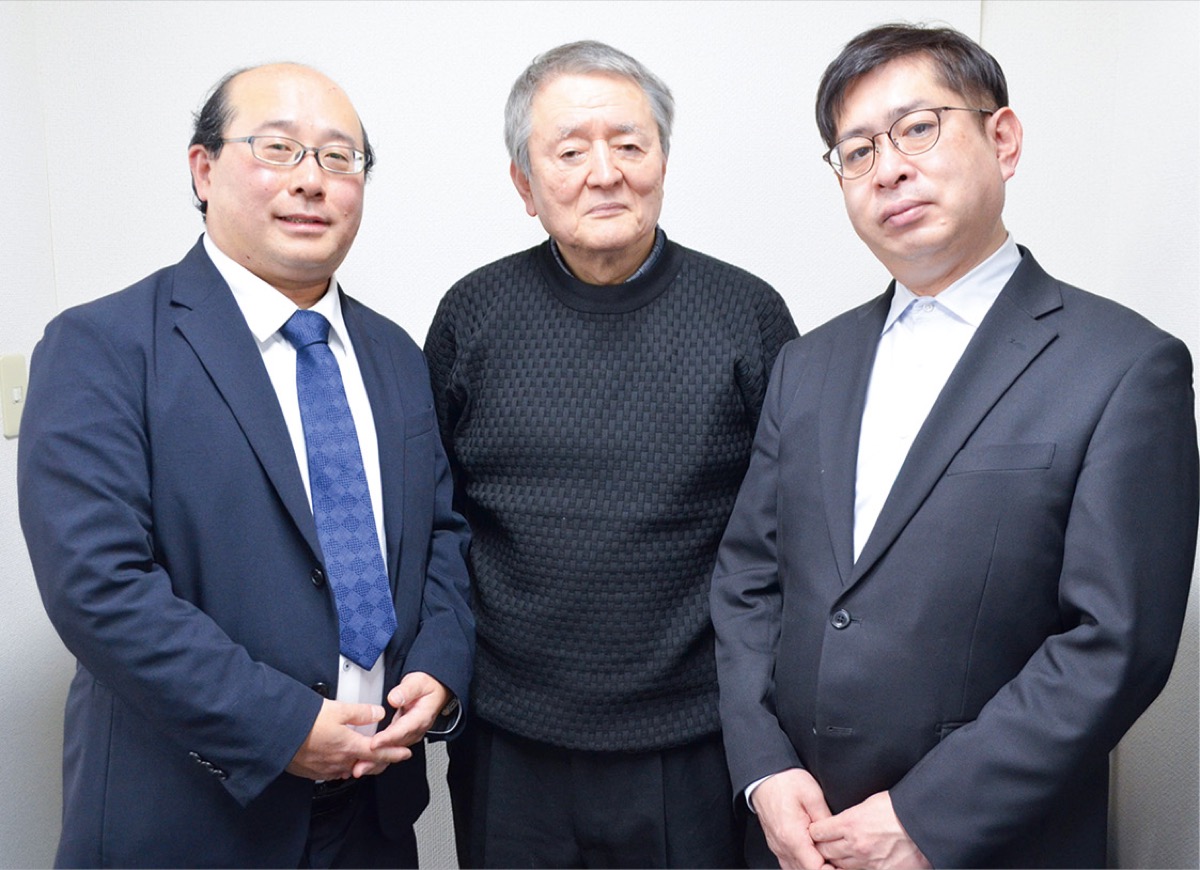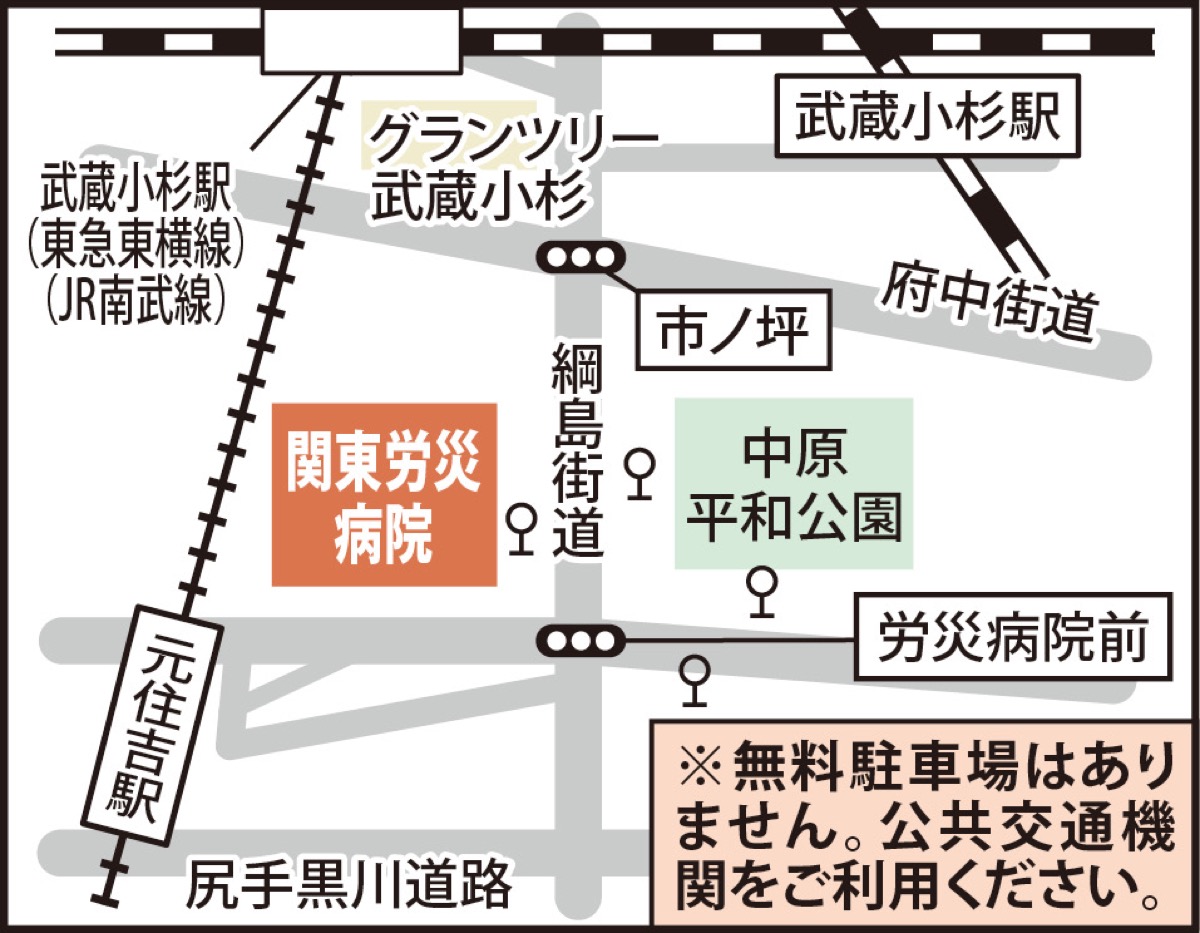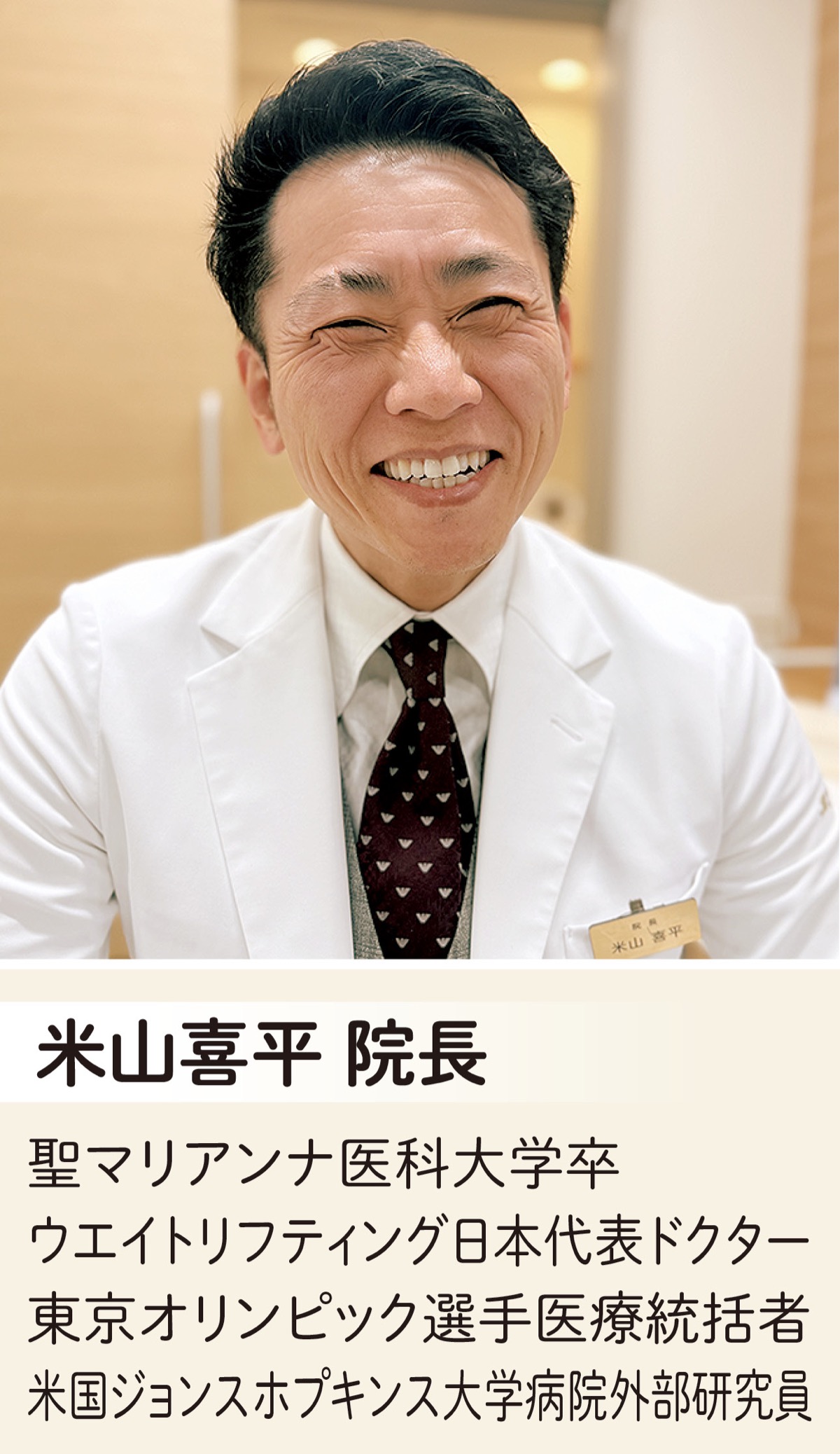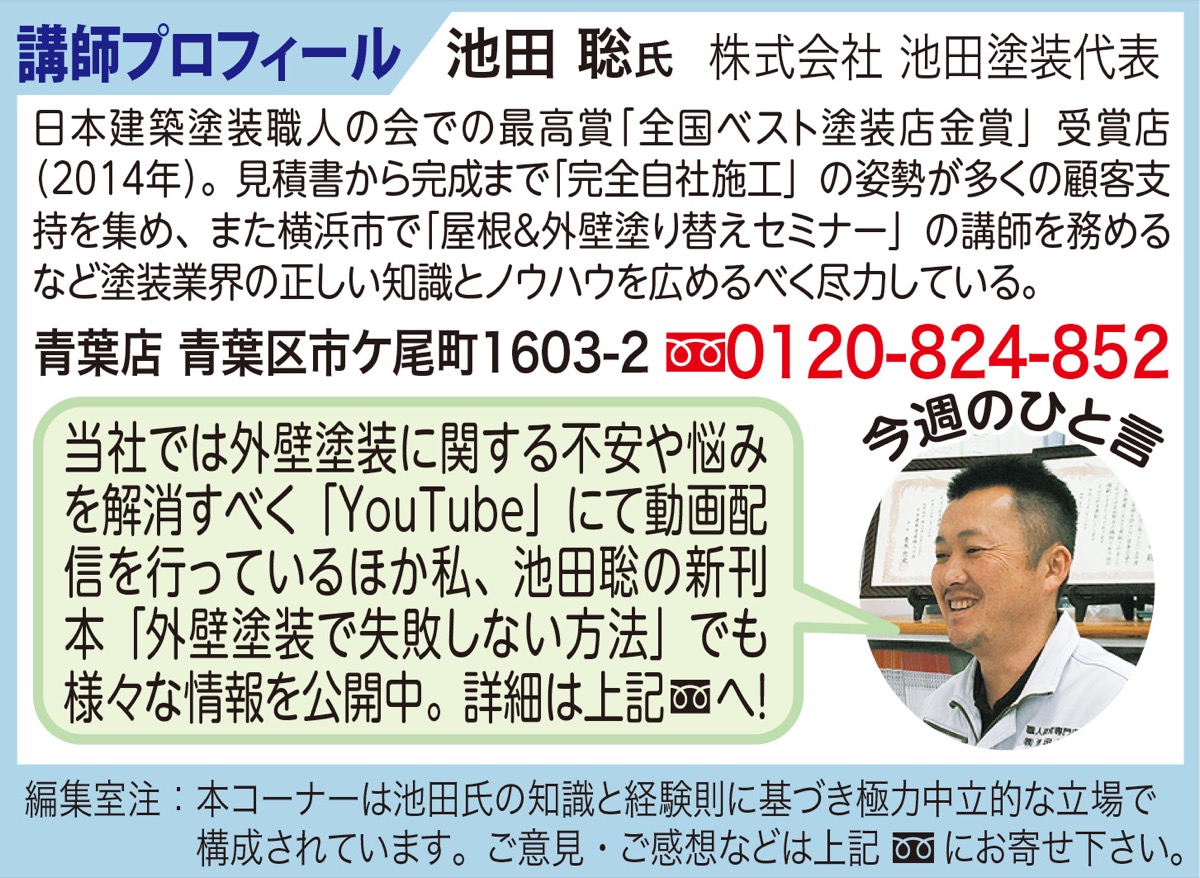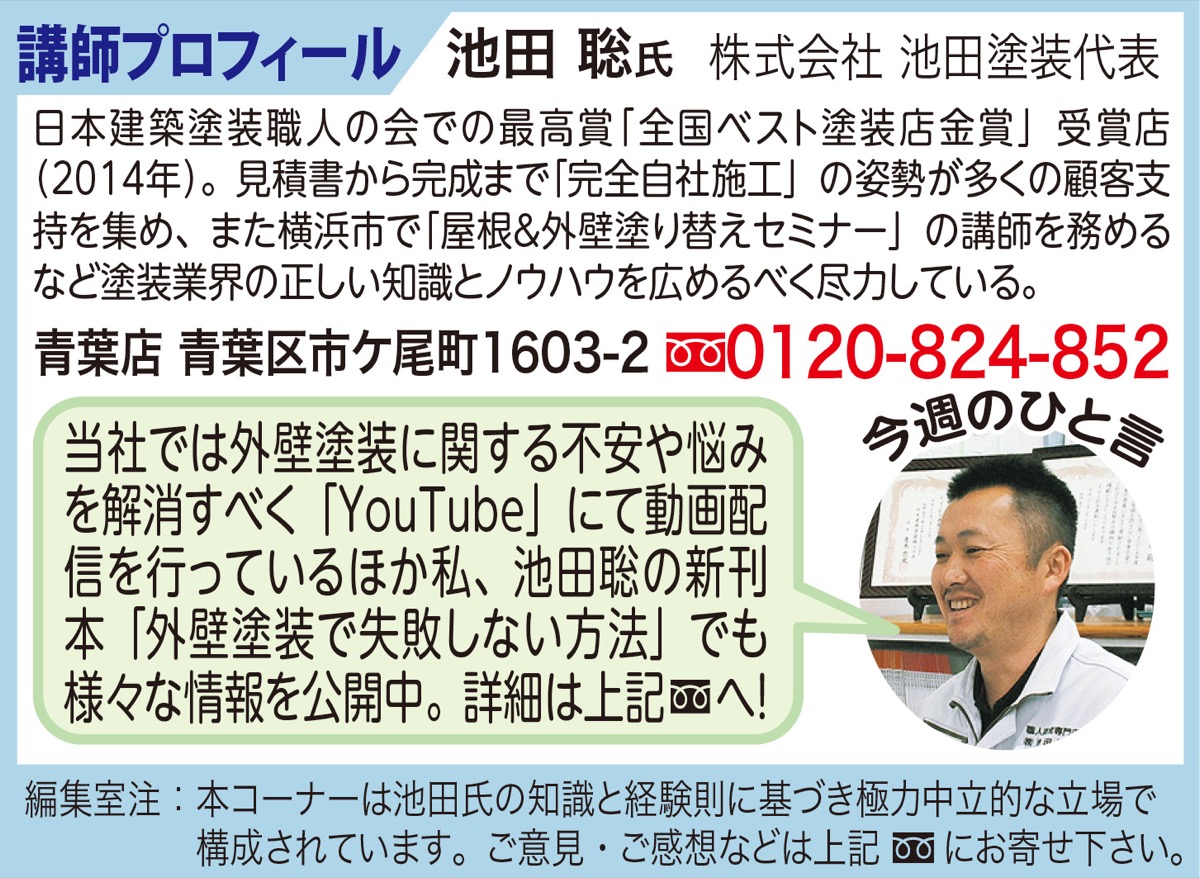青葉区 コラム
公開日:2023.11.09
「硝子体注射とは?」 コラム【28】
悠先生のちょっと気になる目のはなし
加齢黄斑変性症や糖尿病網膜症、網膜中心静脈閉塞症などいずれも眼の奥の方で発症する病気の治療法となる「硝子体注射」。中々聞き慣れない言葉かもしれませんが、硝子体というのは透明なゼリー状の物質で眼の内部はほとんどがこれで満たされています。硝子体注射とは文字通り、注射をして薬剤を硝子体に投与することをいいます。
治療対象となる症状の多くは、黄斑というモノを見る時に非常に大切な働きをする場所の病気です。治療法は、点眼麻酔をした後に角膜(黒目)の縁から30ゲージの細い針を使用して、0・05ミリリットル程の微量な薬剤を硝子体に投与します。針の太さはゲージという単位で表され、数値が大きいほど細くなりますが、通常の点滴などで使用される針は20から22ゲージほどです。30ゲージだと非常に細いため、痛みなどは感じないことがほとんどで、硝子体に薬剤が投与されると黄斑などに作用するのです。
この薬剤が15年程前から使用できるようになり、それまで治療が難しかった前述の病気のコントロールがある程度できるようになりました。
しかし、硝子体注射では、完治するのがなかなか難しかったり、効果が短く注射を繰り返す必要があることや、薬剤の値段が高価だったりと課題はまだまだあると言えるでしょう。
市ケ尾町の「梅の木眼科医院」の加藤悠院長が、目を健康に維持するために大切なことを分かりやすく教えてくれるコーナーです(月1回第2週目に掲載)
ピックアップ
意見広告・議会報告
青葉区 コラムの新着記事
コラム
求人特集
外部リンク
- LINE・メール版 タウンニュース読者限定
毎月計30名様に
Amazonギフトカード
プレゼント! -

あなたの街の話題のニュースや
お得な情報などを、LINEやメールで
無料でお届けします。
通知で見逃しも防げて便利です!