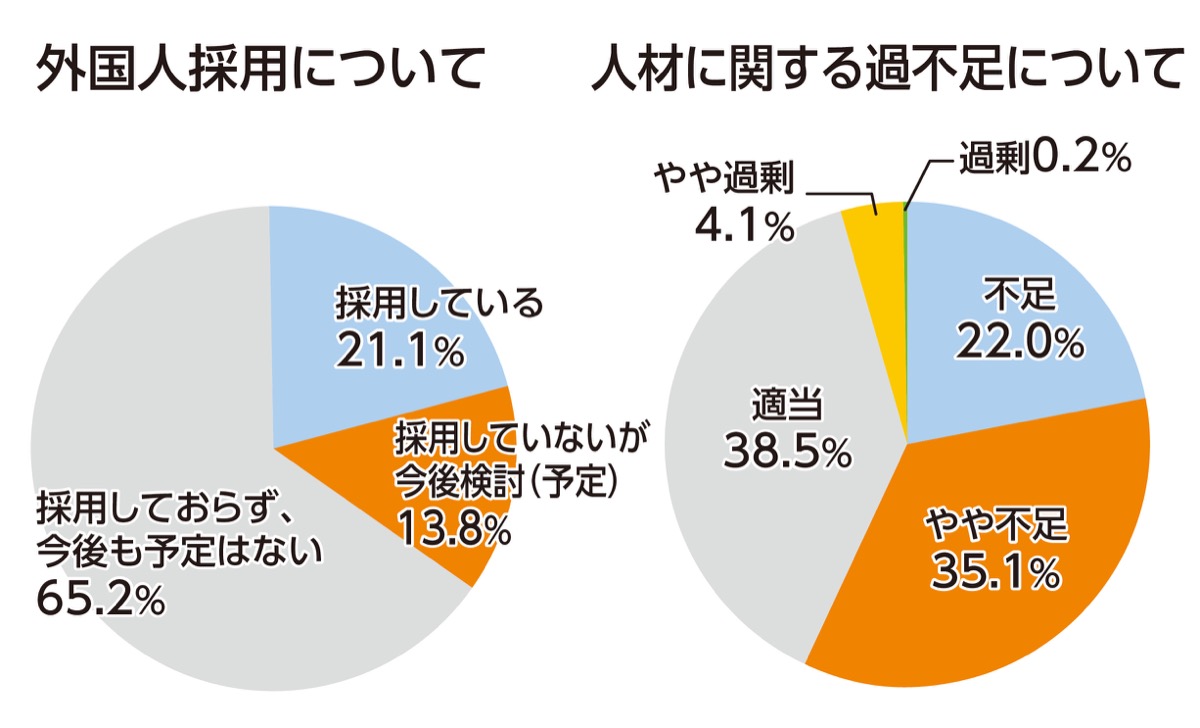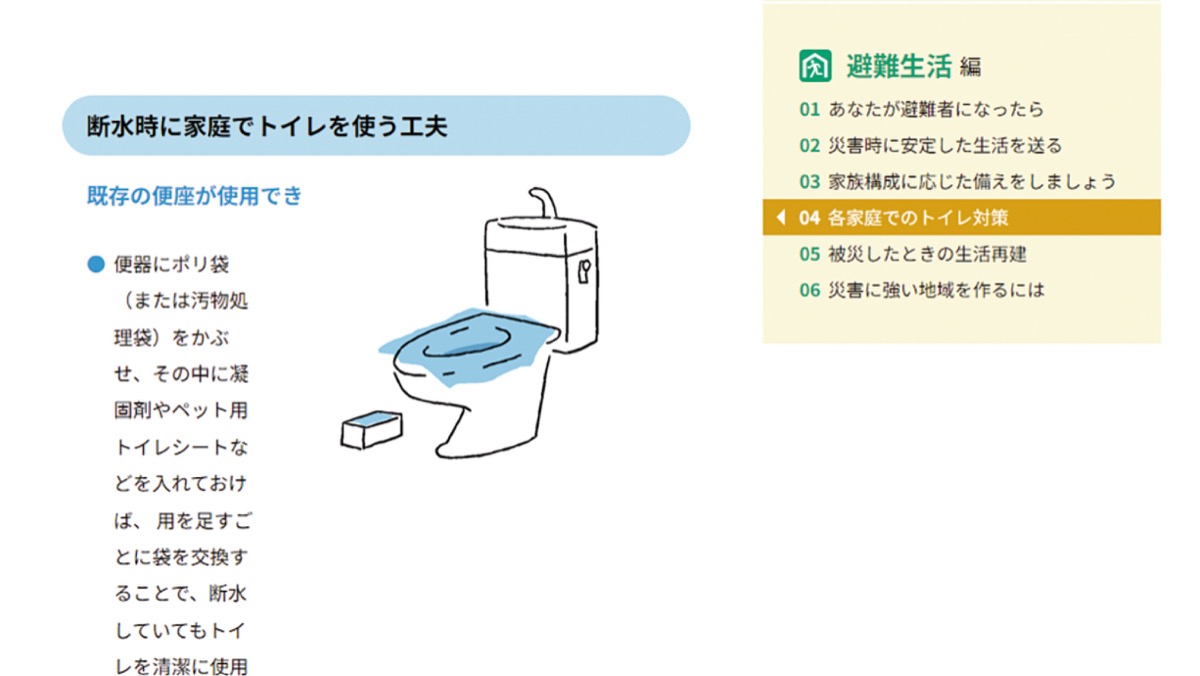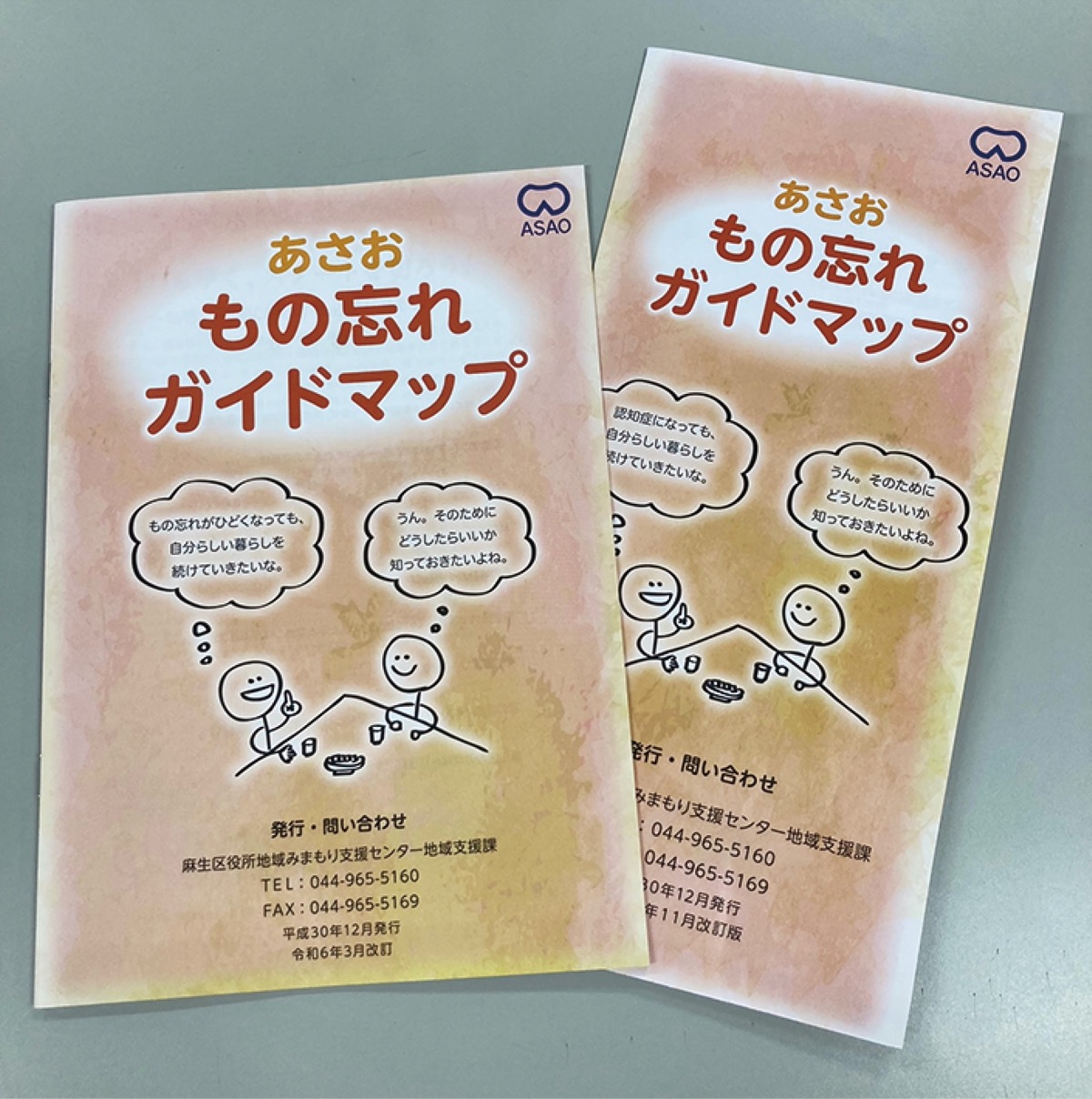麻生区 トップニュース文化
公開日:2021.01.22
ダルマ市
百年超の風物詩も断念
関係者「苦渋の決断」
麻生不動院(下麻生)で毎年1月28日に開催される「ダルマ市」が、今年は中止されることになった。例年、区内外から多くの来場者でにぎわう催しの中止に、関係者や地元住民からも惜しむ声があがる。
「ダルマ市」の原形は江戸、明治の頃から立つようになり、本堂が再建された50年ほど前から、現在のようなにぎわいを見せるようになった。多い年には5万人前後が来場。境内や周辺には、神奈川県内や関東のだるま販売店をはじめ、農機具や飲食の露店も並ぶ。
今年は規模を縮小して開催することを目指し準備を進めていたが、年明けの緊急事態宣言を受けて関係者間で再検討。今月16日に中止を決めた。関係者の一人は「百数十年続くダルマ市の中止は苦渋の決断だが、この状況ではやむを得ない」と肩を落とす。
区民からも残念がる声が寄せられている。上麻生在住の男性は「中止は驚いたが、毎年周辺が混雑することもあり、仕方ないと思う」と話す。
露天商による販売が最初
不動尊は「火伏せの不動」と言われ、火の災害から人を守ると信仰されてきた。不動院の縁日、1月28日にだるまが販売されるようになったのは露天商の影響がある。柿生郷土史料館(上麻生)の機関誌「柿生文化」第92号によると「明治37年(1904)、当時町田能ヶ谷の露天商池田巳之吉が北多摩郡の村山から『だるま』を仕入れ商ったのが最初」という。巳之吉は王禅寺の露天商組合「揚屋一家」の一員で、同第124号には、「揚屋一家」が不動院の沿道を賑わす露天の店を差配していたと記されている。
ピックアップ
意見広告・議会報告
麻生区 トップニュースの新着記事
コラム
求人特集
外部リンク
- LINE・メール版 タウンニュース読者限定
毎月計30名様に
Amazonギフトカード
プレゼント! -

あなたの街の話題のニュースや
お得な情報などを、LINEやメールで
無料でお届けします。
通知で見逃しも防げて便利です!