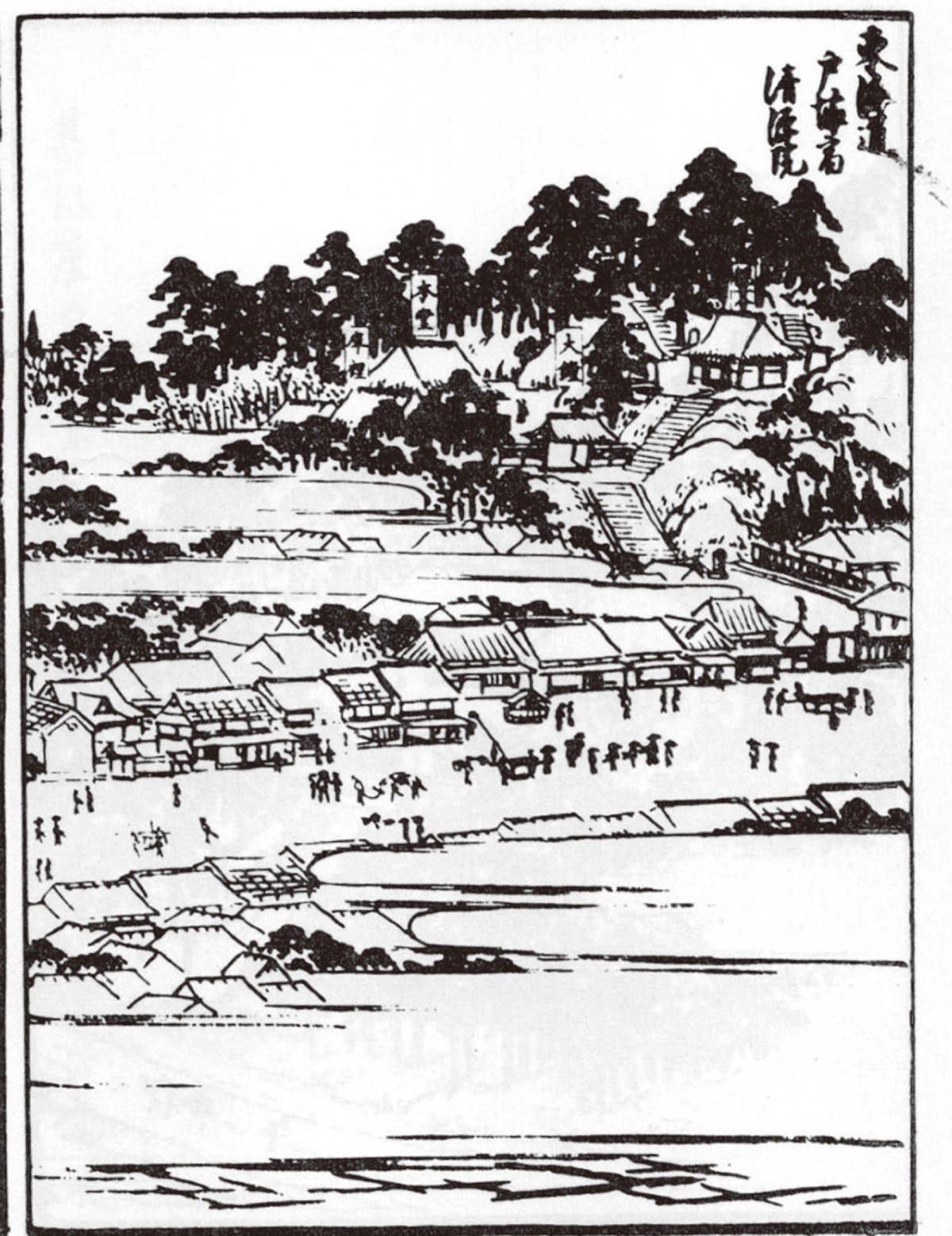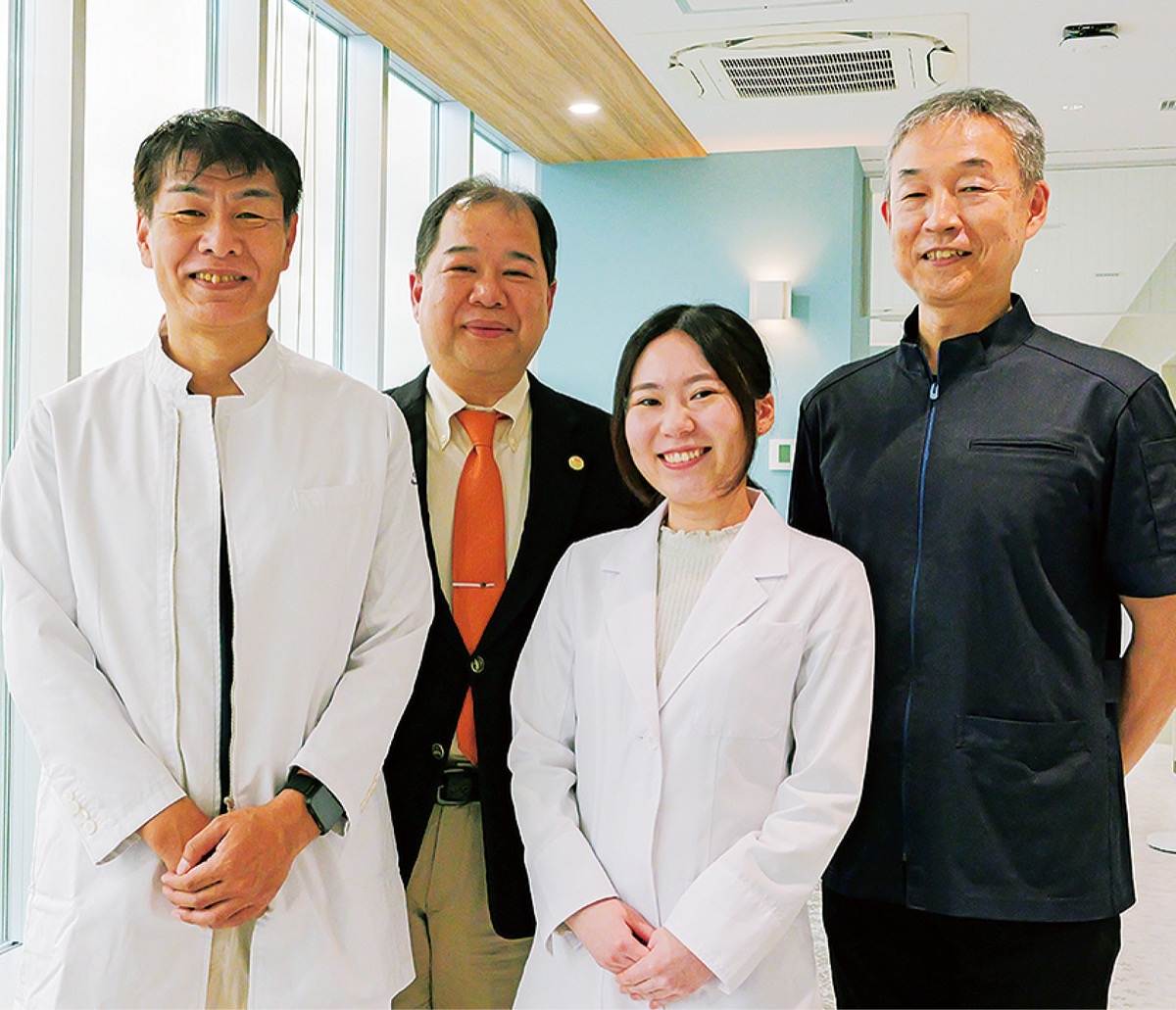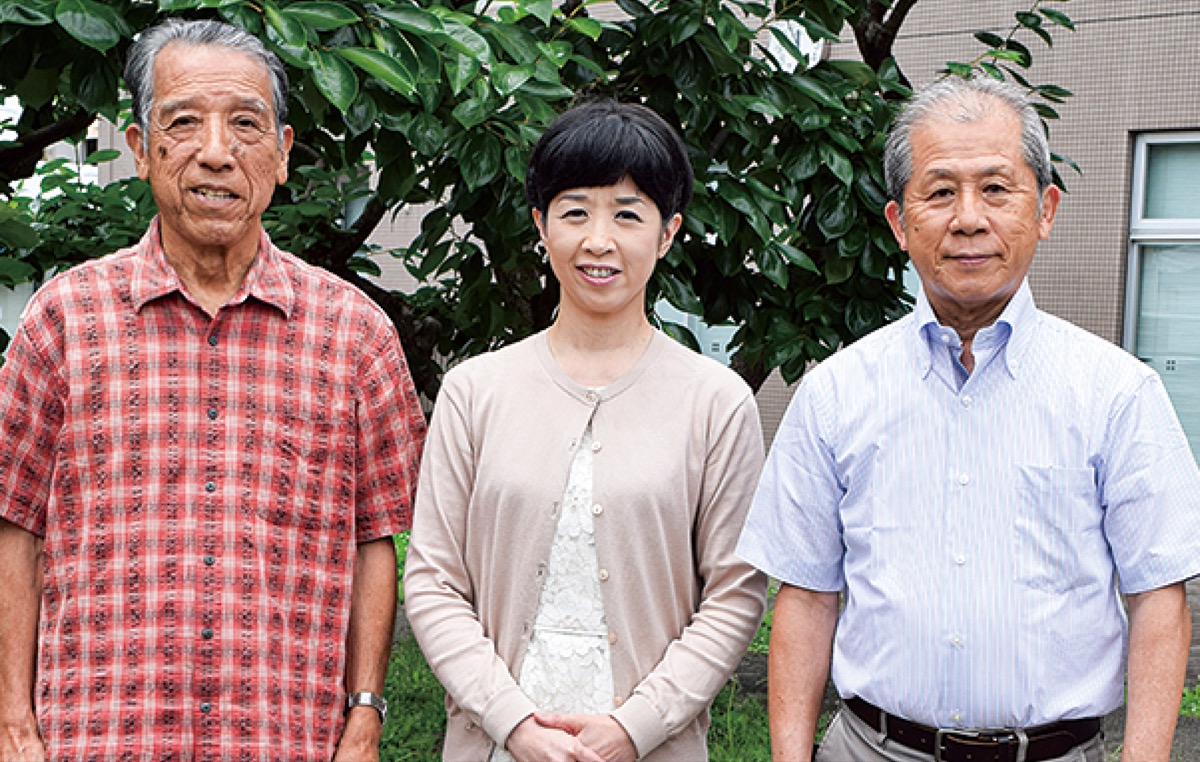大磯・二宮・中井 文化
公開日:2016.09.23
摺師の「命」を生み出す
木版画用ばれん制作 大磯町の後藤さん
絵師と彫師、摺師が三位一体で作り上げる木版画において、摺りの出来を左右するのが「ばれん」と呼ばれる道具だ。大磯町東小磯の後藤英彦さん(63)は数少ない職人として、摺師の命ともいえるばれんの制作を続けている。
後藤さんは、20代のころから現代版画や浮世絵の摺師のもとで修行を積み、1979年にばれん工房「菊英」を創業した。浮世絵文化と密接に関わるばれんの歴史を受け継ぎ、本格的なばれんから代用ばれんの制作販売、修理を手掛けている。注文は国内だけでなく、海外から舞い込むこともあるという。
ばれんは、細く裂いた竹皮を編み込んで渦巻き状にした芯と、約50枚の和紙を蕨のりで張り重ねた当て皮、それらをくるむ包み皮で構成される。摺りの際は、彫りの細かさなどに対応した繊細な摺り分けが求められることから、芯の太さは編みの工程を変えることで超極細から極太まで10種類に及ぶ。実際に、摺師は1枚の版画を摺るのに複数のばれんを使うという。
「摺師の腕はもちろん、ばれんの質によっても仕上がりは全く違うものになる」と後藤さん。中でも芯と包み皮に使う竹が作品に与える影響は大きく、後藤さんが制作に用いる「カシロダケ」は、昔からばれんや茶道具の羽箒(はぼうき)の材料として重宝されてきた。
カシロダケは福岡県八女市にしか存在しない幻の竹といわれるが、近年は需要の低下によって流通業者が減り、竹林の荒廃が進んでいるという。後藤さんは9年ほど前から地権者の了解を得て約2ヘクタールの竹林整備を進め、今では2年に1回、70kgほどの竹皮が手に入るようになった。腐りやシミ、カビがある皮を取り除くと、使用できる量は全体の4割ほど。さらに皮の根本から20cmほどを残し、そこから両端と中央の部分を捨てると、1枚の皮から使える面積は箸紙2枚程度しかない。
ばれんは手入れを行うことで数代にわたって使用でき、多くの摺師は親方から形見分けされたばれんを愛用しているという。中には、江戸時代から使われていたばれんを持つ人もいるほどだ。「丸い形で無駄がなく、江戸時代にこんな合理的なものを作り出す知恵があったことには驚くばかり」。後藤さんはばれんの制作を通して、とこしえの木版画文化を支えてきた伝統技術の継承と向き合っている。
ピックアップ
意見広告・議会報告
大磯・二宮・中井 ローカルニュースの新着記事
コラム
求人特集
大磯・二宮・中井編集室
外部リンク
- LINE・メール版 タウンニュース読者限定
毎月計30名様に
Amazonギフトカード
プレゼント! -

あなたの街の話題のニュースや
お得な情報などを、LINEやメールで
無料でお届けします。
通知で見逃しも防げて便利です!