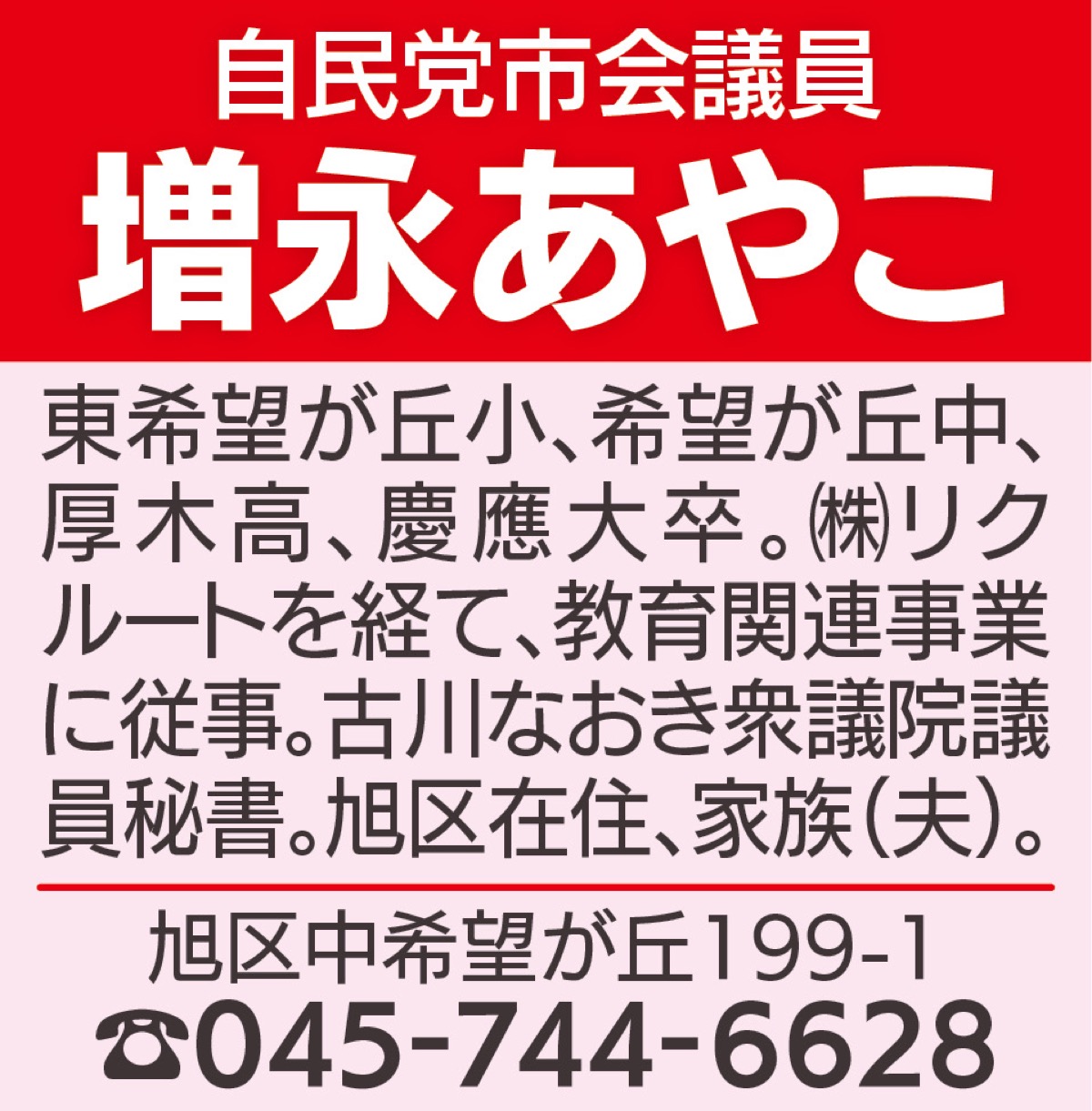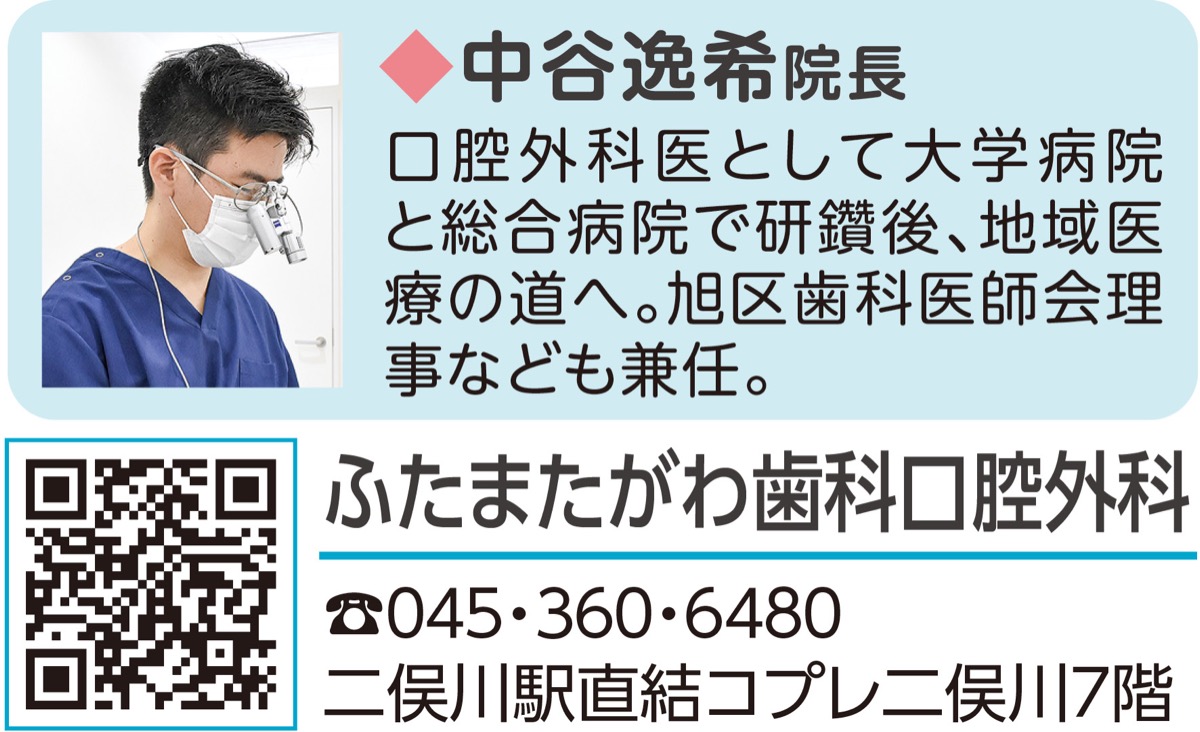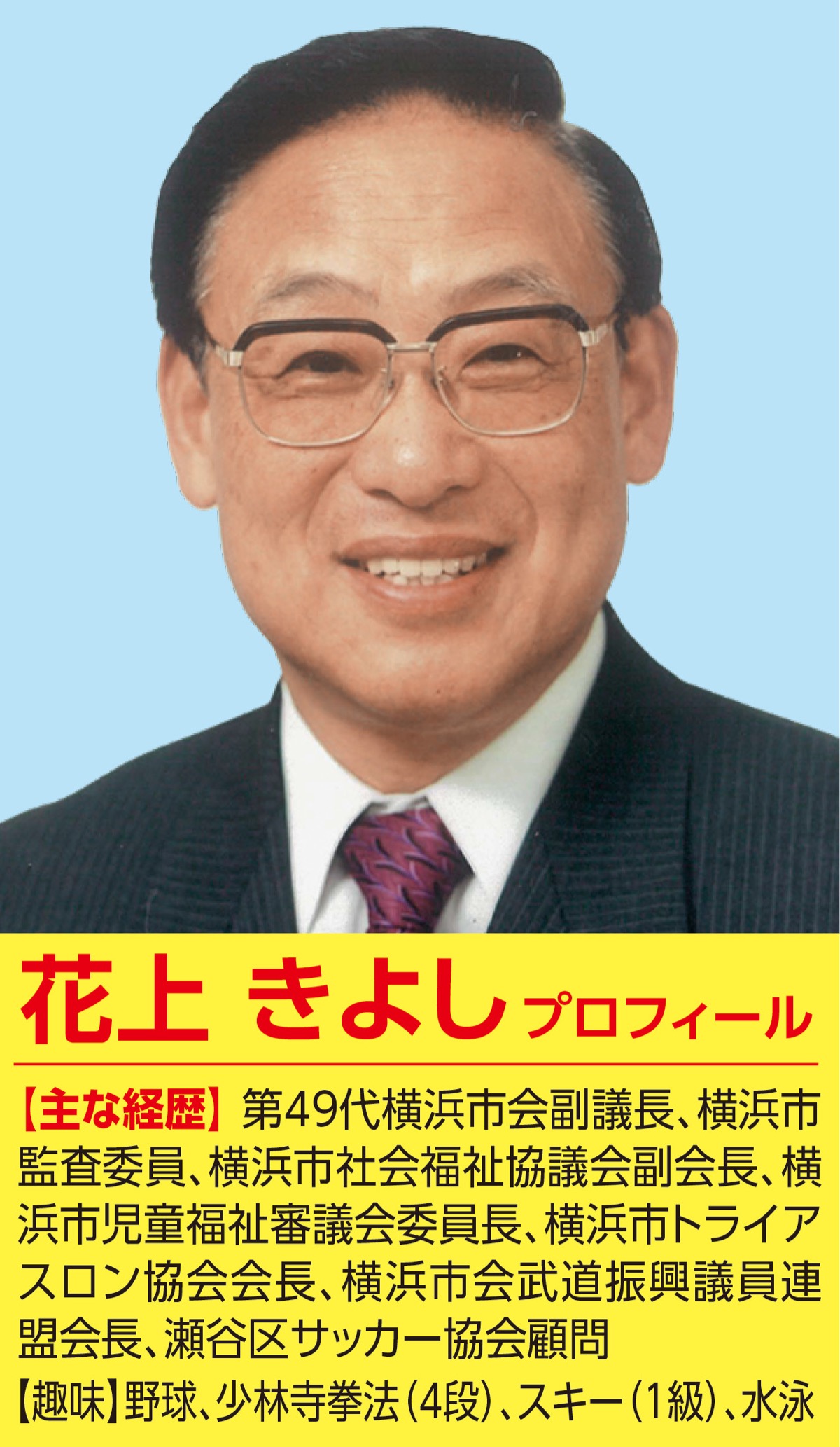旭区・瀬谷区 意見広告
公開日:2024.03.21
市政報告【6】
社会に開かれた「チーム学校」の実現を〜横浜中2女子いじめ事案から私たちが学ぶべきこと〜
横浜市会議員 増永あやこ
横浜市は今月、令和元年度に中学2年の女子生徒が自ら命を絶った事案を発表しました。遺書が見つかり、いじめが原因だったことが死後に分かりましたが、不登校だった当時はいじめとしての認定がなく、後から基本調査が始まり、結果発表まで4年もの歳月を要してしまいました。
今回私は、こども青少年・教育委員会の委員として、なぜこのような事態になってしまったのか質問しました。失った命は戻りません。どんな言い訳も通用しません。事後対応の課題についても言及しましたが、一番大切なのは未来に向かい、この生徒の死から何を学ぶかです。今後できうる限りの施策を打たなければならないと思います。
私は、学校の在り方から見直していくことが重要だと考えています。担任の先生一人に全てを背負わすのではなく、社会に開かれた「チーム学校」で行う生徒指導体制の構築が、求められているのではないかと思います。
私が教員を務めていた頃、学校における学級はブラックボックス化しやすい、と感じました。教師が「学級王国」をつくってしまいやすい。担任一人が頑張り、他の先生には相談しにくい雰囲気を感じたこともありました。だからこそ、自分の学級に不登校の児童がいれば、担任の責任とみなされやすくなってしまう傾向にあると感じます。
生徒も一人の人間ですし、人間同士相性もあります。現状、学校現場では担任の先生が一人で1クラス35人もの児童を受け持つことになっており、生徒が「合わない」と感じれば、少なくとも1年間はそのままになります。しかし、教員はもちろん、様々な専門職員や地域の方々が関わり、様々な大人が寄り添う体制があれば、「あの先生に相談しようかな」「地域の〇〇さんに話してみよう」と、子どもに選択肢が増えます。自らの命を絶つ前に、SOSを出しやすくなるのではないでしょうか。
今、旭区では、約1万6500人もの子どもたちが公立小中学校に通っています。地域の皆さん一人ひとりが、未来を担う子どもたちに関わっていただきたいです。
増永あやこ
-
横浜市旭区中希望が丘199-1
TEL:045-744-6628
ピックアップ
意見広告・議会報告
旭区・瀬谷区 意見広告の新着記事
コラム
求人特集
- LINE・メール版 タウンニュース読者限定
毎月計30名様に
Amazonギフトカード
プレゼント! -

あなたの街の話題のニュースや
お得な情報などを、LINEやメールで
無料でお届けします。
通知で見逃しも防げて便利です!