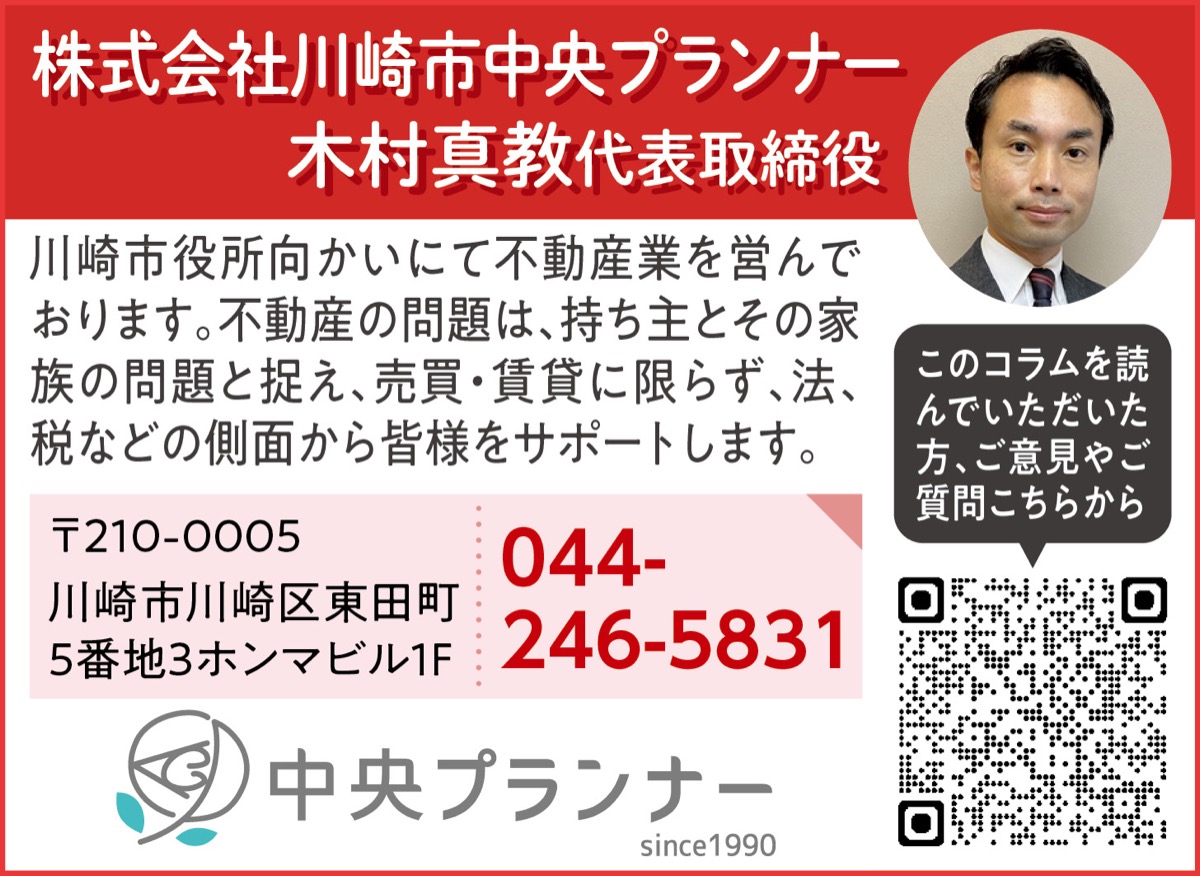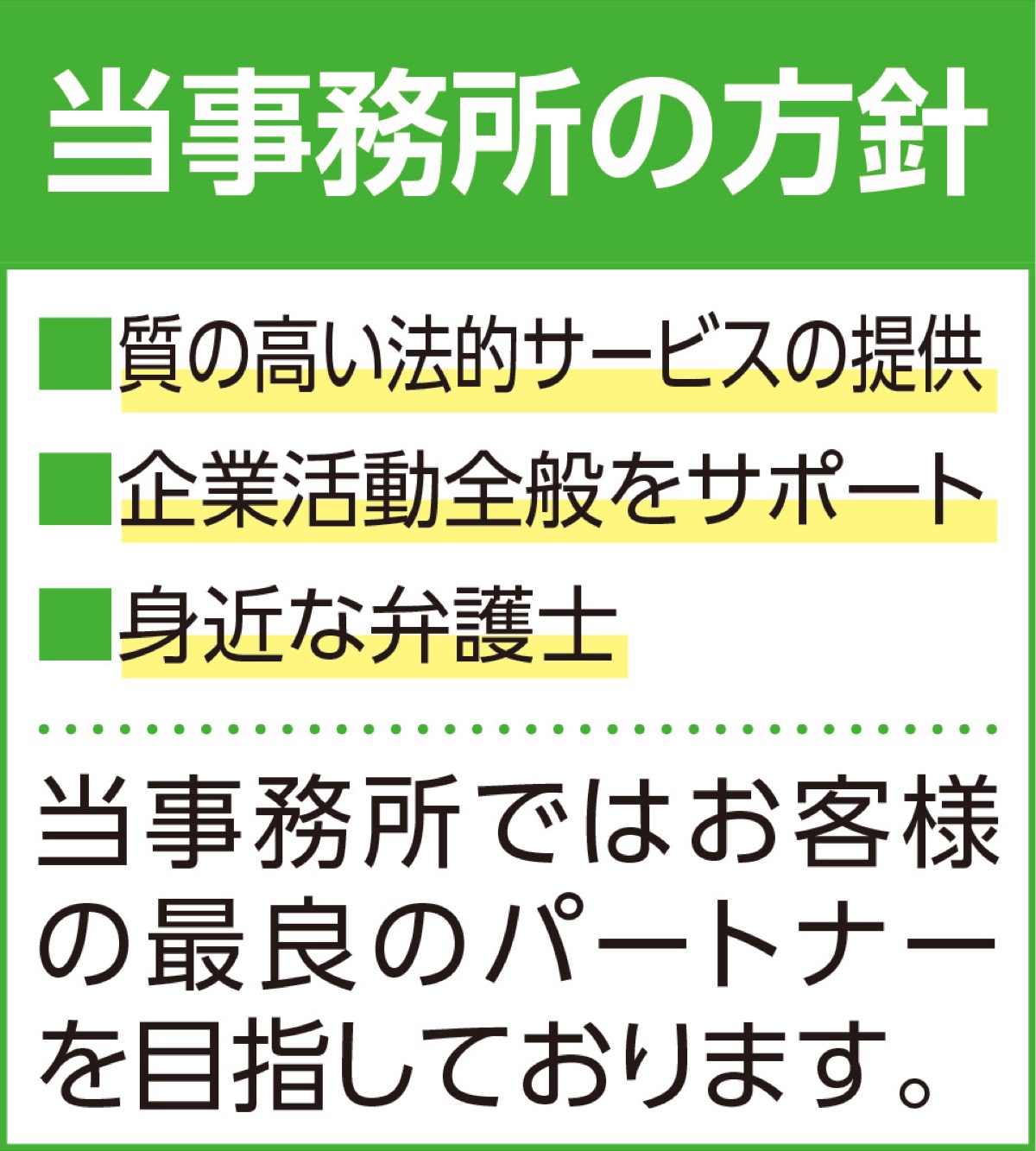川崎区・幸区 トップニュース社会
公開日:2024.05.31
幸区社協
災害VCに住民参加促す
福祉計画の重点項目に
幸区社会福祉協議会は、今年度から3年間かけて実施する「地域福祉活動計画」を策定した。重点取り組みのひとつに「災害ボランティアセンター」(災害VC)を掲げ、地域住民の運営参加を促す。市内では独自の取り組みで、災害時に予想される人出不足や周知不足いった課題の解決を狙う。
災害VCは、災害が発生した際に、被災地域を支援するため、臨時的・応急的に開設されるボランティアセンター。ボランティアと被災者のニーズをつなぐことが役割となる。川崎市では主に社協が主体となり設置・運営が行われるが、災害時は職員も被災するため人材不足が課題と指摘されている。
幸区社会福祉協議会の大竹薫事務局長は、発生が懸念されている南海トラフ地震や首都直下地震が起きた場合、多摩川と鶴見川に挟まれ、東西は線路で隔てられている幸区は外部から孤立する可能性が高いという。橋や鉄橋の倒壊、密集する家屋が崩れ道路を塞ぐなど、外部からの支援が滞ると考えられる。
「そういった状況で災害時に出るニーズに対応していくには社協職員だけでは負担が大きい。地域住民の方々の協力は重要」と大竹さん。地域住民が運営に加わることで、地域でしか分からない情報を復旧・復興につなげられるというメリットも生まれる。また、平常時に行う訓練などで災害VCの役割も周知することもできる。
聞き取り業務を実践
幸区社協では、昨年12月に住民らに災害VCに関する研修を行い、今年2月に行った防災訓練では約20人が参加し、初めて運営業務を行った。
訓練では、被災者から「地震で家財道具が倒れ移動を手伝ってほしい」「仮設住宅への入居が決まり、引越しを手伝ってほしい」といった困りごとの聞き取りを行い、ボランティアへつなぐ調査票への記入する作業を行った。
大竹さんは「参加者からは『初めてで聞き取りが難しかった』という声も聞かれたが、運営に関する改善点も見つかった。覚えることも多いので、まずは地域の中でもリーダーとなるような人を中心に運営の仕方を学んでもらい、徐々に地域に広めていきたい」と語った。
ピックアップ
意見広告・議会報告
川崎区・幸区 トップニュースの新着記事
コラム
求人特集
- LINE・メール版 タウンニュース読者限定
毎月計30名様に
Amazonギフトカード
プレゼント! -

あなたの街の話題のニュースや
お得な情報などを、LINEやメールで
無料でお届けします。
通知で見逃しも防げて便利です!