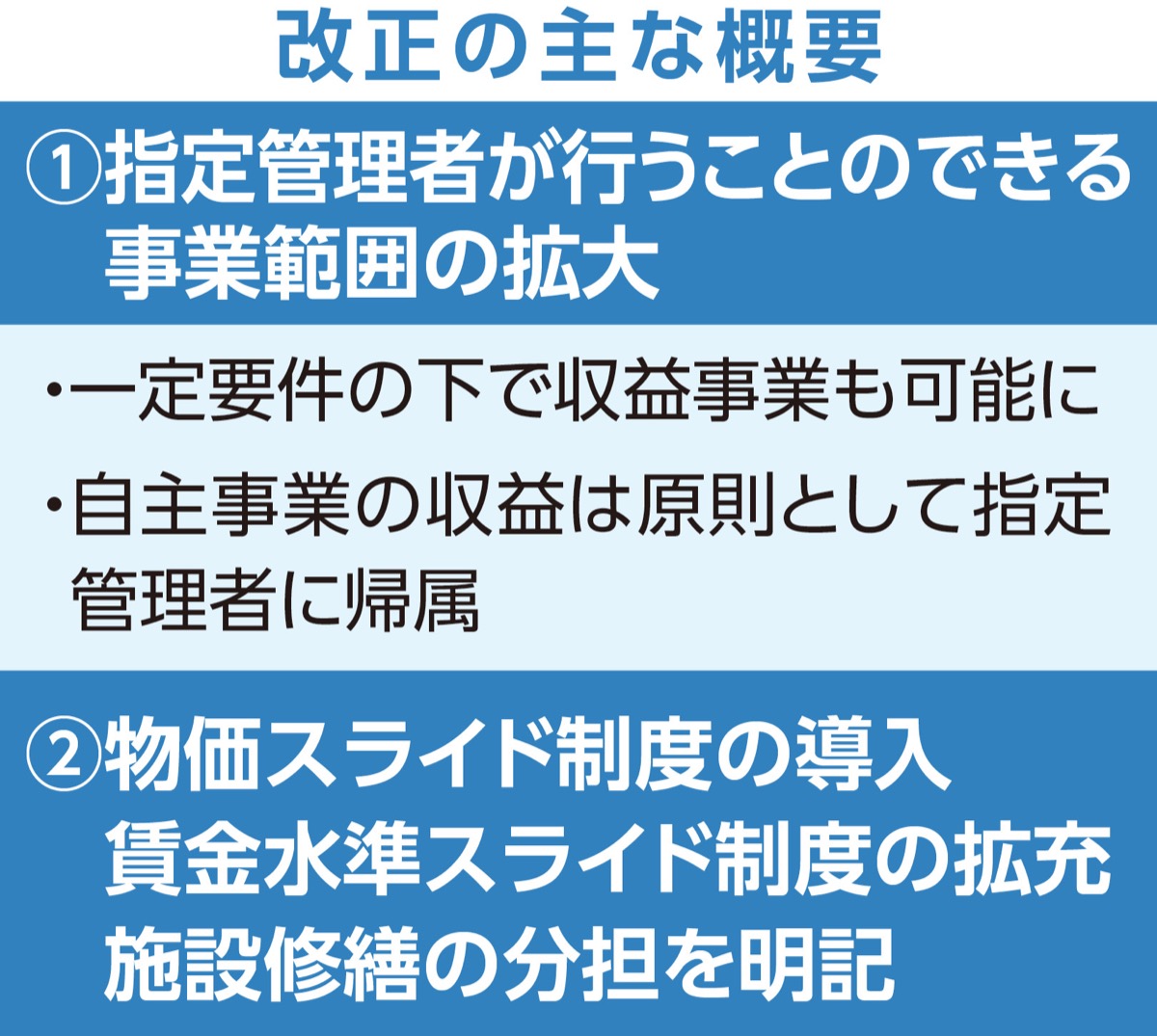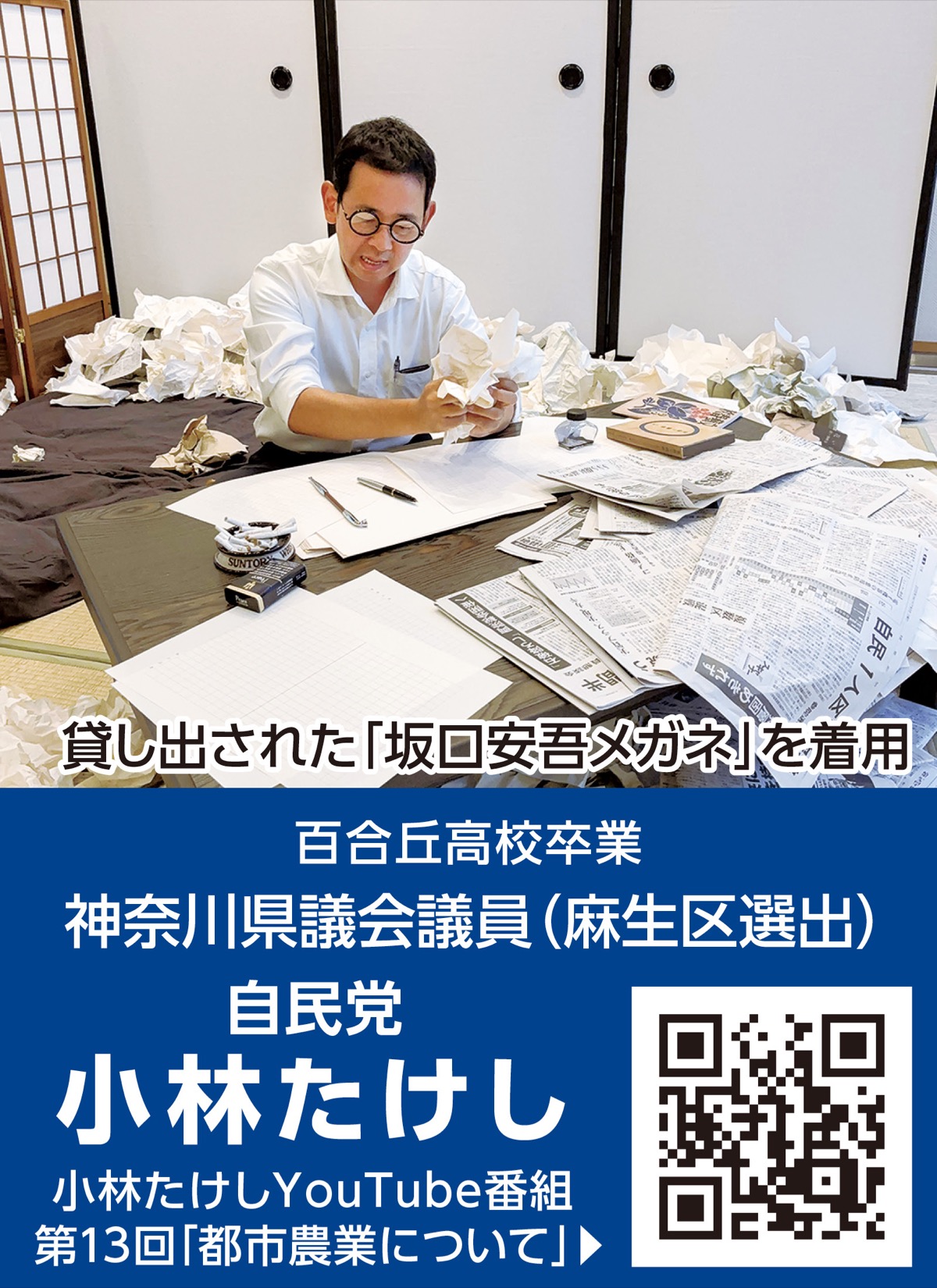多摩区・麻生区 トップニュース社会
公開日:2016.05.20
明治大農学部
アスパラ新栽培 普及へ
産学連携で実用化めざす
品質や収量の向上を掲げたアスパラガスの新栽培法を、明治大学農学部の野菜園芸学研究室が14日、東三田の生田キャンパスで発表した。研究室の元木悟准教授や学生、企業が協力し、4年前に共同研究を開始。生産者の拡大に向け、来春の実用化を目指す。
「採りっきり栽培」と呼ばれる新栽培法では、定植から収穫まで通常3年かかる工程を1年に短縮。初年度に株を養成すれば、翌春に全て収穫する(採りきる)ため長期管理が不要で、経験の少ない農家でも始められる手軽さが特徴だ。
春から秋にかけて出る新芽の若茎を食べるアスパラガスは、特有の甘みと風味があり、優れた機能性野菜とも言われている。通常の露地栽培では10年から15年かけて繰り返し株を養成するため手間がかり、病害虫の防除が難しいとされるが、新栽培法では株を毎年更新するため、病気のリスク軽減が見込める。
全国各地で新栽培法の発表会を行う元木准教授は「アスパラガスの生産者はまだ少なく、(収穫期の)春先でも店頭であまり見られないケースもある」とし、「新規就農者にも適しており、導入してくれる農家があれば来春には実用化したい」と期待を込める。
発表会に150人超
14日には同研究室と連携企業のパイオニアエコサイエンス(株)(東京都港区)による発表会が開かれ、農業や市場、流通関係者、学生ら150人以上が参加。生田キャンパス内の圃場(畑)で、アスパラガスの株養成や収穫の状況が公開された後、元木准教授や同社担当者らにより新栽培法の現状と展望について説明された。
千葉県の実家がアスパラガス農家で、昨年から同研究室に所属する大学院博士前期課程2年の蕪野(かぶの)有貴さん(23)は「新栽培法のアスパラは甘くて太いのが特徴。より多くの農家に取り組んでもらい、アスパラがもっと広まれば」と語った。
ピックアップ
意見広告・議会報告
多摩区・麻生区 トップニュースの新着記事
コラム
求人特集
外部リンク
- LINE・メール版 タウンニュース読者限定
毎月計30名様に
Amazonギフトカード
プレゼント! -

あなたの街の話題のニュースや
お得な情報などを、LINEやメールで
無料でお届けします。
通知で見逃しも防げて便利です!